2018年11月08日
『シザーハンズ』:コクのあるおとぎ話
データ
『シザーハンズ』EDWARD SCISSORHANDS
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:1991年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後数回ビデオで鑑賞し、映画館で再視聴。
監督:ティム・バートン
音楽:ダニー・エルフマン
俳優:ジョニー・デップ(エドワード・シザーハンズ) ウィノナ・ライダー(キム)
ダイアン・ウィースト(ペグ) アンソニー・マイケル・ホール キャシー・ベイカー
アラン・アーキン ヴィンセント・プライス
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

コメント・批評
午前十時の映画祭で上演していたので、久しぶりに鑑賞。
やはりコクがあっておもしろいな、この作品は、と再確認しました。
雪の華が散る場面でウィノナ・ライダーさんが踊る場面は映画史に残る美しさ。
本作はカップルがクリスマスに観る映画として最適です。
でも、ただのロマンティック話ではありません。
本作は、まるで映画のセットのような(セットなのですが:笑)キッチュな街並みを映し出すことから始まります。
その後も、エドワーズの住む山を除けば、ほぼこのキッチュな「世界」で物語は進行します。
おとぎ話の衣装を映画の身にまとわせて、その実、現実世界こそがキッチュだと監督は言うかのようです。
映画の中で根っからの善人はエドワード(ジョニー・ディップさん)ただ一人。
山からやってきた人造人間。
なのにキッチュな世の中でただ一人だけ「実存」する。
もちろん現実にそんな人類は存在しませんし、
存在したとしたら、ふつうの生き方では生存できませんから、
創造主の科学者は彼に武器/凶器にも使えるシザーを与えたわけです。
ところが創造主は何の気まぐれか、
エドワードならやっていけると考えたのか、
自分の死期を悟って、愛される姿に変えて野に放とうと思ったのか、
創造主は考えを変えて、シザーの替わりにホンモノの腕を用意。
でも遅過ぎました。
終盤で、シザーは本物の凶器となり、人を殺めます。
しかしその野蛮は一瞬で終わり、愛する人は傷つけません。
その後は毎年クリスマスの時期に雪を降らせるという優しい使い道がシザーハンズの役目。
エドワードはおそらく永遠に生き続けることでしょう。
ホンモノの腕を持っていたならキッチュにまみれ、きっと長生きはできなかったはず。
だとすると、遅過ぎたわけではなかったのでしょうか。それとも、
愛されることがなかった淋しさは死ぬより辛かったでしょうか。あるいは、
愛されているはずだと信じて氷を削り続けたのでしょうか。
エドワードがシザーハンズという武器を持っていることには、たくさんの示唆が含まれています。
例えば現存するほとんどの国家は国家軍(名称が国防軍であろうと自衛隊であろうと)を有しています。
軍事力を持った国家が他の国家国民から愛され敬意を払われることがありうるでしょうか。
真に友好的な外交は、軍事力というシザーハンズを捨て、やさしく相手をハグできる手に付け替えることでしか実現できないのではないでしょうか。
とかね。
全編を通じて、アイロニーに充ちたオトナの映画。
このような「毒素」を、最近のティム・バートンさんは失ってしまったように見えます。
最初の鑑賞時、出演者の中で、ダイアン・ウィーストさんの演技がいちばん印象に残りました。
キム(ウィノナ・ライダー)さんの母親ペグ役。
エドワードを一人かばい、家に迎え入れた理解者です。
彼女がキッチュな街並みのご近所さんのドアチャイムを鳴らし、「エイボンレディー」と告げる場面から、私はこの映画の世界に取り込まれたのでした。
のちに、彼女がアカデミー助演賞を二度受賞した女優だと知った時は、そりゃあそうだろうなと思いました。
『シザーハンズ』EDWARD SCISSORHANDS
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:1991年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後数回ビデオで鑑賞し、映画館で再視聴。
監督:ティム・バートン
音楽:ダニー・エルフマン
俳優:ジョニー・デップ(エドワード・シザーハンズ) ウィノナ・ライダー(キム)
ダイアン・ウィースト(ペグ) アンソニー・マイケル・ホール キャシー・ベイカー
アラン・アーキン ヴィンセント・プライス
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

コメント・批評
午前十時の映画祭で上演していたので、久しぶりに鑑賞。
やはりコクがあっておもしろいな、この作品は、と再確認しました。
雪の華が散る場面でウィノナ・ライダーさんが踊る場面は映画史に残る美しさ。
本作はカップルがクリスマスに観る映画として最適です。
でも、ただのロマンティック話ではありません。
本作は、まるで映画のセットのような(セットなのですが:笑)キッチュな街並みを映し出すことから始まります。
その後も、エドワーズの住む山を除けば、ほぼこのキッチュな「世界」で物語は進行します。
おとぎ話の衣装を映画の身にまとわせて、その実、現実世界こそがキッチュだと監督は言うかのようです。
映画の中で根っからの善人はエドワード(ジョニー・ディップさん)ただ一人。
山からやってきた人造人間。
なのにキッチュな世の中でただ一人だけ「実存」する。
もちろん現実にそんな人類は存在しませんし、
存在したとしたら、ふつうの生き方では生存できませんから、
創造主の科学者は彼に武器/凶器にも使えるシザーを与えたわけです。
ところが創造主は何の気まぐれか、
エドワードならやっていけると考えたのか、
自分の死期を悟って、愛される姿に変えて野に放とうと思ったのか、
創造主は考えを変えて、シザーの替わりにホンモノの腕を用意。
でも遅過ぎました。
終盤で、シザーは本物の凶器となり、人を殺めます。
しかしその野蛮は一瞬で終わり、愛する人は傷つけません。
その後は毎年クリスマスの時期に雪を降らせるという優しい使い道がシザーハンズの役目。
エドワードはおそらく永遠に生き続けることでしょう。
ホンモノの腕を持っていたならキッチュにまみれ、きっと長生きはできなかったはず。
だとすると、遅過ぎたわけではなかったのでしょうか。それとも、
愛されることがなかった淋しさは死ぬより辛かったでしょうか。あるいは、
愛されているはずだと信じて氷を削り続けたのでしょうか。
エドワードがシザーハンズという武器を持っていることには、たくさんの示唆が含まれています。
例えば現存するほとんどの国家は国家軍(名称が国防軍であろうと自衛隊であろうと)を有しています。
軍事力を持った国家が他の国家国民から愛され敬意を払われることがありうるでしょうか。
真に友好的な外交は、軍事力というシザーハンズを捨て、やさしく相手をハグできる手に付け替えることでしか実現できないのではないでしょうか。
とかね。
全編を通じて、アイロニーに充ちたオトナの映画。
このような「毒素」を、最近のティム・バートンさんは失ってしまったように見えます。
最初の鑑賞時、出演者の中で、ダイアン・ウィーストさんの演技がいちばん印象に残りました。
キム(ウィノナ・ライダー)さんの母親ペグ役。
エドワードを一人かばい、家に迎え入れた理解者です。
彼女がキッチュな街並みのご近所さんのドアチャイムを鳴らし、「エイボンレディー」と告げる場面から、私はこの映画の世界に取り込まれたのでした。
のちに、彼女がアカデミー助演賞を二度受賞した女優だと知った時は、そりゃあそうだろうなと思いました。
2018年11月06日
『Vision ビジョン』
データ
『Vision ビジョン』
評価:☆☆☆・・・・・・・
年度:2018年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:河瀬直美
音楽:小曽根真
俳優:ジュリエット・ビノシュ 永瀬正敏 森山未來 夏木マリ 岩田剛典 田中泯 白川和子 ジジ・ぶぅ
製作国:日本、フランス
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
たいへん残念な映画でした。
作品になっていません。
わたしの家には河瀬直美さんの「空」の文字の書が飾られています。
退職祝いに友人が贈ってくださったのですが、
まるでパンダかアナグマの顔のような悠々としてどこかとぼけたその書はとても素敵です。
河瀬さんの映画もたとえば『あん』は傑作だと考えています。
ところが本作はどうしたことでしょう。
悠々とした、あるいは超然とした、河瀬さんのどこか俯瞰的な視点が消え、
あざとく、あるいは焦った印象がぬぐえません。
これだけの役者を揃えているのに、世界観が自立しているように見えるのは夏木マリさんだけで、後の方々はとても断片的な存在でした。(☆一つ分は夏木さんに捧げます)
ハーモニーがないのです。
どういう映画を作りたいのか、という意志が見えないのです。
聞けば、みなさん吉野の山で暮らしてから撮影したとか。
もしかして山に同化されて背景になってしまいましたか。
それとも、言い過ぎかもしれませんが、賞獲りを狙いすぎましたか。
「ビジョン」という事象・概念の用語は作中で日本語としても使われるのですが、これには違和感がありすぎました。
「びじょん」という語感の古来からの日本語はちょっと思い当たりません。
延々と吉野の杉の森の映像が映し出されます。
それはそれは美しい風景ですが、あくまで人工林です。
ところが、作中でパワースポット的に描かれる場所は杉林ではないのです。
わたしの目にも、いいところ見つけましたなあ、さすが河瀬さん、森山未來さんの呪術的な踊りにふさわしい、
と思うのですが、そこは谷あいの雑木林?スポット。
では吉野杉の人工美林は何のために長回しを?
海外へのアピールとしか思えないわたしは鑑賞眼の無いやつでしょうか。
後で知ったのですが、
「エグゼクティブプロデューサー:EXILE HIRO」という文字を見てのけぞりました。
岩田剛典さんという役者も彼の傘下なのですか。
それならこの作品のできばえも仕方ないのか、EXILE水準なのかと諦めました。
HIROさん、岩田さん、河瀬さん、、、カンヌのレッドカーペットを歩けなくて残念でした、と申しておきましょう。
『Vision ビジョン』
評価:☆☆☆・・・・・・・
年度:2018年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:河瀬直美
音楽:小曽根真
俳優:ジュリエット・ビノシュ 永瀬正敏 森山未來 夏木マリ 岩田剛典 田中泯 白川和子 ジジ・ぶぅ
製作国:日本、フランス
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
たいへん残念な映画でした。
作品になっていません。
わたしの家には河瀬直美さんの「空」の文字の書が飾られています。
退職祝いに友人が贈ってくださったのですが、
まるでパンダかアナグマの顔のような悠々としてどこかとぼけたその書はとても素敵です。
河瀬さんの映画もたとえば『あん』は傑作だと考えています。
ところが本作はどうしたことでしょう。
悠々とした、あるいは超然とした、河瀬さんのどこか俯瞰的な視点が消え、
あざとく、あるいは焦った印象がぬぐえません。
これだけの役者を揃えているのに、世界観が自立しているように見えるのは夏木マリさんだけで、後の方々はとても断片的な存在でした。(☆一つ分は夏木さんに捧げます)
ハーモニーがないのです。
どういう映画を作りたいのか、という意志が見えないのです。
聞けば、みなさん吉野の山で暮らしてから撮影したとか。
もしかして山に同化されて背景になってしまいましたか。
それとも、言い過ぎかもしれませんが、賞獲りを狙いすぎましたか。
「ビジョン」という事象・概念の用語は作中で日本語としても使われるのですが、これには違和感がありすぎました。
「びじょん」という語感の古来からの日本語はちょっと思い当たりません。
延々と吉野の杉の森の映像が映し出されます。
それはそれは美しい風景ですが、あくまで人工林です。
ところが、作中でパワースポット的に描かれる場所は杉林ではないのです。
わたしの目にも、いいところ見つけましたなあ、さすが河瀬さん、森山未來さんの呪術的な踊りにふさわしい、
と思うのですが、そこは谷あいの雑木林?スポット。
では吉野杉の人工美林は何のために長回しを?
海外へのアピールとしか思えないわたしは鑑賞眼の無いやつでしょうか。
後で知ったのですが、
「エグゼクティブプロデューサー:EXILE HIRO」という文字を見てのけぞりました。
岩田剛典さんという役者も彼の傘下なのですか。
それならこの作品のできばえも仕方ないのか、EXILE水準なのかと諦めました。
HIROさん、岩田さん、河瀬さん、、、カンヌのレッドカーペットを歩けなくて残念でした、と申しておきましょう。
2018年11月04日
『焼肉ドラゴン』
データ
『焼肉ドラゴン』
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:鄭義信
原作:鄭義信(戯曲)
俳優:キム・サンホ(父) イ・ジョンウン(母) 真木よう子(長女) 井上真央(次女)
桜庭ななみ(三女) 大泉洋(次女の夫) 大谷亮平
ハン・ドンギュ イム・ヒチョル 根岸季衣
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

写真は全て映画の公式HPから
コメント
和歌山市で映画『焼肉ドラゴン』を観てきました。
1970年前後の尼崎「朝鮮人部落」内のホルモン屋さんのお話。
生駒山と伊丹空港が借景になっています。
西宮市に住み、父が尼崎で働いていた私にはかなり懐かしい風景でした。
一家が(一帯が)立ちのきを迫られていること、
息子が中学校でイジメにあっていることを除くと、
済州島四・三事件や朝鮮併合、戦争のことなど大状況の難しい話は背景に収めていて、
映画の中心は家族の物語です。
苦しいことが続いても、明日はきっと良い日になるに違いないという父親のモットーが反映された、明るい映画だと言っておきましょう。
ただし長女が北朝鮮、次女が韓国へ移住する(帰国する)シーンで、
地上に影を落としながら爆音を立てて飛行機が上空を横切リます。
不安の暗喩ですよね、これは。
真木よう子さん、素晴らしい。井上真央さん、うまい。桜庭ななみさん、可愛いくもたくましい。
私はこのくらいの表現しかできないのですが、妻の三姉妹評はもう少し充実しています。
「長女は優しい設定だけど、真木よう子さんを起用するということは、韓国人には優しさと強さが求められるということかな。次女は巻き舌でポンポン言う。三女はぶっ飛んでる。三人ともあまり笑顔を見せない。」
そうですね、韓国人は日本人より笑顔が少ない気がします。それはイカツイからではなく、(日本人がよく見せる)追従笑いやトラブルを避けるための笑顔が韓国では少ないからではないでしょうか。私はそれを強さだと考えています。
あ、少し話題が逸れました。
以上の三姉妹をはじめ、大泉さん、大谷さんなど日本の役者陣も熱演していましたが、
何と言っても、三姉妹の両親役のハン・ドンギュさんとキム・サンポさんの年季の入った確かな芝居はもう感涙ものでした。
二人とも韓国の役者さんで在日の方ではないのですが、「在日」を完全に理解した上での演技のように感じました。
その演技を見るだけでも本作はおすすめできます。
ちょうど私はその三日前に鶴橋・桃谷あたりをうろついていたので本作のテーマはタイムリーでした。
その時買ってきた鶴橋の岡村商店さんのキムチとマッコリで、帰宅後は夫婦で映画に乾杯しました。
そうそう、もうすぐ『済州島四・三事件―「島(タムナ)のくに」の死と再生の物語』の中古本が届くはずなので、
これでもっと勉強せなあきまへんな。
良い映画でしたが、小さな不満を一つ書いておきます。
本作は「ドラゴン」という名の焼肉屋が舞台なのですが、
ホルモンなど韓国料理の質素でも美味しそうなアップの映像がほとんどありませんでした。
食べ物屋さんが舞台なのに惜しいではありませんか。
元が演劇でしたから、映画化に当たって考えが及ばなかったのでしょうか。
その代わり、やかんに入ったマッコリが「マッコリあるある」・・うまそうでした。
さらに批評を書きたいのですが、長くなりそうでまとまりません。
とりあえずコメントだけでアップしておくことにします。


『焼肉ドラゴン』
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:鄭義信
原作:鄭義信(戯曲)
俳優:キム・サンホ(父) イ・ジョンウン(母) 真木よう子(長女) 井上真央(次女)
桜庭ななみ(三女) 大泉洋(次女の夫) 大谷亮平
ハン・ドンギュ イム・ヒチョル 根岸季衣
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

写真は全て映画の公式HPから
コメント
和歌山市で映画『焼肉ドラゴン』を観てきました。
1970年前後の尼崎「朝鮮人部落」内のホルモン屋さんのお話。
生駒山と伊丹空港が借景になっています。
西宮市に住み、父が尼崎で働いていた私にはかなり懐かしい風景でした。
一家が(一帯が)立ちのきを迫られていること、
息子が中学校でイジメにあっていることを除くと、
済州島四・三事件や朝鮮併合、戦争のことなど大状況の難しい話は背景に収めていて、
映画の中心は家族の物語です。
苦しいことが続いても、明日はきっと良い日になるに違いないという父親のモットーが反映された、明るい映画だと言っておきましょう。
ただし長女が北朝鮮、次女が韓国へ移住する(帰国する)シーンで、
地上に影を落としながら爆音を立てて飛行機が上空を横切リます。
不安の暗喩ですよね、これは。
真木よう子さん、素晴らしい。井上真央さん、うまい。桜庭ななみさん、可愛いくもたくましい。
私はこのくらいの表現しかできないのですが、妻の三姉妹評はもう少し充実しています。
「長女は優しい設定だけど、真木よう子さんを起用するということは、韓国人には優しさと強さが求められるということかな。次女は巻き舌でポンポン言う。三女はぶっ飛んでる。三人ともあまり笑顔を見せない。」
そうですね、韓国人は日本人より笑顔が少ない気がします。それはイカツイからではなく、(日本人がよく見せる)追従笑いやトラブルを避けるための笑顔が韓国では少ないからではないでしょうか。私はそれを強さだと考えています。
あ、少し話題が逸れました。
以上の三姉妹をはじめ、大泉さん、大谷さんなど日本の役者陣も熱演していましたが、
何と言っても、三姉妹の両親役のハン・ドンギュさんとキム・サンポさんの年季の入った確かな芝居はもう感涙ものでした。
二人とも韓国の役者さんで在日の方ではないのですが、「在日」を完全に理解した上での演技のように感じました。
その演技を見るだけでも本作はおすすめできます。
ちょうど私はその三日前に鶴橋・桃谷あたりをうろついていたので本作のテーマはタイムリーでした。
その時買ってきた鶴橋の岡村商店さんのキムチとマッコリで、帰宅後は夫婦で映画に乾杯しました。
そうそう、もうすぐ『済州島四・三事件―「島(タムナ)のくに」の死と再生の物語』の中古本が届くはずなので、
これでもっと勉強せなあきまへんな。
良い映画でしたが、小さな不満を一つ書いておきます。
本作は「ドラゴン」という名の焼肉屋が舞台なのですが、
ホルモンなど韓国料理の質素でも美味しそうなアップの映像がほとんどありませんでした。
食べ物屋さんが舞台なのに惜しいではありませんか。
元が演劇でしたから、映画化に当たって考えが及ばなかったのでしょうか。
その代わり、やかんに入ったマッコリが「マッコリあるある」・・うまそうでした。
さらに批評を書きたいのですが、長くなりそうでまとまりません。
とりあえずコメントだけでアップしておくことにします。


2018年11月02日
『フルメタル・ジャケット』:戦争とは何か
データ
『フルメタル・ジャケット』FULL METAL JACKET
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・
年度:1987年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。ビデオ、DVDで多数回視聴。
監督:スタンリー・キューブリック
原作:グスタフ・ハスフォード
俳優:マシュー・モディーン(ジョーカー) アーリス・ハワード(カウボーイ)
ヴィンセント・ドノフリオ(パイル、Gomer Pyle) アダム・ボールドウィン(アニマル・マザー)
R・リー・アーメイ(ハートマン軍曹) ドリアン・ヘアウッド(エイトボール)
ケヴィン・メイジャー・ハワード(ラフターマン)
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

SUNSET BOULEVARD VIA GETTY IMAGES
コメント
戦争そのもの、戦争とは何かを生一本に描いた大傑作です。
高校で政治経済や倫理の授業の教材として使わせていただいたため、数十回観ていますが飽きません。
たいしたものです。(批評欄にもう少し詳しく書きます。)
それなのに私が本作に☆10を差し上げないただ一つの理由は、キューブリック監督の飛行機嫌いのせいです(笑)
アメリカからイギリスに移住した彼は、撮影場所を頑としてイギリスから動かさず、その結果しおれた輸入ヤシ(だけ)がしょぼしょぼ植えられた「ベトナム」を再現したからです。
ですから映像に東南アジアのあの暑く湿った空気感が皆無。
ほんまにもう、困ったわがまま監督やね。

これ以降の写真はすべてDVDより
本作に登場するアメリカ軍兵士たちは主に海兵隊員です。
海兵隊 (United States Marine Corps)とは「陸海空軍の全機能を備え、アメリカ軍が参加する主な戦いには最初に、上陸・空挺作戦などの任務で前線に投入され、その自己完結性と高い機動性から脚光を浴びている緊急展開部隊」です(wikipediaより)。
陸海空軍のいずれからも独立しています。
国内戦には投入されず、常に海外で活動するところから、別名を
<殴り込み部隊>と呼ばれます。
日本にも常駐しており、普天間基地がよく知られていますが、上記の性格上、沖縄を守る任務などありません。
第二次大戦後のアメリカは、世界でもっとも他国に兵を送り戦争を実行した国家です。
それらの行為は世界の安寧平和のため、すなわち「世界の警察」を大義名分としていますが、もちろんその原動力は世界一肥大した産軍複合体の要求です。戦争が起こらなければ儲からない軍需産業と、戦争が起こらなければ利権や栄達が実現できない国家・軍とは共通の利害関係があるからです。戦争が彼らの望みを叶えるために起こされています。
本作ではこのような戦争の原因について追求していませんが、ラストシーンで兵士たちがミッキーマウスマーチを歌いながら他国ベトナムを焼き払いその大地を行進していく姿こそ、産軍複合体の象徴と捉えるべきだと思います。
アメリカの戦争にはいつもミッキーが寄り添い、応援していますから。

民間人と「ベトコン」の区別なく射撃する兵士:彼のセリフは批評3に掲載
批評1:映画の前半と後半のギャップについて
同じ時期に製作された『プラトーン』は1987年度アカデミー作品賞・監督賞を受賞していますので、無冠のこの本作は同じベトナム戦争を題材にした映画として後塵を拝してしまいました。
(私は本作の方をより高く評価します)
キューブリック監督としては忸怩たる思いでしょうけれど、オリバー・ストーン監督の『プラトーン』からは東南アジアのジャングルの熱気がプンプン伝わってきましたよ、監督。
恋愛はもちろん美しい風景などの情緒が何もない戦争映画です。
それどころか、後半には観客を退屈させる時間帯まであります。
そのせいで、本作の前半と後半との落差を嘆くレビューアーには枚挙のいとまもありません。

「囮生殺し」シーン
もう少しだけ詳しく書きましょう。
時代はベトナム戦争の頃、1960年代〜70年代初頭です。
ベトナム戦争は、冷戦の時代に社会主義国の盟主ソ連に対する防波堤としてインドシナ半島に的を絞った資本主義国アメリカが、ベトナムに兵を送って始まった戦争です。
アメリカはその傀儡(かいらい)政権南ベトナム政府をコントロールし、南ベトナム内の社会主義・民族主義ゲリラ(アメリカはベトコンと呼びました)や北ベトナム(社会主義国)と戦いました。
この戦いは長期化し、次第に劣勢になったアメリカは、これまでより多くの兵士が必要になったわけです。
本作の前半は、その頃米軍海兵隊に志願して入隊した若者が、訓練所で受ける厳しい訓練を描いています。
訓練教官ハートマン軍曹(R・リー・アーメイさん)の下劣極まる悪口雑言と、彼によるいじめを伴う猛訓練、そして仲間によるリンチの結果壊れてしまったパイル(ヴィンセント・ドノフリオさん)の戦慄の行動はよく知られています。
この前半は、緊張感に圧倒されるような凝縮した雰囲気であっという間に過ぎていきます。
(訓練の「意義」については批評2で書きます。)

ジョーカー(左)の二律背反
転じて後半はとてもゆるやかに進行します。
訓練所を巣立った新兵たちは戦場の各地に散らばるのですが、主役格のジョーカー(マシュー・モディーンさん)は現地の報道部に配属されたので、まだ戦闘は未体験です。
報道部の日常はのんびりとして危険が少なく、ジョーカーは責任者に口ごたえができる余裕があるほどです。
前半の緊張感に比べ、弛緩したような空気が流れていますが、まさにジョーカーはそういう環境の中で軍務を行っているわけです。
この弛緩も戦争の側面だとキューブリック監督は言うのです。
ジョーカーは、戦場に行かない安堵と同時にいつまでも戦闘を体験できないじれったい焦燥にもかられているというわけです。
この二律背反、矛盾も戦場の側面だとキューブリック監督は言うのです。
つまり、まさしく監督は戦争そのものをストレートに描いていると言えます。
ドラマ仕立てに作っていないところがいかにもキューブリックさんの面目躍如じゃないですか。
そう言う視点から、私は本作の後半も高く評価しているのです。
さらに後半のさらに後半では衝撃的な戦闘が行われます。
ヴェトナム民族解放戦線(ベトコン)側の狙撃兵による囮生殺し戦術はその一つです。
さらに強烈なのはその続きの場面です。前半のパイルの自死と同じくらいの。
ただ、日本人にはその衝撃がうまく伝わらないきらいがありました。
私はその原因の一つを、日本人が歴史や国際社会に無関心になってしまったせいだと考えています。
そしてさらに、欧米人とアジア人の死生観の相違のようなものに影響された結果だと。
しかし本稿では原因について深入りはしません。
なお、この衝撃のシーンの映画的意義については批評3で書きます。

懲罰=イジメ
批評2:海兵隊の訓練学校の訓練
シリアやソマリアのように、不幸にも身近な場所でいま現に戦闘が行われている地域・国家を除いて議論します。
強制的な徴兵であれ(海兵隊のような)志願兵であれ、兵士になる前は「ふつうの人」でした。
人殺しの経験はもちろんありません。それどころか気の合わない隣人や同級生とも「ふつうの付き合い」をしていた人がほとんどだったはずです。
「ふつうの人」は、盗んだり破壊したり殺したりすることは良くないことだと信じて生きています。
また同時に「ふつうの人」は、気に入らない指示や納得のいかない命令に対して疑問を感じます。勇気があればNO!も言えるでしょう。
(民主主義化が進んだ国ほどそういう傾向があります)
ところが、軍隊の意義、兵士の役割はこれら「ふつうの人」の価値観とは全く異なります。
軍隊は人類史上そもそも殺人と破壊のために存在していましたし、その本質は現代においてもなんらかわりがありません。
マックス・ヴェーバー(ウェーバー)の定義によれば暴力装置ということになります。
抑止力だろうと反論したい方には、殺戮や破壊する能力のない軍隊など抑止力にならないだろう、と申し上げればすみます。
軍隊の意義が暴力にある以上、兵士は暴力をふるえる機能を持たねばなりません。
必要な場合はためらいなく人を殺し、敵の施設を破壊しなければなりません。
しかし下級兵士個々は判断力を期待されていませんし、そういう訓練を受けていません。
ですから、兵士は必ず上官の命令に反射的に応えなければなりません。
つまり、「ふつうの人」がふつうのままでいては兵士になれないのです。
ここに、本作のような新兵の訓練所における訓練の必要が生まれるわけです。
1)これまでの価値観・常識を捨てる。(人格の地軸を逆転させる。)
2)命令には絶対服従する、(その習慣を体に叩き込ませる。)
その両方の要素を備えた人間に生まれ変わらなければならないわけです。
ハートマン軍曹による悪罵を含んだ非人間的訓練の目的はここにあります。
したがって、程度の違いや方法の違いはあったにせよ、全ての現代国家の軍隊(自衛隊を含む)の訓練は同じように行われていますし、そうでなくてはならないという論理的帰結になります。
キューブリック監督はその真理を映像化しているのです。
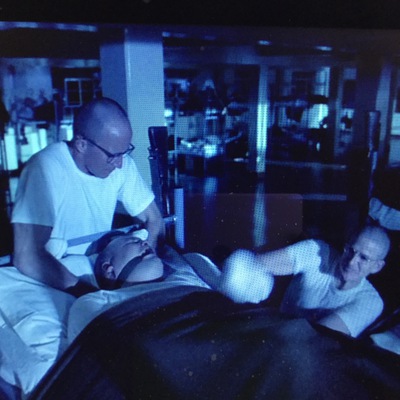
生徒間のリンチ:タオルに包んだ石鹸による殴打は傷が残りにくく、大日本帝国軍でも横行しました
批評3:ただの兵士となったジョーカー
さて、主役を張るジョーカーは、ここまではやや狂言回し的な役割。
しかし終盤に、戦争そのものを体現する存在になります。
上述のように、ジョーカーは矛盾した青年。ハートマン教官に褒められるほどガッツはあるのですが、知性が邪魔をしているのかどこか中途半端。
ヘルメットには殺し屋と書きながら、胸にはピースマークのピンバッジ。
輸送ヘリの射撃手(ティム・コルセリさん)が「(女子供を殺すのは)簡単さ、動きがのろいからな」、「ホント、戦争は地獄だぜ!」、「逃げる奴は皆ベトコンだ、逃げない奴はよく訓練されたベトコンだ」などと笑いながら民間人を射撃することにも納得していないはず。
スナイパーと直接対面した時も、戦闘経験のなさが露呈して銃が起動しない失策。
相棒のカメラマン兵ラフターマンに命を救われる始末です。
しかし床に倒れ瀕死のベトナム人スナイパーが「shoot me」(私を射って)と懇願するのに負けて射殺することで、それまで中途半端だったジョーカーがいっぱしの悪虐非道の兵士に変身します。
これぞ海兵隊魂。
殺すために生まれた男。
ラストで皆と一緒に満足そうに「ミッキーマウス・マーチ」を歌いながら行進することでそのことは表現されるのです。
ここで詳しく書くことは煩雑なのでしませんが、まったく馬鹿馬鹿しい人類の矛盾ですが、戦争にも国際ルールがあるのです。
(誤解しないでください。私は戦争それ自体が最大のルール違反だと考えています。)
例えば民間人を殺害してはならない、無抵抗な捕虜は保護されねばならないのです。
上記のヘリの射撃手はこのルールを破った殺人鬼ですし、ジョーカーもルール違反の殺人者なのです。
大日本帝国による重慶の無差別爆撃、南京虐殺、バターン死の行進などはもちろんルール違反。
同様にアメリカによる東京大空襲や原爆投下もルール違反です。
ただし勝者は普通裁く側にまわりますから、アメリカの罪は不問に付されました。

スナイパーは壁の穴から敵を狙撃する:ここでジョーカーの旧友カウボーイが戦死
終盤最大の衝撃シーンは、ジョーカーの変身の直前。
凄腕の狙撃でジョーカーたちを足止めし、囮生殺しで全滅させようとした狙撃手はたった一人だったこと。
しかもそれがおさげの少女だったこと。
(ジョーカーはその少女を殺害したのです。)
ジョーカーたち海兵隊員は、あの過酷な訓練を受けてようやく戦場に出ました。
しかしこの少女はヴェトナム民族解放戦線の一員。
もちろん射撃訓練はしたでしょうが、アメリカ海兵隊のような組織的な学校があるはずがないゲリラです。
彼女たちは「ふつうの人」ではないのです。
なぜなら、彼女たちの住む大地は、外国(フランス→日本→フランス→アメリカ)に蹂躙され続けていたからです。
極端に言えば、生まれながらに銃を持っていた人々なのです。
しかも、侵略国家を憎んで戦う意志も生まれながらに持っていたはず。
戦争の意義がよくわからないままベトナムにやってきた海兵隊員とはまるで次元の違う戦いを戦っているのです。
誠に不幸。
そして、かなうはずがありません。
このシーンで、大国が小国を侵略する戦争というものに、一瞬にして目を向けさせるのです。
キューブリック監督、さすがです。
彼を舐めるわけにはいきません。
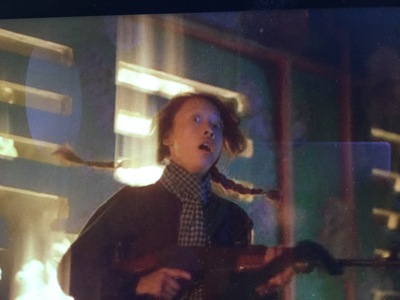
スナイパーはたった一人の少女だった
『フルメタル・ジャケット』FULL METAL JACKET
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・
年度:1987年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。ビデオ、DVDで多数回視聴。
監督:スタンリー・キューブリック
原作:グスタフ・ハスフォード
俳優:マシュー・モディーン(ジョーカー) アーリス・ハワード(カウボーイ)
ヴィンセント・ドノフリオ(パイル、Gomer Pyle) アダム・ボールドウィン(アニマル・マザー)
R・リー・アーメイ(ハートマン軍曹) ドリアン・ヘアウッド(エイトボール)
ケヴィン・メイジャー・ハワード(ラフターマン)
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

SUNSET BOULEVARD VIA GETTY IMAGES
コメント
戦争そのもの、戦争とは何かを生一本に描いた大傑作です。
高校で政治経済や倫理の授業の教材として使わせていただいたため、数十回観ていますが飽きません。
たいしたものです。(批評欄にもう少し詳しく書きます。)
それなのに私が本作に☆10を差し上げないただ一つの理由は、キューブリック監督の飛行機嫌いのせいです(笑)
アメリカからイギリスに移住した彼は、撮影場所を頑としてイギリスから動かさず、その結果しおれた輸入ヤシ(だけ)がしょぼしょぼ植えられた「ベトナム」を再現したからです。
ですから映像に東南アジアのあの暑く湿った空気感が皆無。
ほんまにもう、困ったわがまま監督やね。

これ以降の写真はすべてDVDより
本作に登場するアメリカ軍兵士たちは主に海兵隊員です。
海兵隊 (United States Marine Corps)とは「陸海空軍の全機能を備え、アメリカ軍が参加する主な戦いには最初に、上陸・空挺作戦などの任務で前線に投入され、その自己完結性と高い機動性から脚光を浴びている緊急展開部隊」です(wikipediaより)。
陸海空軍のいずれからも独立しています。
国内戦には投入されず、常に海外で活動するところから、別名を
<殴り込み部隊>と呼ばれます。
日本にも常駐しており、普天間基地がよく知られていますが、上記の性格上、沖縄を守る任務などありません。
第二次大戦後のアメリカは、世界でもっとも他国に兵を送り戦争を実行した国家です。
それらの行為は世界の安寧平和のため、すなわち「世界の警察」を大義名分としていますが、もちろんその原動力は世界一肥大した産軍複合体の要求です。戦争が起こらなければ儲からない軍需産業と、戦争が起こらなければ利権や栄達が実現できない国家・軍とは共通の利害関係があるからです。戦争が彼らの望みを叶えるために起こされています。
本作ではこのような戦争の原因について追求していませんが、ラストシーンで兵士たちがミッキーマウスマーチを歌いながら他国ベトナムを焼き払いその大地を行進していく姿こそ、産軍複合体の象徴と捉えるべきだと思います。
アメリカの戦争にはいつもミッキーが寄り添い、応援していますから。

民間人と「ベトコン」の区別なく射撃する兵士:彼のセリフは批評3に掲載
批評1:映画の前半と後半のギャップについて
同じ時期に製作された『プラトーン』は1987年度アカデミー作品賞・監督賞を受賞していますので、無冠のこの本作は同じベトナム戦争を題材にした映画として後塵を拝してしまいました。
(私は本作の方をより高く評価します)
キューブリック監督としては忸怩たる思いでしょうけれど、オリバー・ストーン監督の『プラトーン』からは東南アジアのジャングルの熱気がプンプン伝わってきましたよ、監督。
恋愛はもちろん美しい風景などの情緒が何もない戦争映画です。
それどころか、後半には観客を退屈させる時間帯まであります。
そのせいで、本作の前半と後半との落差を嘆くレビューアーには枚挙のいとまもありません。

「囮生殺し」シーン
もう少しだけ詳しく書きましょう。
時代はベトナム戦争の頃、1960年代〜70年代初頭です。
ベトナム戦争は、冷戦の時代に社会主義国の盟主ソ連に対する防波堤としてインドシナ半島に的を絞った資本主義国アメリカが、ベトナムに兵を送って始まった戦争です。
アメリカはその傀儡(かいらい)政権南ベトナム政府をコントロールし、南ベトナム内の社会主義・民族主義ゲリラ(アメリカはベトコンと呼びました)や北ベトナム(社会主義国)と戦いました。
この戦いは長期化し、次第に劣勢になったアメリカは、これまでより多くの兵士が必要になったわけです。
本作の前半は、その頃米軍海兵隊に志願して入隊した若者が、訓練所で受ける厳しい訓練を描いています。
訓練教官ハートマン軍曹(R・リー・アーメイさん)の下劣極まる悪口雑言と、彼によるいじめを伴う猛訓練、そして仲間によるリンチの結果壊れてしまったパイル(ヴィンセント・ドノフリオさん)の戦慄の行動はよく知られています。
この前半は、緊張感に圧倒されるような凝縮した雰囲気であっという間に過ぎていきます。
(訓練の「意義」については批評2で書きます。)

ジョーカー(左)の二律背反
転じて後半はとてもゆるやかに進行します。
訓練所を巣立った新兵たちは戦場の各地に散らばるのですが、主役格のジョーカー(マシュー・モディーンさん)は現地の報道部に配属されたので、まだ戦闘は未体験です。
報道部の日常はのんびりとして危険が少なく、ジョーカーは責任者に口ごたえができる余裕があるほどです。
前半の緊張感に比べ、弛緩したような空気が流れていますが、まさにジョーカーはそういう環境の中で軍務を行っているわけです。
この弛緩も戦争の側面だとキューブリック監督は言うのです。
ジョーカーは、戦場に行かない安堵と同時にいつまでも戦闘を体験できないじれったい焦燥にもかられているというわけです。
この二律背反、矛盾も戦場の側面だとキューブリック監督は言うのです。
つまり、まさしく監督は戦争そのものをストレートに描いていると言えます。
ドラマ仕立てに作っていないところがいかにもキューブリックさんの面目躍如じゃないですか。
そう言う視点から、私は本作の後半も高く評価しているのです。
さらに後半のさらに後半では衝撃的な戦闘が行われます。
ヴェトナム民族解放戦線(ベトコン)側の狙撃兵による囮生殺し戦術はその一つです。
さらに強烈なのはその続きの場面です。前半のパイルの自死と同じくらいの。
ただ、日本人にはその衝撃がうまく伝わらないきらいがありました。
私はその原因の一つを、日本人が歴史や国際社会に無関心になってしまったせいだと考えています。
そしてさらに、欧米人とアジア人の死生観の相違のようなものに影響された結果だと。
しかし本稿では原因について深入りはしません。
なお、この衝撃のシーンの映画的意義については批評3で書きます。

懲罰=イジメ
批評2:海兵隊の訓練学校の訓練
シリアやソマリアのように、不幸にも身近な場所でいま現に戦闘が行われている地域・国家を除いて議論します。
強制的な徴兵であれ(海兵隊のような)志願兵であれ、兵士になる前は「ふつうの人」でした。
人殺しの経験はもちろんありません。それどころか気の合わない隣人や同級生とも「ふつうの付き合い」をしていた人がほとんどだったはずです。
「ふつうの人」は、盗んだり破壊したり殺したりすることは良くないことだと信じて生きています。
また同時に「ふつうの人」は、気に入らない指示や納得のいかない命令に対して疑問を感じます。勇気があればNO!も言えるでしょう。
(民主主義化が進んだ国ほどそういう傾向があります)
ところが、軍隊の意義、兵士の役割はこれら「ふつうの人」の価値観とは全く異なります。
軍隊は人類史上そもそも殺人と破壊のために存在していましたし、その本質は現代においてもなんらかわりがありません。
マックス・ヴェーバー(ウェーバー)の定義によれば暴力装置ということになります。
抑止力だろうと反論したい方には、殺戮や破壊する能力のない軍隊など抑止力にならないだろう、と申し上げればすみます。
軍隊の意義が暴力にある以上、兵士は暴力をふるえる機能を持たねばなりません。
必要な場合はためらいなく人を殺し、敵の施設を破壊しなければなりません。
しかし下級兵士個々は判断力を期待されていませんし、そういう訓練を受けていません。
ですから、兵士は必ず上官の命令に反射的に応えなければなりません。
つまり、「ふつうの人」がふつうのままでいては兵士になれないのです。
ここに、本作のような新兵の訓練所における訓練の必要が生まれるわけです。
1)これまでの価値観・常識を捨てる。(人格の地軸を逆転させる。)
2)命令には絶対服従する、(その習慣を体に叩き込ませる。)
その両方の要素を備えた人間に生まれ変わらなければならないわけです。
ハートマン軍曹による悪罵を含んだ非人間的訓練の目的はここにあります。
したがって、程度の違いや方法の違いはあったにせよ、全ての現代国家の軍隊(自衛隊を含む)の訓練は同じように行われていますし、そうでなくてはならないという論理的帰結になります。
キューブリック監督はその真理を映像化しているのです。
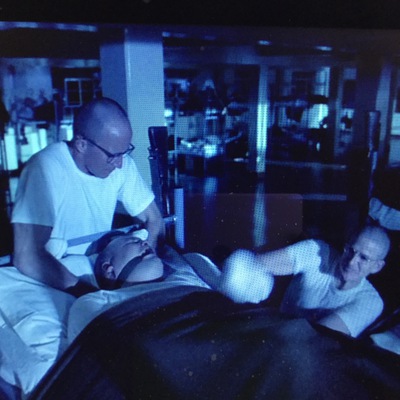
生徒間のリンチ:タオルに包んだ石鹸による殴打は傷が残りにくく、大日本帝国軍でも横行しました
批評3:ただの兵士となったジョーカー
さて、主役を張るジョーカーは、ここまではやや狂言回し的な役割。
しかし終盤に、戦争そのものを体現する存在になります。
上述のように、ジョーカーは矛盾した青年。ハートマン教官に褒められるほどガッツはあるのですが、知性が邪魔をしているのかどこか中途半端。
ヘルメットには殺し屋と書きながら、胸にはピースマークのピンバッジ。
輸送ヘリの射撃手(ティム・コルセリさん)が「(女子供を殺すのは)簡単さ、動きがのろいからな」、「ホント、戦争は地獄だぜ!」、「逃げる奴は皆ベトコンだ、逃げない奴はよく訓練されたベトコンだ」などと笑いながら民間人を射撃することにも納得していないはず。
スナイパーと直接対面した時も、戦闘経験のなさが露呈して銃が起動しない失策。
相棒のカメラマン兵ラフターマンに命を救われる始末です。
しかし床に倒れ瀕死のベトナム人スナイパーが「shoot me」(私を射って)と懇願するのに負けて射殺することで、それまで中途半端だったジョーカーがいっぱしの悪虐非道の兵士に変身します。
これぞ海兵隊魂。
殺すために生まれた男。
ラストで皆と一緒に満足そうに「ミッキーマウス・マーチ」を歌いながら行進することでそのことは表現されるのです。
ここで詳しく書くことは煩雑なのでしませんが、まったく馬鹿馬鹿しい人類の矛盾ですが、戦争にも国際ルールがあるのです。
(誤解しないでください。私は戦争それ自体が最大のルール違反だと考えています。)
例えば民間人を殺害してはならない、無抵抗な捕虜は保護されねばならないのです。
上記のヘリの射撃手はこのルールを破った殺人鬼ですし、ジョーカーもルール違反の殺人者なのです。
大日本帝国による重慶の無差別爆撃、南京虐殺、バターン死の行進などはもちろんルール違反。
同様にアメリカによる東京大空襲や原爆投下もルール違反です。
ただし勝者は普通裁く側にまわりますから、アメリカの罪は不問に付されました。

スナイパーは壁の穴から敵を狙撃する:ここでジョーカーの旧友カウボーイが戦死
終盤最大の衝撃シーンは、ジョーカーの変身の直前。
凄腕の狙撃でジョーカーたちを足止めし、囮生殺しで全滅させようとした狙撃手はたった一人だったこと。
しかもそれがおさげの少女だったこと。
(ジョーカーはその少女を殺害したのです。)
ジョーカーたち海兵隊員は、あの過酷な訓練を受けてようやく戦場に出ました。
しかしこの少女はヴェトナム民族解放戦線の一員。
もちろん射撃訓練はしたでしょうが、アメリカ海兵隊のような組織的な学校があるはずがないゲリラです。
彼女たちは「ふつうの人」ではないのです。
なぜなら、彼女たちの住む大地は、外国(フランス→日本→フランス→アメリカ)に蹂躙され続けていたからです。
極端に言えば、生まれながらに銃を持っていた人々なのです。
しかも、侵略国家を憎んで戦う意志も生まれながらに持っていたはず。
戦争の意義がよくわからないままベトナムにやってきた海兵隊員とはまるで次元の違う戦いを戦っているのです。
誠に不幸。
そして、かなうはずがありません。
このシーンで、大国が小国を侵略する戦争というものに、一瞬にして目を向けさせるのです。
キューブリック監督、さすがです。
彼を舐めるわけにはいきません。
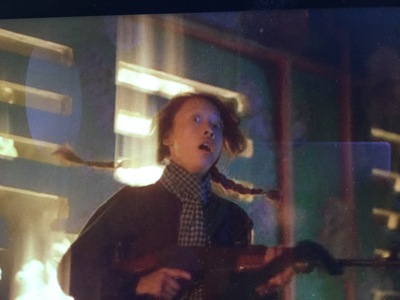
スナイパーはたった一人の少女だった
タグ :スタンリー・キューブリックマシュー・モディーンアーリス・ハワードヴィンセント・ドノフリオアダム・ボールドウィンR・リー・アーメイケヴィン・メイジャー・ハワードドリアン・ヘアウッドアメリカ映画☆9
2018年10月30日
『ドリームキャッチャー』
データ
『ドリームキャッチャー』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2003年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:ローレンス・カスダン
原作:スティーヴン・キング
音楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード
俳優:トーマス・ジェーン トム・サイズモア ジェイソン・リー ダミアン・ルイス
ティモシー・オリファント ドニー・ウォールバーグ モーガン・フリーマン
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

WarnerBros./Photofest/ゲッティイメージズ
コメント
スティーヴン・キング原作の映画がけっこう好きな私のために、知らぬ間に妻が録画してくれていました。
短い紹介文を読むと、キングが激賞していたと。
キングが褒めた映画に当たりはなかったので、期待せずに身始めると、意外にも135分があっという間でした。
(実際はヒマヒマに三度に分割して見ましたが)
おもしろいエイリアン+ホラー+グロテスクB級映画です。
アメリカの少年たちのみずみずしい仲間意識や性への憧れ、いじめ、鉄道軌道、、、の映像が流れると、あ〜またかと思ったのは事実です。『スタンドバイミー』や『IT』と同じ。少年ものなら『トリュフォーの思春期』に勝る映画はないぞ、などと思っていたら、その後の展開は意外性の連続技。闇鍋状態。好きです、こういうわけわからん展開の映画も。
カギになるのは少年4人がイジメから救った病弱な知的障害児ダディッツ。
彼と仲良くなったために、4人はちょっとした超能力を授かります。
予知能力、テレパシー通信、等々。
これを駆使して悪と戦うのか、と思いきや、倒すほどの画期的なパワーはないのが肩透かしでかえって面白い。
モーガン・フリーマンさんが狂気を帯びた「悪役」で登場しています。
私にとっては善い人役を演じる印象が強いので、最後まで彼の悪意を信じなかったところがありました。
そこがかえって面白かったように思います。
ラストバトルについては賛否両論のようですが、
意外な設定に少し驚かされた私は、これはアリだと思いました。
これ以上詳しい説明は蛇足だと思います。
けったいな映画が好きな方には、おヒマな時にぜひ、とオススメしておきます。
なお、原題のドリームキャッチャーはご存知アメリカ大陸先住民の呪術道具ですが、
本作品中のそれは埃か蜘蛛の巣かで薄汚れたまま、見た目には活躍しませんでした。
『ドリームキャッチャー』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2003年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:ローレンス・カスダン
原作:スティーヴン・キング
音楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード
俳優:トーマス・ジェーン トム・サイズモア ジェイソン・リー ダミアン・ルイス
ティモシー・オリファント ドニー・ウォールバーグ モーガン・フリーマン
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

WarnerBros./Photofest/ゲッティイメージズ
コメント
スティーヴン・キング原作の映画がけっこう好きな私のために、知らぬ間に妻が録画してくれていました。
短い紹介文を読むと、キングが激賞していたと。
キングが褒めた映画に当たりはなかったので、期待せずに身始めると、意外にも135分があっという間でした。
(実際はヒマヒマに三度に分割して見ましたが)
おもしろいエイリアン+ホラー+グロテスクB級映画です。
アメリカの少年たちのみずみずしい仲間意識や性への憧れ、いじめ、鉄道軌道、、、の映像が流れると、あ〜またかと思ったのは事実です。『スタンドバイミー』や『IT』と同じ。少年ものなら『トリュフォーの思春期』に勝る映画はないぞ、などと思っていたら、その後の展開は意外性の連続技。闇鍋状態。好きです、こういうわけわからん展開の映画も。
カギになるのは少年4人がイジメから救った病弱な知的障害児ダディッツ。
彼と仲良くなったために、4人はちょっとした超能力を授かります。
予知能力、テレパシー通信、等々。
これを駆使して悪と戦うのか、と思いきや、倒すほどの画期的なパワーはないのが肩透かしでかえって面白い。
モーガン・フリーマンさんが狂気を帯びた「悪役」で登場しています。
私にとっては善い人役を演じる印象が強いので、最後まで彼の悪意を信じなかったところがありました。
そこがかえって面白かったように思います。
ラストバトルについては賛否両論のようですが、
意外な設定に少し驚かされた私は、これはアリだと思いました。
これ以上詳しい説明は蛇足だと思います。
けったいな映画が好きな方には、おヒマな時にぜひ、とオススメしておきます。
なお、原題のドリームキャッチャーはご存知アメリカ大陸先住民の呪術道具ですが、
本作品中のそれは埃か蜘蛛の巣かで薄汚れたまま、見た目には活躍しませんでした。
2018年10月30日
『リバーズ・エッジ』:生きている実感があるか
データ
『リバーズ・エッジ』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・
年度:2018年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:行定勲
原作:岡崎京子『リバーズ・エッジ』(宝島社刊)
音楽:世武裕子
主題歌:小沢健二『アルペジオ(きっと魔法のトンネルの先)』
俳優:二階堂ふみ(若草ハルナ)吉沢亮(山田一郎)上杉柊平(観音崎)
SUMIRE(吉川こずえ) 土居志央梨(小山ルミ) 森川葵(田島カンナ)
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

写真はすべてパンフレットより
コメント
2018年に公開された映画で私が鑑賞した中では、ベストな作品になりました。
同じ年の公開の『万引き家族』は俳優の演技面でパーフェクトな秀作でしたが、本作の方が私の中に食い込んだように感じます。
私は、本作に描かれた荒野のような十代を送ったわけではないのに、なぜこれほどシンクロしてしまうのかずいぶん考え込んでしまいました。
至った結論はシンプルです。
時代が異なるだけで、私を取り巻く荒野があり、私の内部にも荒野があったのです。
これは普遍的な漫画を原作にした普遍的な映画なのでした。
それを気づかせてくれたのは、誰よりもハルナ(二階堂ふみさん)の空洞(しかし温かい)のような、自分が何者かを知らない目の再現のおかげです。
生きているのだという実感が持てない。
その実感をどうやって手に入れるか、
模索する若者の物語。
本作の紹介は、妻の文章を借ります。
『リバーズ・エッジ』、私が映画業界の人だったら何らかの形でこの現場に関わりたかったなー、と思うような、スタッフとキャストの熱量を感じる作品だった。
原作は90年代にリアルタイムで読んで、ヒリヒリしすぎて手放して、でも10年ぐらい前にまた買ってしまったという、なんか深いところまで刺さった作品。
公開前にネットでこの二階堂ふみを見て、「あっ、ハルナ(主人公)だ!」って思った。二階堂さんは16歳で原作を読んで、「すごく傷ついたような気持ちになった」という。その感性を信じて観に行った。
結果、二階堂さんはすごくハルナだったし、そこまで期待していなかった山田役の吉沢亮くんもすごく山田だった。二人を取り巻く森川葵、土居志央梨、SUMIRE、上杉柊平といった若い役者さん達も魂のこもった演技で、キーワードの「平坦な戦場」を団体戦で表現していた。
閉塞感とか孤独とか焦燥とか、生に対する実感のなさとか。そういう言葉が浮かんでくるような、明るくない群像劇が好きな人にはおすすめかもしれません。

批評
原作で印象深かった文章が、本作でも冒頭のナレーションとして使われていました。
わたしたちの住んでいる街には
川が流れていて、
それは河口にほど近く広くゆっくり淀み、臭い。
河原にはセイタカアワダチソウがおいしげっていて、
よくネコの死骸が転がっていたりする。
どうぞ声に出して三回ほど読んでみてください。
わたしたちは今もこういう街に、住んでいるはずです。
いえ、川の有無や都会・過疎地の別など具体的な地理環境を申し上げているのではありません。
高校生でなくても同じです。
そうだな、こういう街に住んでいるんだよなわたしの心は。
と共感していただいた方にはこの映像作品がねじ込まれていくはずです。
それ以上書く言葉が見つかりません。

『リバーズ・エッジ』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・
年度:2018年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:行定勲
原作:岡崎京子『リバーズ・エッジ』(宝島社刊)
音楽:世武裕子
主題歌:小沢健二『アルペジオ(きっと魔法のトンネルの先)』
俳優:二階堂ふみ(若草ハルナ)吉沢亮(山田一郎)上杉柊平(観音崎)
SUMIRE(吉川こずえ) 土居志央梨(小山ルミ) 森川葵(田島カンナ)
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

写真はすべてパンフレットより
コメント
2018年に公開された映画で私が鑑賞した中では、ベストな作品になりました。
同じ年の公開の『万引き家族』は俳優の演技面でパーフェクトな秀作でしたが、本作の方が私の中に食い込んだように感じます。
私は、本作に描かれた荒野のような十代を送ったわけではないのに、なぜこれほどシンクロしてしまうのかずいぶん考え込んでしまいました。
至った結論はシンプルです。
時代が異なるだけで、私を取り巻く荒野があり、私の内部にも荒野があったのです。
これは普遍的な漫画を原作にした普遍的な映画なのでした。
それを気づかせてくれたのは、誰よりもハルナ(二階堂ふみさん)の空洞(しかし温かい)のような、自分が何者かを知らない目の再現のおかげです。
生きているのだという実感が持てない。
その実感をどうやって手に入れるか、
模索する若者の物語。
本作の紹介は、妻の文章を借ります。
『リバーズ・エッジ』、私が映画業界の人だったら何らかの形でこの現場に関わりたかったなー、と思うような、スタッフとキャストの熱量を感じる作品だった。
原作は90年代にリアルタイムで読んで、ヒリヒリしすぎて手放して、でも10年ぐらい前にまた買ってしまったという、なんか深いところまで刺さった作品。
公開前にネットでこの二階堂ふみを見て、「あっ、ハルナ(主人公)だ!」って思った。二階堂さんは16歳で原作を読んで、「すごく傷ついたような気持ちになった」という。その感性を信じて観に行った。
結果、二階堂さんはすごくハルナだったし、そこまで期待していなかった山田役の吉沢亮くんもすごく山田だった。二人を取り巻く森川葵、土居志央梨、SUMIRE、上杉柊平といった若い役者さん達も魂のこもった演技で、キーワードの「平坦な戦場」を団体戦で表現していた。
閉塞感とか孤独とか焦燥とか、生に対する実感のなさとか。そういう言葉が浮かんでくるような、明るくない群像劇が好きな人にはおすすめかもしれません。

批評
原作で印象深かった文章が、本作でも冒頭のナレーションとして使われていました。
わたしたちの住んでいる街には
川が流れていて、
それは河口にほど近く広くゆっくり淀み、臭い。
河原にはセイタカアワダチソウがおいしげっていて、
よくネコの死骸が転がっていたりする。
どうぞ声に出して三回ほど読んでみてください。
わたしたちは今もこういう街に、住んでいるはずです。
いえ、川の有無や都会・過疎地の別など具体的な地理環境を申し上げているのではありません。
高校生でなくても同じです。
そうだな、こういう街に住んでいるんだよなわたしの心は。
と共感していただいた方にはこの映像作品がねじ込まれていくはずです。
それ以上書く言葉が見つかりません。

2018年10月28日
『三度目の殺人』
データ
『三度目の殺人』
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:是枝裕和
俳優:福山雅治(重盛朋章弁護士) 蒔田彩珠(重盛結花=朋章の娘) 役所広司(三隅高司)
広瀬すず(山中咲江) 斉藤由貴(山中美津江=咲江の母) 市川実日子(篠原一葵検事)
満島真之介 吉田鋼太郎 橋爪功 松岡依都美 品川徹 根岸季衣 高橋努 小倉一郎
中村まこと 井上肇
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

予告より
批評
映像作家是枝監督の実力は十分に認めています。
原作のある『海街diary』でも、そうでない『万引き家族』でも、その才能は遺憾無く発揮され、傑作を生み出しました。
しかし、すべての作品がそのレベルで仕上がるとは限りません。
『そして父になる』や本作ではそのエンジンにトルクがかからずタイヤが空転したと私は感じました。
昨年本作が公開されたとき、私は映画館に行く気が起きませんでしたが、今回『万引き家族』のカンヌ受賞を機に本作がBS/CSで放送されると知り、それならば見ておきたいと思いました。
その結果、直観が正しかったことが証明されてしまいました。
問題意識に溢れた意欲作ですから、そっとしておきたい気持ちもありますが、見てしまった以上、簡潔に批判したいと考えます。
一言で言うと、盛り過ぎ、欲張りすぎです。
『ニーチェの馬』は154分を費やして、荒野に住む父娘と馬を通じて世界の終末を描きました。
『アラビアのロレンス』は207分かけて、繊細な理想主義者の青年を通じて白人国家の傲慢を描きました。
『道』は115分を費やして、神と人の愛を知らない無知な男の悲劇を描きました。
では『三度目の殺人』は、125分かけて何を描いたのでしょう。私には的がたくさん見えました。誤解でしょうか。
中で是枝監督がもっとも描きたかったことは裁判批判だと私はみました。
「裁判は真実の追求ではなく、利害の調整になっている」という劇中のセリフが本作の核心でしょう。
その裁判の惨状を体現しているのが重盛弁護士で、福山雅治さんが好演しています。
クールに選挙戦術だけを考える重盛弁護士に立ちはだかったのは、依頼人三隅高司。罪状は殺人罪。役者は役所広司さんです。
三隅高司は供述・説明を簡単に変えていく人物。彼の何が本当で何が嘘なのかわからず、弁護士は振り回されます。
選挙戦術(たとえば死刑が相当だろうという裁判で無期懲役を勝ち取りたいなどの)が成功すれば良いとする重盛にとって、勝つためには三隅の供述が変わっては困るのですが、そうはいかない。
そこで重盛は三隅の供述の信憑性を調査せざるを得なくなりますが、それは重盛が必要ないと考えていた「真実の追求」作業に他なりません。
裁判の本来の目的が「真実の追求」という正義であるならば、皮肉なことに、そこからもっとも遠かった重盛が「正義派」として仕事せざるを得なくなリます。
殺人容疑者三隅高司は、本質的にいえば、現状の堕落した裁判を矯正する役割を果たすわけです。
三隅の一度目の殺人事件を捜査した刑事は、三隅を「空っぽの器のような男」と評します。
空っぽの器は簡単に他者の難儀を自分のものとして殺人を代行することもあるかもしれませんが、
空っぽの器は、同時に、その不可知性無限性の虚無の中に他人を取り込んでしまうのかもしれません。
三隅の弁護士としての面会を重ねるうちに、重盛はしだいにその三隅の「罠」にはまっていきます。
映像がそのことをわかりやすく表現しています。
最後には二人の顔が重なるように映し出されるのですから。
(是枝監督の作品は映像による説明が多過ぎると感じることがありますが、ここは映像による必要な説明だったと思います。これだけならば、ですが。)
ここまで私の文におつきあい下さった方は、その設定の重さに気が付かれたと思います。
謎に満ちた虚無のような男と真実の追求に関心がなかった弁護士〜〜その二人の対決と同化という道筋だけでもういっぱいいっぱいだと思いませんか。
それを描くだけで125分のうち大部分を使えば良かったのだと私は考えます。
さぞや裁判の堕落した現状を監督の鋭い刃が切り裂いたことでしょう。

予告より
ところが是枝監督は欲張るのです。
吉田鋼太郎さんと満島真之介さんがそれぞれ弁護士を演じています。吉田さんは検事から弁護士に転身したいわゆるヤメ弁。意欲に乏しい。満島さんの役どころは経験の乏しい若手弁護士。
この二人、存在感ある熱演にもかかわらず、映画の本筋からは不要な蛇足になりました。たとえば満島さんは真実追求派弁護士なのですが、重盛弁護士は上述の通り三隅によって真実追求派に変えられてしまうのですから、満島さんの純粋な熱血は必要ありません。吉田さんは映画の風味付けになっていますが、その割に多くのセリフがあります。ただTV連続ドラマなら二人ともぜひ必要なことはよくわかります。
三隅の第二の殺人(容疑)の被害者は、広瀬すずさん演じる山中咲江の父でした。高校生の咲江は、もう長く父親から性的虐待を受けていたのです。その咲江の難儀、不幸をどうやら解決するための殺人であった模様です(本作では示唆されるだけです)。空っぽの器男である三隅の犯行動機ですから、山中咲江の存在は重要です。
けれど、咲江がいつも足を引きずっているその原因が生まれつきなのかそうではないのか、結局真相はわからないまま。咲江の足を不自由な設定にしたのはミスリードのためのミス、ではありませんか。念のため申しますが、広瀬すずさんの影がありながら凛とした姿の演技は秀逸でした。
母親斉藤由貴さんの出番がやや長いと感じました。母親の犯行であるとほのめかした三隅の供述は、父親の性的虐待を見て見ぬ振りを続けた母親へ三隅が振り下ろした鉄槌なのでしょうから、母親は重要な役柄ではあるのですが。ただ、斉藤由貴さんの演技は真に迫って見応えがありました。
裁判官に憧れていた、という三隅のプロフィールで観客はこの母親に対する「裁き」にも薄々気がつくわけです。
それにしてもこの空っぽの器の男は随分と頭が良いですね。
さて極め付きの無駄は重盛の娘のエピソードです。蒔田彩珠さんはお気に入りの子役ですので本作に登場するのは嬉しいのです。でも、扱いが中途半端で残念でした。
アメリカ映画の刑事物でもおなじみの、父親が仕事に熱中するあまり家庭崩壊してしまうパターンの踏襲なのですが、まず本作にそれが必要でしょうか。蒔田さんが演じる娘は、万引きで補導されて保護者として(別居中の、あるいは離婚した)父重盛を指名します。父を求めているというわかりやすいサインです。でも本作にこのエピソードがなぜ組み込まれるのでしょう。
終盤に、娘との和解のサインが示されます。重盛は三隅と出会ったことで人間らしさを取り戻し、実生活でも好影響を与えた、ということなのでしょうが、それなら重盛にとってたいへん重要なことですので、もっと娘との関係を深めて描いても良かったはずです。
咲江の父を殺害して焼いた跡が十字架形に焦げていましたが、それだけではなく、十字(クロス)のモティーフが随所に登場します。
三隅は「生まれてこなければよかった人間もいるのです」と重盛に語るのですが、十字架形はその三隅による「裁き」を象徴しているのでしょうか、または犯した罪への赦しを得る象徴なのでしょうか。
唐突にキリスト教のサインが出され、私には監督の意図がわからなかったのです。この点は単に私の不明によるものかもしれません。
最後に、タイトルの解釈です。
三隅による咲江の父殺しは彼にとって二度目の殺人です。
裁判で三隅は咲江を巻き込まないように配慮し、自分の罪を認めました。これは死刑判決を意味しますし、事実そうなりました。
これを三度目の殺人と呼んでいるのでしょう。
真実がよくわからないまま死刑判決が下される、、、つまり
本作は死刑制度に対するアンチテーゼになろうともしているようですが、やはりこれまた欲張りすぎではなかったでしょうか。
なお、殺人行為の後三隅は頰の返り血を拭うような仕草をします。
終盤で、三隅に死刑判決が下された後、重盛は同じ仕草をします。
重盛も、自分が絞首刑のボタンを押した気になったのでしょうね。
しかしわざとらしいと感じました。
是枝さん、生涯に監督できる映画の本数は確かに限られていますが、
総花的な作品は観客の印象がかえってぼんやりしてしまいます。
TVの連続ものと映画とは、やはり異なる媒体だと思うのですよ。
『三度目の殺人』
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:是枝裕和
俳優:福山雅治(重盛朋章弁護士) 蒔田彩珠(重盛結花=朋章の娘) 役所広司(三隅高司)
広瀬すず(山中咲江) 斉藤由貴(山中美津江=咲江の母) 市川実日子(篠原一葵検事)
満島真之介 吉田鋼太郎 橋爪功 松岡依都美 品川徹 根岸季衣 高橋努 小倉一郎
中村まこと 井上肇
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

予告より
批評
映像作家是枝監督の実力は十分に認めています。
原作のある『海街diary』でも、そうでない『万引き家族』でも、その才能は遺憾無く発揮され、傑作を生み出しました。
しかし、すべての作品がそのレベルで仕上がるとは限りません。
『そして父になる』や本作ではそのエンジンにトルクがかからずタイヤが空転したと私は感じました。
昨年本作が公開されたとき、私は映画館に行く気が起きませんでしたが、今回『万引き家族』のカンヌ受賞を機に本作がBS/CSで放送されると知り、それならば見ておきたいと思いました。
その結果、直観が正しかったことが証明されてしまいました。
問題意識に溢れた意欲作ですから、そっとしておきたい気持ちもありますが、見てしまった以上、簡潔に批判したいと考えます。
一言で言うと、盛り過ぎ、欲張りすぎです。
『ニーチェの馬』は154分を費やして、荒野に住む父娘と馬を通じて世界の終末を描きました。
『アラビアのロレンス』は207分かけて、繊細な理想主義者の青年を通じて白人国家の傲慢を描きました。
『道』は115分を費やして、神と人の愛を知らない無知な男の悲劇を描きました。
では『三度目の殺人』は、125分かけて何を描いたのでしょう。私には的がたくさん見えました。誤解でしょうか。
中で是枝監督がもっとも描きたかったことは裁判批判だと私はみました。
「裁判は真実の追求ではなく、利害の調整になっている」という劇中のセリフが本作の核心でしょう。
その裁判の惨状を体現しているのが重盛弁護士で、福山雅治さんが好演しています。
クールに選挙戦術だけを考える重盛弁護士に立ちはだかったのは、依頼人三隅高司。罪状は殺人罪。役者は役所広司さんです。
三隅高司は供述・説明を簡単に変えていく人物。彼の何が本当で何が嘘なのかわからず、弁護士は振り回されます。
選挙戦術(たとえば死刑が相当だろうという裁判で無期懲役を勝ち取りたいなどの)が成功すれば良いとする重盛にとって、勝つためには三隅の供述が変わっては困るのですが、そうはいかない。
そこで重盛は三隅の供述の信憑性を調査せざるを得なくなりますが、それは重盛が必要ないと考えていた「真実の追求」作業に他なりません。
裁判の本来の目的が「真実の追求」という正義であるならば、皮肉なことに、そこからもっとも遠かった重盛が「正義派」として仕事せざるを得なくなリます。
殺人容疑者三隅高司は、本質的にいえば、現状の堕落した裁判を矯正する役割を果たすわけです。
三隅の一度目の殺人事件を捜査した刑事は、三隅を「空っぽの器のような男」と評します。
空っぽの器は簡単に他者の難儀を自分のものとして殺人を代行することもあるかもしれませんが、
空っぽの器は、同時に、その不可知性無限性の虚無の中に他人を取り込んでしまうのかもしれません。
三隅の弁護士としての面会を重ねるうちに、重盛はしだいにその三隅の「罠」にはまっていきます。
映像がそのことをわかりやすく表現しています。
最後には二人の顔が重なるように映し出されるのですから。
(是枝監督の作品は映像による説明が多過ぎると感じることがありますが、ここは映像による必要な説明だったと思います。これだけならば、ですが。)
ここまで私の文におつきあい下さった方は、その設定の重さに気が付かれたと思います。
謎に満ちた虚無のような男と真実の追求に関心がなかった弁護士〜〜その二人の対決と同化という道筋だけでもういっぱいいっぱいだと思いませんか。
それを描くだけで125分のうち大部分を使えば良かったのだと私は考えます。
さぞや裁判の堕落した現状を監督の鋭い刃が切り裂いたことでしょう。

予告より
ところが是枝監督は欲張るのです。
吉田鋼太郎さんと満島真之介さんがそれぞれ弁護士を演じています。吉田さんは検事から弁護士に転身したいわゆるヤメ弁。意欲に乏しい。満島さんの役どころは経験の乏しい若手弁護士。
この二人、存在感ある熱演にもかかわらず、映画の本筋からは不要な蛇足になりました。たとえば満島さんは真実追求派弁護士なのですが、重盛弁護士は上述の通り三隅によって真実追求派に変えられてしまうのですから、満島さんの純粋な熱血は必要ありません。吉田さんは映画の風味付けになっていますが、その割に多くのセリフがあります。ただTV連続ドラマなら二人ともぜひ必要なことはよくわかります。
三隅の第二の殺人(容疑)の被害者は、広瀬すずさん演じる山中咲江の父でした。高校生の咲江は、もう長く父親から性的虐待を受けていたのです。その咲江の難儀、不幸をどうやら解決するための殺人であった模様です(本作では示唆されるだけです)。空っぽの器男である三隅の犯行動機ですから、山中咲江の存在は重要です。
けれど、咲江がいつも足を引きずっているその原因が生まれつきなのかそうではないのか、結局真相はわからないまま。咲江の足を不自由な設定にしたのはミスリードのためのミス、ではありませんか。念のため申しますが、広瀬すずさんの影がありながら凛とした姿の演技は秀逸でした。
母親斉藤由貴さんの出番がやや長いと感じました。母親の犯行であるとほのめかした三隅の供述は、父親の性的虐待を見て見ぬ振りを続けた母親へ三隅が振り下ろした鉄槌なのでしょうから、母親は重要な役柄ではあるのですが。ただ、斉藤由貴さんの演技は真に迫って見応えがありました。
裁判官に憧れていた、という三隅のプロフィールで観客はこの母親に対する「裁き」にも薄々気がつくわけです。
それにしてもこの空っぽの器の男は随分と頭が良いですね。
さて極め付きの無駄は重盛の娘のエピソードです。蒔田彩珠さんはお気に入りの子役ですので本作に登場するのは嬉しいのです。でも、扱いが中途半端で残念でした。
アメリカ映画の刑事物でもおなじみの、父親が仕事に熱中するあまり家庭崩壊してしまうパターンの踏襲なのですが、まず本作にそれが必要でしょうか。蒔田さんが演じる娘は、万引きで補導されて保護者として(別居中の、あるいは離婚した)父重盛を指名します。父を求めているというわかりやすいサインです。でも本作にこのエピソードがなぜ組み込まれるのでしょう。
終盤に、娘との和解のサインが示されます。重盛は三隅と出会ったことで人間らしさを取り戻し、実生活でも好影響を与えた、ということなのでしょうが、それなら重盛にとってたいへん重要なことですので、もっと娘との関係を深めて描いても良かったはずです。
咲江の父を殺害して焼いた跡が十字架形に焦げていましたが、それだけではなく、十字(クロス)のモティーフが随所に登場します。
三隅は「生まれてこなければよかった人間もいるのです」と重盛に語るのですが、十字架形はその三隅による「裁き」を象徴しているのでしょうか、または犯した罪への赦しを得る象徴なのでしょうか。
唐突にキリスト教のサインが出され、私には監督の意図がわからなかったのです。この点は単に私の不明によるものかもしれません。
最後に、タイトルの解釈です。
三隅による咲江の父殺しは彼にとって二度目の殺人です。
裁判で三隅は咲江を巻き込まないように配慮し、自分の罪を認めました。これは死刑判決を意味しますし、事実そうなりました。
これを三度目の殺人と呼んでいるのでしょう。
真実がよくわからないまま死刑判決が下される、、、つまり
本作は死刑制度に対するアンチテーゼになろうともしているようですが、やはりこれまた欲張りすぎではなかったでしょうか。
なお、殺人行為の後三隅は頰の返り血を拭うような仕草をします。
終盤で、三隅に死刑判決が下された後、重盛は同じ仕草をします。
重盛も、自分が絞首刑のボタンを押した気になったのでしょうね。
しかしわざとらしいと感じました。
是枝さん、生涯に監督できる映画の本数は確かに限られていますが、
総花的な作品は観客の印象がかえってぼんやりしてしまいます。
TVの連続ものと映画とは、やはり異なる媒体だと思うのですよ。
2018年10月26日
『プラネタリウム』:ナタリー・ポートマンファンなら
データ
『プラネタリウム』
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:レベッカ・ズロトヴスキ
俳優:ナタリー・ポートマン(ローラ、姉) リリー=ローズ・デップ(ケイト、妹)
エマニュエル・サランジェ(コルベン)
ルイ・ガレル(フェルナンド) アミラ・カサール(エヴァ)
製作国:フランス、ベルギー
allcinemaの情報ページはこちら

公式サイトより
コメント
映画館で観れば良かったかもしれませんね。
映像も主役の姉妹もみごとに美しいから。
でもその映像の「解像度」の高さが逆に欠点にもなったのではないかなあ。
スクリーンで観ておけば映像に圧倒されて、その欠点が見えにくかったかもしれないから。
そもそもタイトルの『PLANETARIUM』が解せません。
(映画が始まると変にダサダサな活字で大写しになるのですが)
自宅の録画メディアに入れておいて、タイトルを眺めて、さあ、今夜は何を見ようかと検討している時、『プラネタリウム』というタイトルからもうミスリードされてしまいます。
というのは、記憶力が貧しい私の個人的な事情かもしれません。
内容に触れましょう、簡単に。
1930年代、まだ第二次大戦が始まる前、アメリカ人の姉妹がパリに渡ります。
二人は降霊術師との触れ込みです。
姉は司会進行、妹は降霊担当です。
戦争が近づき、人々は降霊術師を呼ぶ余裕がなくなり、興行は不調になっていきます。
そんな時、姉妹はコルベンという映画会社の重役に呼ばれ、降霊術を施します。
コルベンは霊と出会い、姉妹こそ本物の霊媒だと感じ、霊を映像化しようとひらめきます。
アメリカ映画と比べ劣勢になったフランス映画を復活させたいのです。
コルベンは姉妹に映画化を持ちかけ、了解をえます。
・・という導入部から、
コルベンの狂気のような映画への情熱。
映画界という華やかな世界とコルベンの魅力に翻弄される姉妹。
そして、
コルベンは映画に入れ込みすぎました。
また彼はユダヤ系であることが知られてしまいます。
ナチスドイツに「忖度」したフランス映画界から追放されます。
妹は降霊に力を使い果たして?死にます。
しかし姉は映画界に再び活路を見出そうと、次の一歩を踏み出します。
あらすじにもなっていませんが、ざっとそういう内容の作品でした。
ナタリー・ポートマンさんの表情演技はぴったりと状況にはまって適切です。毎回思うのですが、頭脳派ですね、演技が。考えて決めてその通り演じている様子がよくわかります。その分やや仮面的に見える時がありますが仕方ないでしょう。
リリー=ローズ・デップさんは、ついつい父のジョニー・デップさんの顔を思い浮かべてしまいがちですが、とてもナチュラルにやや暗い役柄を演じていました。
エマニュエル・サランジェさんは目が特徴的でセクシーな俳優だと思います。存在感ある演技でした。
さて、
映像の美しさに加え、ミスのないキャスティングに思えるのに、なぜ鑑賞後の心の震えがないのでしょう。
逆説的ですが、映像の「解像度」が良すぎ、姉妹が美しすぎた(=美しく撮りすぎた)ため、姉妹の胡散臭さやマイナー感が損なわれたことも一因だと思います。
真偽のわからない、放浪の降霊術師姉妹なのですから、いかに野心家な姉が仕切ろうと、もう少し野暮ったさが欲しかったと思うのです。(二人がおしゃれという意味ではなく、映像そのものを指しています。)
恐山のイタコとは言いませんが、これでは映画のリアル感が失せてしまいます。
しかし、もっと重要な敗因があります。
それは批評欄で書きます。
批評
プラネタリウム(PLANETARIUM)はほんとうの星空ではありません。
序盤に美しい本物の星空を見せ、終盤に映画セットの星空を見せます。
ですから、監督の狙いは明白です。
本作は、本物と偽物をめぐる物語なのです。
世間からは、降霊術師という存在の評価がちょうどそれに当たります。
コルベンもその真偽のボーダーに足をすくわれました。
姉妹の立場から言えば、真実スピリチュアルだった二人が、映画界に入ることで偽物になっていきます。
監督の意図はこのように明白なのに、文頭に書いたように、『PLANETARIUM』というタイトルは解せません。
監督はその意図一本に絞ってグイグイとストーリーを追っていくべきだったのです。
しかし残念ながら、美しい映像を撮ろうとしすぎました。
枝葉であるロマンスに深入りしてしまいました。
映画界やコルベンにもこだわりすぎました。
あれもこれもと欲張ってしまい、よくある新進監督の独りよがり作品になってしまったのです。
鑑賞中、鑑賞後の感動に包まれながら、
「あ〜そういうことだったのか!」と腑に落ちることは映画の醍醐味の一つですが、
本作の場合は、観客が監督に一目散に駆け寄って目を覗き込み、
「えー?それが言いたかったの?なんだあ。わかったわかった。」
と力一杯努力”してあげなければ”ならないのです。
難解な映画ではなく、未熟な映画なのです。
映像作りに才能がある女性監督だと思いますので、
今後はテーマを絞って佳作を生み出して欲しいと願います。
『プラネタリウム』
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:レベッカ・ズロトヴスキ
俳優:ナタリー・ポートマン(ローラ、姉) リリー=ローズ・デップ(ケイト、妹)
エマニュエル・サランジェ(コルベン)
ルイ・ガレル(フェルナンド) アミラ・カサール(エヴァ)
製作国:フランス、ベルギー
allcinemaの情報ページはこちら

公式サイトより
コメント
映画館で観れば良かったかもしれませんね。
映像も主役の姉妹もみごとに美しいから。
でもその映像の「解像度」の高さが逆に欠点にもなったのではないかなあ。
スクリーンで観ておけば映像に圧倒されて、その欠点が見えにくかったかもしれないから。
そもそもタイトルの『PLANETARIUM』が解せません。
(映画が始まると変にダサダサな活字で大写しになるのですが)
自宅の録画メディアに入れておいて、タイトルを眺めて、さあ、今夜は何を見ようかと検討している時、『プラネタリウム』というタイトルからもうミスリードされてしまいます。
というのは、記憶力が貧しい私の個人的な事情かもしれません。
内容に触れましょう、簡単に。
1930年代、まだ第二次大戦が始まる前、アメリカ人の姉妹がパリに渡ります。
二人は降霊術師との触れ込みです。
姉は司会進行、妹は降霊担当です。
戦争が近づき、人々は降霊術師を呼ぶ余裕がなくなり、興行は不調になっていきます。
そんな時、姉妹はコルベンという映画会社の重役に呼ばれ、降霊術を施します。
コルベンは霊と出会い、姉妹こそ本物の霊媒だと感じ、霊を映像化しようとひらめきます。
アメリカ映画と比べ劣勢になったフランス映画を復活させたいのです。
コルベンは姉妹に映画化を持ちかけ、了解をえます。
・・という導入部から、
コルベンの狂気のような映画への情熱。
映画界という華やかな世界とコルベンの魅力に翻弄される姉妹。
そして、
コルベンは映画に入れ込みすぎました。
また彼はユダヤ系であることが知られてしまいます。
ナチスドイツに「忖度」したフランス映画界から追放されます。
妹は降霊に力を使い果たして?死にます。
しかし姉は映画界に再び活路を見出そうと、次の一歩を踏み出します。
あらすじにもなっていませんが、ざっとそういう内容の作品でした。
ナタリー・ポートマンさんの表情演技はぴったりと状況にはまって適切です。毎回思うのですが、頭脳派ですね、演技が。考えて決めてその通り演じている様子がよくわかります。その分やや仮面的に見える時がありますが仕方ないでしょう。
リリー=ローズ・デップさんは、ついつい父のジョニー・デップさんの顔を思い浮かべてしまいがちですが、とてもナチュラルにやや暗い役柄を演じていました。
エマニュエル・サランジェさんは目が特徴的でセクシーな俳優だと思います。存在感ある演技でした。
さて、
映像の美しさに加え、ミスのないキャスティングに思えるのに、なぜ鑑賞後の心の震えがないのでしょう。
逆説的ですが、映像の「解像度」が良すぎ、姉妹が美しすぎた(=美しく撮りすぎた)ため、姉妹の胡散臭さやマイナー感が損なわれたことも一因だと思います。
真偽のわからない、放浪の降霊術師姉妹なのですから、いかに野心家な姉が仕切ろうと、もう少し野暮ったさが欲しかったと思うのです。(二人がおしゃれという意味ではなく、映像そのものを指しています。)
恐山のイタコとは言いませんが、これでは映画のリアル感が失せてしまいます。
しかし、もっと重要な敗因があります。
それは批評欄で書きます。
批評
プラネタリウム(PLANETARIUM)はほんとうの星空ではありません。
序盤に美しい本物の星空を見せ、終盤に映画セットの星空を見せます。
ですから、監督の狙いは明白です。
本作は、本物と偽物をめぐる物語なのです。
世間からは、降霊術師という存在の評価がちょうどそれに当たります。
コルベンもその真偽のボーダーに足をすくわれました。
姉妹の立場から言えば、真実スピリチュアルだった二人が、映画界に入ることで偽物になっていきます。
監督の意図はこのように明白なのに、文頭に書いたように、『PLANETARIUM』というタイトルは解せません。
監督はその意図一本に絞ってグイグイとストーリーを追っていくべきだったのです。
しかし残念ながら、美しい映像を撮ろうとしすぎました。
枝葉であるロマンスに深入りしてしまいました。
映画界やコルベンにもこだわりすぎました。
あれもこれもと欲張ってしまい、よくある新進監督の独りよがり作品になってしまったのです。
鑑賞中、鑑賞後の感動に包まれながら、
「あ〜そういうことだったのか!」と腑に落ちることは映画の醍醐味の一つですが、
本作の場合は、観客が監督に一目散に駆け寄って目を覗き込み、
「えー?それが言いたかったの?なんだあ。わかったわかった。」
と力一杯努力”してあげなければ”ならないのです。
難解な映画ではなく、未熟な映画なのです。
映像作りに才能がある女性監督だと思いますので、
今後はテーマを絞って佳作を生み出して欲しいと願います。
2018年10月24日
『007/サンダーボール作戦』
データ
『007/サンダーボール作戦』THUNDERBALL
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:1965年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後1,2回ビデオ等で鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:テレンス・ヤング
原作:イアン・フレミング
音楽:ジョン・バリー、モンティ・ノーマン
主題歌:トム・ジョーンズ
俳優:ショーン・コネリー クローディーヌ・オージェ アドルフォ・チェリ マルティーヌ・ベズウィック
ルチアナ・パルッツィ リク・ヴァン・ヌッター バーナード・リー ロイス・マクスウェル
デスモンド・リュウェリン フィリップ・ロック
製作国:イギリス
allcinemaの情報ページはこちら

Licensed by gettyimages
クローディーヌ・オージェさんとルチアナ・パルッツィさんが魅力的。パルッツィさん演じる美女は早めに死んでしまうのが残念。
コメント
前作『007 ゴールドフィンガー』に比べて展開のテンポが落ち、散漫・冗長になっているのが残念です。
ボンド・ガールや悪役にも前作ほどの魅力がありません。
主題歌も、トム・ジョーンズさん悪くはないけれど、やはりシャーリー・バッシーさんにはかないません。
ボンドのユーモアもやや低調。
それでもテレンス・ヤング監督らしく、どつき合いには迫力があります。
終盤の水中翼船内のアクションなど、お、ボンドほんまに殴られたんちゃう?と思ったことが2.3回ありましたから。
しかし今作の圧巻は何と言っても水中戦です。
公開された1965年の日本では、私も含め、人が水中に潜るといえば宇宙服のような潜水服しか思い浮かばなかった人が大半だったろうと思います。
ところが本作では、圧縮空気ボンベ2本を背にしょったスキューバダイバーが、敵味方入り多数入り乱れて戦闘を繰り広げるのです。
武器は水中銃とナイフ。ナイフは主にレギュレーターホース(空気が通る)を切断するのに使います。
本当に海で撮影しているのだぞと見せかけるアピールするために、タコやウツボやニシキエビ?まで登場させていますので、多少長々と続くきらいはあるものの、当時としてはもう息を飲むようなアクションシーンでした。
私も今は(いつまでたっても初心者マークながら)ダイバーのはしくれです。
改めてこのシーンを見ると、自分が海中で戦い、自分が溺れているかのようなリアル感がありました。
ショーンコネリーさんもずいぶん訓練したのだとわかります。
もし初めて観る方がおられましたら、上記の背景を頭の隅に入れ微細を逃さずしっかりご覧ください。
『007/サンダーボール作戦』THUNDERBALL
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:1965年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後1,2回ビデオ等で鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:テレンス・ヤング
原作:イアン・フレミング
音楽:ジョン・バリー、モンティ・ノーマン
主題歌:トム・ジョーンズ
俳優:ショーン・コネリー クローディーヌ・オージェ アドルフォ・チェリ マルティーヌ・ベズウィック
ルチアナ・パルッツィ リク・ヴァン・ヌッター バーナード・リー ロイス・マクスウェル
デスモンド・リュウェリン フィリップ・ロック
製作国:イギリス
allcinemaの情報ページはこちら

Licensed by gettyimages
クローディーヌ・オージェさんとルチアナ・パルッツィさんが魅力的。パルッツィさん演じる美女は早めに死んでしまうのが残念。
コメント
前作『007 ゴールドフィンガー』に比べて展開のテンポが落ち、散漫・冗長になっているのが残念です。
ボンド・ガールや悪役にも前作ほどの魅力がありません。
主題歌も、トム・ジョーンズさん悪くはないけれど、やはりシャーリー・バッシーさんにはかないません。
ボンドのユーモアもやや低調。
それでもテレンス・ヤング監督らしく、どつき合いには迫力があります。
終盤の水中翼船内のアクションなど、お、ボンドほんまに殴られたんちゃう?と思ったことが2.3回ありましたから。
しかし今作の圧巻は何と言っても水中戦です。
公開された1965年の日本では、私も含め、人が水中に潜るといえば宇宙服のような潜水服しか思い浮かばなかった人が大半だったろうと思います。
ところが本作では、圧縮空気ボンベ2本を背にしょったスキューバダイバーが、敵味方入り多数入り乱れて戦闘を繰り広げるのです。
武器は水中銃とナイフ。ナイフは主にレギュレーターホース(空気が通る)を切断するのに使います。
本当に海で撮影しているのだぞと
私も今は(いつまでたっても初心者マークながら)ダイバーのはしくれです。
改めてこのシーンを見ると、自分が海中で戦い、自分が溺れているかのようなリアル感がありました。
ショーンコネリーさんもずいぶん訓練したのだとわかります。
もし初めて観る方がおられましたら、上記の背景を頭の隅に入れ微細を逃さずしっかりご覧ください。
2018年10月24日
『アヒルと鴨のコインロッカー』:異国の風に吹かれて
データ
『アヒルと鴨のコインロッカー』The Foreign Duck, the Native Duck and God in a Coin Locker
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2007年公開
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:中村義洋
原作:伊坂幸太郎
主題歌:『風に吹かれて』Blowin' in the Wind ボブ・ディラン
俳優:濱田岳 瑛太 関めぐみ 田村圭生 関暁夫(ハローバイバイ) 杉山英一郎 東真彌 藤島陸八
岡田将生 眞島秀和 野村恵里 平田薫 寺十吾 恩田括 キムラ緑子 なぎら健壱 猫田直
土井原菜央 中村尚 佐藤楓 松田龍平 大塚寧々
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

『アヒルと鴨のコインロッカー』製作委員会
コメント
映画の最後、空港のシーンがとても印象的でした。
このラストシーンのために本作は生まれたのか、と思うほどです。
神様を空港のコインロッカーにしまいます。
神様に自分たちの「犯行」を見て見ぬ振りをしてもらうために。
神様とはボブ・ディラン。
この空港のシーンでは、濱田岳さんと瑛太さんの微妙な関係に一本の糸が繋がるような、あるいは繋がっていたことが可視化されるような気持ちになりました。
アヒルは外国人。
鴨は日本人。
両者の違いは文化の違いか人間性の違いか。
いえ、こういう書き方は作品理解のミスリードになりますね。
異文化理解を啓蒙するような堅苦しい映画ではありませんから。
脚本は適度に入り組んでいて、観客に推理せよと要求します。
ですから推理しながら観るのですが、それでもいくつもの意外な事実が明らかになり、観客は心の中で「あっ」と叫ぶのです。
真相が知らされ、決着がついても、どこか割り切れなさが残ります。(褒めてます)
とはいえ、いつもながら濱田岳さんの演技力の平凡さは並外れていますので、安心して見ておれます。(褒めてます)
いつもながら瑛太さんのどこか裏表のある人物像はやっぱりその通りなので、これまた安心です。(褒めてます)
そういう意味で意外性だけではなくサービス精神にも富んだ優しい作品だと思いました。
作品内容の詳細、特に意外な展開については語らないでおきます。
若干の物足りなさ、瑕疵についても触れないでおきます。
ただ、思います。私はブータンに旅したいと。
主題歌?「風に吹かれて」について、作者ボブ・ディランが1962年に雑誌「シング・アウト!」に掲載したコメントをwikipediaから引用して、短い感想を終わらせていただきます。(赤字は筆者)
「この歌についちゃ、あまり言えることはないけど、ただ答えは風の中で吹かれているということだ。答えは本にも載ってないし、映画やテレビや討論会を見ても分からない。風の中にあるんだ、しかも風に吹かれちまっている。ヒップな奴らは「ここに答えがある」だの何だの言ってるが、俺は信用しねえ。俺にとっちゃ風にのっていて、しかも紙切れみたいに、いつかは地上に降りてこなきゃならない。でも、折角降りてきても、誰も拾って読もうとしないから、誰にも見られず理解されず、また飛んでいっちまう。世の中で一番の悪党は、間違っているものを見て、それが間違っていると頭でわかっていても、目を背けるやつだ。俺はまだ21歳だが、そういう大人が大勢いすぎることがわかっちまった。あんたら21歳以上の大人は、だいたい年長者だし、もっと頭がいいはずだろう。」

『アヒルと鴨のコインロッカー』製作委員会
『アヒルと鴨のコインロッカー』The Foreign Duck, the Native Duck and God in a Coin Locker
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2007年公開
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:中村義洋
原作:伊坂幸太郎
主題歌:『風に吹かれて』Blowin' in the Wind ボブ・ディラン
俳優:濱田岳 瑛太 関めぐみ 田村圭生 関暁夫(ハローバイバイ) 杉山英一郎 東真彌 藤島陸八
岡田将生 眞島秀和 野村恵里 平田薫 寺十吾 恩田括 キムラ緑子 なぎら健壱 猫田直
土井原菜央 中村尚 佐藤楓 松田龍平 大塚寧々
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

『アヒルと鴨のコインロッカー』製作委員会
コメント
映画の最後、空港のシーンがとても印象的でした。
このラストシーンのために本作は生まれたのか、と思うほどです。
神様を空港のコインロッカーにしまいます。
神様に自分たちの「犯行」を見て見ぬ振りをしてもらうために。
神様とはボブ・ディラン。
この空港のシーンでは、濱田岳さんと瑛太さんの微妙な関係に一本の糸が繋がるような、あるいは繋がっていたことが可視化されるような気持ちになりました。
アヒルは外国人。
鴨は日本人。
両者の違いは文化の違いか人間性の違いか。
いえ、こういう書き方は作品理解のミスリードになりますね。
異文化理解を啓蒙するような堅苦しい映画ではありませんから。
脚本は適度に入り組んでいて、観客に推理せよと要求します。
ですから推理しながら観るのですが、それでもいくつもの意外な事実が明らかになり、観客は心の中で「あっ」と叫ぶのです。
真相が知らされ、決着がついても、どこか割り切れなさが残ります。(褒めてます)
とはいえ、いつもながら濱田岳さんの演技力の平凡さは並外れていますので、安心して見ておれます。(褒めてます)
いつもながら瑛太さんのどこか裏表のある人物像はやっぱりその通りなので、これまた安心です。(褒めてます)
そういう意味で意外性だけではなくサービス精神にも富んだ優しい作品だと思いました。
作品内容の詳細、特に意外な展開については語らないでおきます。
若干の物足りなさ、瑕疵についても触れないでおきます。
ただ、思います。私はブータンに旅したいと。
主題歌?「風に吹かれて」について、作者ボブ・ディランが1962年に雑誌「シング・アウト!」に掲載したコメントをwikipediaから引用して、短い感想を終わらせていただきます。(赤字は筆者)
「この歌についちゃ、あまり言えることはないけど、ただ答えは風の中で吹かれているということだ。答えは本にも載ってないし、映画やテレビや討論会を見ても分からない。風の中にあるんだ、しかも風に吹かれちまっている。ヒップな奴らは「ここに答えがある」だの何だの言ってるが、俺は信用しねえ。俺にとっちゃ風にのっていて、しかも紙切れみたいに、いつかは地上に降りてこなきゃならない。でも、折角降りてきても、誰も拾って読もうとしないから、誰にも見られず理解されず、また飛んでいっちまう。世の中で一番の悪党は、間違っているものを見て、それが間違っていると頭でわかっていても、目を背けるやつだ。俺はまだ21歳だが、そういう大人が大勢いすぎることがわかっちまった。あんたら21歳以上の大人は、だいたい年長者だし、もっと頭がいいはずだろう。」

『アヒルと鴨のコインロッカー』製作委員会
2018年10月22日
『ラブ&ピース』:カメちゃんうれしそうね
データ
『ラブ&ピース』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:2015年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年DVDで再視聴。
監督:園子温
特技監督:田口清隆
主題歌:RCサクセション『スローバラード』
俳優:長谷川博己(鈴木良一) 麻生久美子(寺島裕子) 大谷育江(ラブちゃんの声)
西田敏行 中川翔子(マリアの声) 犬山イヌコ(スネ公の声) 星野源(PC-300の声)
渋川清彦 奥野瑛太 マキタスポーツ 深水元基 手塚とおる 松田美由紀 神楽坂恵
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
園子温監督の会心作です。
ジャンルは怪獣特撮映画、いえ、ファンタジー。
切ないファンタジー。
子供と一緒に観られる園子温映画(笑)
主役は冴えない青年です。演じるのは長谷川博己さん。
音楽(バンド)を諦めて就職したのですが、大きな会場でのライブを夢見ています。
職場で背中に「廃棄」のラベルを貼られるなど同僚からいじめられていた青年は、ある日ふと買った子ガメ(ピカドンからラブちゃんに改名)と心を通わせます。
しかしその子ガメをこっそり勤務先に連れていったところ見咎められ、さらにいじめられる結果に。
青年はあろうことか子ガメを泣く泣くトイレに流してしまいます。なんてやつだ。
子ガメは下水を漂い、ある場所に漂着します。
そこは廃棄されてしまった人形やぬいぐるみ、ペットたちの居場所。
ゴミにされてしまった人形たちは、その場所の管理人のような謎の老人と心を通わせます。
みんな捨てられた身の上なのに、多くは「ご主人」をかばい、恋い慕っています。
流れ着いた子ガメもやはり「ご主人」を恨むことはなく、その幸せを念じ、願いを叶えてあげようとします。
・・・
地上と地下、全く別の世界どうしが、ラブちゃんという交差点で繋がるのです。
二つの異次元の世界で物語が進行するので、大作を鑑賞したような充実感が味わえ、お得です(笑)。
その大作ぶりにダメを押すのが、終盤の圧倒的な特撮です。
ご主人の願いを叶えるたびに巨大化した子ガメのラブちゃんは、ついに東京都庁までぶち壊します。
地表の権威の象徴のような都庁を破壊し、爽快です。
ルサンチマン※① 溢れるちっちゃい男鈴木良一のエレベーターのような人生の一コマを長谷川博己さんがコミカルに好演。
監督が最初に映画化しようとした時、この役を忌野清志郎さんにオファーしたとか。
長谷川さん、ギターや歌の練習は大変だったでしょうね。
その想いびと寺島裕子を演じる麻生久美子さんは持ち前のインディーズな匂い。
決して笑わないダサいダサい女性像を貫きます。
謎の老人役の西田敏行さんの台詞回しはもはや神業。
ちょっと代役はききません。
そしてこれら生きた人間たちにもまして、棄てられても再び可愛がってもらえる夢を見る人形マリアの哀愁と、
(中川翔子さん素晴らしい)、
捨てられたネコぬいぐるみスネ公のの屈折
(心情の通う声は犬山イヌコさん)、
棄てられても鈴木良一の望みを叶えることが生きがいになった可愛すぎるラブちゃんの純情に
(ピカチュウ大谷育江さんの声がたまりません)、
私の涙腺は緩みっぱなしになるのでした。
「カメちゃんうれしそうね」マリア
※①ルサンチマン(仏: ressentiment)
弱者が強者に対して、「憤り・怨恨・憎悪・非難」の感情を持つこと。(wikipedia)
キェルケゴール→ニーチェという実存主義思想家による造語。
たくさんの小ネタも満載です。
それはあるときは箴言(しんげん)のように観客の脳髄に釘を打ち込み、
またあるときは観客のハートを羽根箒のようにくすぐります。
例えば、
東京五輪とピカドン(原爆の異名)の並立や、
そのピカドンの代わりの歌詞がラブ&ピースになったことや、
『地獄でなぜ悪い』の挿入歌「全力歯ぎしりレッツゴー」の歌や、
忌野清志郎そっくりの衣装で歌う鈴木良一や、
きらびやかなクリスマス前の地上と薄暗く臭い地下の下水道世界との対比や、
『ファインディング・ニモ』のニモのようにトイレに流されるピカドンや、
『未来世紀ブラジル』の劣化コピーのように舞う書類や、
田原総一郎さんの討論番組が総力をあげて鈴木良一をディスりにかかることや、
・・・
ほんとうに盛りだくさんで楽しめます。

コメント2
西田敏行さん演じる謎の老人は実はサンタクロースなのでした。
毎年子どもたちに贈ったプレゼントが無残な姿で捨てられたり、下水に流れついたりします。
老人はその人形やぬいぐるみやペットたちに話ができる飴をなめさせ、
次のクリスマスまで一緒に暮らしているのです。
クリスマスがやってくると、老人は彼らを眠らせ、記憶を消し、新品や子犬などに戻してもう一度子どもたちに配るのです。
でも彼らは何度も何度も繰り返し下水に流れ着くのです。
マリアがクリスマスのショーウィンドーを理由はわからないまま懐かしそうに見入っている姿が忘れられません。
どうぞ、大切にしてあげてくださいね。
『ラブ&ピース』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:2015年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年DVDで再視聴。
監督:園子温
特技監督:田口清隆
主題歌:RCサクセション『スローバラード』
俳優:長谷川博己(鈴木良一) 麻生久美子(寺島裕子) 大谷育江(ラブちゃんの声)
西田敏行 中川翔子(マリアの声) 犬山イヌコ(スネ公の声) 星野源(PC-300の声)
渋川清彦 奥野瑛太 マキタスポーツ 深水元基 手塚とおる 松田美由紀 神楽坂恵
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
園子温監督の会心作です。
ジャンルは怪獣特撮映画、いえ、ファンタジー。
切ないファンタジー。
子供と一緒に観られる園子温映画(笑)
主役は冴えない青年です。演じるのは長谷川博己さん。
音楽(バンド)を諦めて就職したのですが、大きな会場でのライブを夢見ています。
職場で背中に「廃棄」のラベルを貼られるなど同僚からいじめられていた青年は、ある日ふと買った子ガメ(ピカドンからラブちゃんに改名)と心を通わせます。
しかしその子ガメをこっそり勤務先に連れていったところ見咎められ、さらにいじめられる結果に。
青年はあろうことか子ガメを泣く泣くトイレに流してしまいます。なんてやつだ。
子ガメは下水を漂い、ある場所に漂着します。
そこは廃棄されてしまった人形やぬいぐるみ、ペットたちの居場所。
ゴミにされてしまった人形たちは、その場所の管理人のような謎の老人と心を通わせます。
みんな捨てられた身の上なのに、多くは「ご主人」をかばい、恋い慕っています。
流れ着いた子ガメもやはり「ご主人」を恨むことはなく、その幸せを念じ、願いを叶えてあげようとします。
・・・
地上と地下、全く別の世界どうしが、ラブちゃんという交差点で繋がるのです。
二つの異次元の世界で物語が進行するので、大作を鑑賞したような充実感が味わえ、お得です(笑)。
その大作ぶりにダメを押すのが、終盤の圧倒的な特撮です。
ご主人の願いを叶えるたびに巨大化した子ガメのラブちゃんは、ついに東京都庁までぶち壊します。
地表の権威の象徴のような都庁を破壊し、爽快です。
ルサンチマン※① 溢れるちっちゃい男鈴木良一のエレベーターのような人生の一コマを長谷川博己さんがコミカルに好演。
監督が最初に映画化しようとした時、この役を忌野清志郎さんにオファーしたとか。
長谷川さん、ギターや歌の練習は大変だったでしょうね。
その想いびと寺島裕子を演じる麻生久美子さんは持ち前のインディーズな匂い。
決して笑わないダサいダサい女性像を貫きます。
謎の老人役の西田敏行さんの台詞回しはもはや神業。
ちょっと代役はききません。
そしてこれら生きた人間たちにもまして、棄てられても再び可愛がってもらえる夢を見る人形マリアの哀愁と、
(中川翔子さん素晴らしい)、
捨てられたネコぬいぐるみスネ公のの屈折
(心情の通う声は犬山イヌコさん)、
棄てられても鈴木良一の望みを叶えることが生きがいになった可愛すぎるラブちゃんの純情に
(ピカチュウ大谷育江さんの声がたまりません)、
私の涙腺は緩みっぱなしになるのでした。
「カメちゃんうれしそうね」マリア
※①ルサンチマン(仏: ressentiment)
弱者が強者に対して、「憤り・怨恨・憎悪・非難」の感情を持つこと。(wikipedia)
キェルケゴール→ニーチェという実存主義思想家による造語。
たくさんの小ネタも満載です。
それはあるときは箴言(しんげん)のように観客の脳髄に釘を打ち込み、
またあるときは観客のハートを羽根箒のようにくすぐります。
例えば、
東京五輪とピカドン(原爆の異名)の並立や、
そのピカドンの代わりの歌詞がラブ&ピースになったことや、
『地獄でなぜ悪い』の挿入歌「全力歯ぎしりレッツゴー」の歌や、
忌野清志郎そっくりの衣装で歌う鈴木良一や、
きらびやかなクリスマス前の地上と薄暗く臭い地下の下水道世界との対比や、
『ファインディング・ニモ』のニモのようにトイレに流されるピカドンや、
『未来世紀ブラジル』の劣化コピーのように舞う書類や、
田原総一郎さんの討論番組が総力をあげて鈴木良一をディスりにかかることや、
・・・
ほんとうに盛りだくさんで楽しめます。

コメント2
西田敏行さん演じる謎の老人は実はサンタクロースなのでした。
毎年子どもたちに贈ったプレゼントが無残な姿で捨てられたり、下水に流れついたりします。
老人はその人形やぬいぐるみやペットたちに話ができる飴をなめさせ、
次のクリスマスまで一緒に暮らしているのです。
クリスマスがやってくると、老人は彼らを眠らせ、記憶を消し、新品や子犬などに戻してもう一度子どもたちに配るのです。
でも彼らは何度も何度も繰り返し下水に流れ着くのです。
マリアがクリスマスのショーウィンドーを理由はわからないまま懐かしそうに見入っている姿が忘れられません。
どうぞ、大切にしてあげてくださいね。
2018年10月20日
『歌謡曲だよ、人生は』
データ
『歌謡曲だよ、人生は』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2007年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:オムニバスにつき下記に一覧
俳優:オムニバスにつき下記に一覧
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

(C) 2007アルタミラピクチャーズ/ポニーキャニオン/ザナドゥー
コメント
オープニング・エンディングまで含めると全12作品のオムニバス。
それぞれ異なる昭和歌謡曲各1曲をモチーフにそれぞれの監督が自由に制作。
ラインアップは以下の通り。(wikipediaのお世話になりました)
あなたのお好きな歌謡曲はありましたでしょうか。
私の場合、「ダンシング・セブンティーン」と「これが青春だ」 以外はよく知っていて、しかも好きな曲ばかり。
中でも「ざんげの値打ちもない」は、別ブログ「あんたの歌を 聞かせてくれ」で選んだ日本語の名歌名唱百選に選ばせていただいた大好きな曲です。
もちろん、それぞれの監督たちと私とでは、その曲の内容やイメージが異なる場合が多いのですが、そんなことは当たり前。
気にならずに2時間楽しめました。
オムニバス映画にはあまり食指が働かない私ですので、数少ない体験の『ユメ十夜』と比較してみます。
『ユメ十夜』は、臆病な料理人の調理。端正に調えられているものの独創性がなく、食べても力が湧かない料理。
『歌謡曲・・』は素人料理。独創性に富んでいるから当たり外れはあるものの、調理人のエネルギーが伝わって元気が出る料理。
と言えましょう。
心に元気が減り、何だか平板な毎日を過ごしておられるあなたなら、もしかするとニンニクたっぷりの餃子を食べた後のように力が湧いてくるかもしれません。
ま、少し褒めすぎですが。

予告編より
オープニング「ダンシング・セブンティーン」 (歌:オックス)
第1話 「僕は泣いちっち 」(歌:守屋浩)オススメ
監督・脚本 - 磯村一路
出演 - 青木崇高、伴杏里、六平直政、下元史朗
見所:原曲の「僕も行こう、あの娘の住んでる東京へ」(浜口庫之助)を実行してしまった青年のお話。青木崇高さんの「オレはヤルゼ」感がgood。(by 妻)
第2話 「これが青春だ」 (歌:布施明)
監督・脚本 - 七字幸久
出演 - 松尾諭、加藤理恵、U.K.、池田貴美子、徳井優、田中要次
見所:松尾諭さんの切ないエアギターは必見かも。確かにまあ青春だわさ。でもそもそもは主人公が恋をするにはだらしなかったせいだね。
第3話 「小指の想い出 」(歌:伊東ゆかり)
監督・脚本 - タナカ・T
出演 - 大杉漣、高松いく、中山卓也
見所:高松いくさんの笑顔は可愛い。原曲が流行していた頃に付き合っていて、、、という設定でしょうが、映画との関係に説得力は乏しい。昔の彼女そっくりのラブドール、、という内容は切ないというより気色悪いよ。映像もカラオケ背景映像以下。
第4話「ラブユー東京」 (歌:黒沢明とロス・プリモス)オススメ
監督・脚本 - 片岡英子
出演 - 正名僕蔵、本田大輔、千崎若菜
見所:もっともシュールな作品。先史時代に好き合っていたゲイのカップルが火山噴火のせいでなぜか現代に生まれ変わったものの、愛する彼は女性が好きな男になっていた・・悲哀といえば悲哀ですが、ぶっ飛んだ設定に笑えます。
もっとも妻はゲイのカップルではなく、男女だった、それが性別を変えて生まれ変わったのだと言います。それはそれでぶっ飛んでますから、どちらでもいいでしょうかしら。
第5話 「女のみち」(歌:宮史郎)オススメ
監督・脚本 - 三原光尋
出演 - 宮史郎、久野雅弘、板谷由夏
見所:昔のお笑い芸人さんは歌も芝居もお上手です。妻は板谷さんの起用に驚く妻。詳しくは後述。
第6話 「ざんげの値打ちもない 」(歌:北原ミレイ)オススメ
監督・脚本 - 水谷俊之
出演 - 余貴美子、山路和弘、吉高由里子、山根和馬
見所:若い吉高さん(いい目つき)に過去の自分を重ね合わせ、自分の轍を踏まないように自立を促す、やさぐれ余貴美子さんの目の表情が絶品です。場末感のある映像は歌ともマッチ。
第7話 「いとしのマックス/マックス・ア・ゴーゴー」 (歌:荒木一郎)オススメ
監督・脚本 - 蛭子能収
出演 - 武田真治、インリン・オブ・ジョイトイ、久保麻衣子、矢沢心、希和、長井秀和
見所:血まみれバイオレンス。蛭子さんの漫画そのままのはちゃめちゃな結末に映画の楽しさを感じました。妻によれば原曲がそのまま生かされていると。でもまさか「真っ赤なドレス」がこう使われるとは!武田真治さんのドヤ顔に悶え笑い。ヒロインは顔を引きつらせたまま。二人の今後がどうなるかはもうはっきり見えますね。
第8話 「乙女のワルツ」 (歌:伊藤咲子)
監督・脚本 - 宮島竜治
出演 - マモル・マヌー、内田朝陽、高橋真唯、梅沢昌代、山下敦弘、エディ藩、鈴木ヒロミツ
見所:原曲とのマッチングに失敗。映像の印象は薄くて、カラオケ背景映像の域を出ません。最後に主役を現実に戻す梅沢昌代さんはいい味。それにしても伊藤咲子さんの歌が胸を打つとは予想外でした。いい曲ですね。
第9話 「逢いたくて逢いたくて」 (歌:園まり)オススメ
監督・脚本 - 矢口史靖
出演 - 妻夫木聡、伊藤歩、ベンガル、江口のりこ、堺沢隆史、寺部智英、小林トシ江
見所:越した先の部屋の前住人との心温まるエピソード。脚本・演出の完成度の高さはさすが矢口監督。妻夫木さんと伊藤さんが主役という豪華版ですから当然かもしれませんが。ベンガルさんの心情と原曲の雰囲気は私にはミスマッチでした。とはいえ歌謡曲ファンでない方にもこの作品だけはご覧になれば?と薦めます。
第10話 「みんな夢の中」 (歌:高田恭子)
監督・脚本 - おさだたつや
出演 - 高橋恵子、烏丸せつこ、松金よね子、キムラ緑子、田山涼成、本田博太郎、鈴木ヒロミツ、北見敏之、村松利史
見所:同窓会のお話。高橋恵子さんは雰囲気あるわねと妻。そうなんです、ならばもう少し高橋さんに焦点を絞れば良かった。散漫で冗長な印象。また、子ども時代の回想を「みんな夢の中」と括るのは無理筋でしょう。
エンディング「東京ラプソディ」 (歌:渥美二郎、オリジナル:藤山一郎)
監督・脚本 - 山口晃二
出演 - 瀬戸朝香、田口浩正、中村咲哉
私たち夫婦は各々のベスト3を作ってみました。
妻
第一位 「逢いたくて逢いたくて」
第二位 「ざんげの値打ちもない 」
第三位 「ラブユー東京」
私
第一位 「女のみち」
第二位 「いとしのマックス/マックス・ア・ゴーゴー」
第三位 「ざんげの値打ちもない 」
ちなみに、「こんな映画は見ちゃいけない」さんのベストスリーは、以下の模様です。
第一位 「女のみち」
第二位 「小指の思い出」
第二位 「 いとしのマックス/マックス・ア・ゴーゴー」
また、「365日映画コラム」さんは、本作全体を痛烈に批判される中で、二作品だけ推しておられます。それは
「女のみち」
「逢いたくて逢いたくて」
他の方の好みも尋ねてみたいものです。
できれば全世界の人々にみていただいて(笑)

シネマぴあ
ですが、私の中で「女のみち」の首位は動かないでしょう。
これこそオムニバス短編映画の代表例とすら思います。
サウナに耐えている青年。
そこに刺青のヤクザが入室。
「女のみち」の歌詞がどうしても思い出せない、と。
服役生活中、週に一回面会に来てくれた女性がいて、その女性のためにもどうしても思い出したいと。
歌詞を思い出す手伝いをさせられる青年。
思い出すまでサウナから出してもらえない。
・・・
そのヤクザを演じるのがぴんからトリオの宮史郎さん。
ご本人が歌うのは本作ではこの短編だけ。
歌詞を思い出した後には銭湯の客たちの声援に包まれて熱唱。
銭湯を後にしたら、
何と和服姿の美女、板谷由夏さんが待っている。
面会の女性とは板谷さんだったのか!
その二人を眺め、胸ふくらませて「良かったあ」と笑顔になる青年・・・
この面白さと意外性に溢れる設定を考えた三原光尋監督は、関西を活動拠点にする映画監督。
大阪芸大出身だそうな。
『歌謡曲だよ、人生は』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2007年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:オムニバスにつき下記に一覧
俳優:オムニバスにつき下記に一覧
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

(C) 2007アルタミラピクチャーズ/ポニーキャニオン/ザナドゥー
コメント
オープニング・エンディングまで含めると全12作品のオムニバス。
それぞれ異なる昭和歌謡曲各1曲をモチーフにそれぞれの監督が自由に制作。
ラインアップは以下の通り。(wikipediaのお世話になりました)
あなたのお好きな歌謡曲はありましたでしょうか。
私の場合、「ダンシング・セブンティーン」と「これが青春だ」 以外はよく知っていて、しかも好きな曲ばかり。
中でも「ざんげの値打ちもない」は、別ブログ「あんたの歌を 聞かせてくれ」で選んだ日本語の名歌名唱百選に選ばせていただいた大好きな曲です。
もちろん、それぞれの監督たちと私とでは、その曲の内容やイメージが異なる場合が多いのですが、そんなことは当たり前。
気にならずに2時間楽しめました。
オムニバス映画にはあまり食指が働かない私ですので、数少ない体験の『ユメ十夜』と比較してみます。
『ユメ十夜』は、臆病な料理人の調理。端正に調えられているものの独創性がなく、食べても力が湧かない料理。
『歌謡曲・・』は素人料理。独創性に富んでいるから当たり外れはあるものの、調理人のエネルギーが伝わって元気が出る料理。
と言えましょう。
心に元気が減り、何だか平板な毎日を過ごしておられるあなたなら、もしかするとニンニクたっぷりの餃子を食べた後のように力が湧いてくるかもしれません。
ま、少し褒めすぎですが。

予告編より
オープニング「ダンシング・セブンティーン」 (歌:オックス)
第1話 「僕は泣いちっち 」(歌:守屋浩)オススメ
監督・脚本 - 磯村一路
出演 - 青木崇高、伴杏里、六平直政、下元史朗
見所:原曲の「僕も行こう、あの娘の住んでる東京へ」(浜口庫之助)を実行してしまった青年のお話。青木崇高さんの「オレはヤルゼ」感がgood。(by 妻)
第2話 「これが青春だ」 (歌:布施明)
監督・脚本 - 七字幸久
出演 - 松尾諭、加藤理恵、U.K.、池田貴美子、徳井優、田中要次
見所:松尾諭さんの切ないエアギターは必見かも。確かにまあ青春だわさ。でもそもそもは主人公が恋をするにはだらしなかったせいだね。
第3話 「小指の想い出 」(歌:伊東ゆかり)
監督・脚本 - タナカ・T
出演 - 大杉漣、高松いく、中山卓也
見所:高松いくさんの笑顔は可愛い。原曲が流行していた頃に付き合っていて、、、という設定でしょうが、映画との関係に説得力は乏しい。昔の彼女そっくりのラブドール、、という内容は切ないというより気色悪いよ。映像もカラオケ背景映像以下。
第4話「ラブユー東京」 (歌:黒沢明とロス・プリモス)オススメ
監督・脚本 - 片岡英子
出演 - 正名僕蔵、本田大輔、千崎若菜
見所:もっともシュールな作品。先史時代に好き合っていたゲイのカップルが火山噴火のせいでなぜか現代に生まれ変わったものの、愛する彼は女性が好きな男になっていた・・悲哀といえば悲哀ですが、ぶっ飛んだ設定に笑えます。
もっとも妻はゲイのカップルではなく、男女だった、それが性別を変えて生まれ変わったのだと言います。それはそれでぶっ飛んでますから、どちらでもいいでしょうかしら。
第5話 「女のみち」(歌:宮史郎)オススメ
監督・脚本 - 三原光尋
出演 - 宮史郎、久野雅弘、板谷由夏
見所:昔のお笑い芸人さんは歌も芝居もお上手です。妻は板谷さんの起用に驚く妻。詳しくは後述。
第6話 「ざんげの値打ちもない 」(歌:北原ミレイ)オススメ
監督・脚本 - 水谷俊之
出演 - 余貴美子、山路和弘、吉高由里子、山根和馬
見所:若い吉高さん(いい目つき)に過去の自分を重ね合わせ、自分の轍を踏まないように自立を促す、やさぐれ余貴美子さんの目の表情が絶品です。場末感のある映像は歌ともマッチ。
第7話 「いとしのマックス/マックス・ア・ゴーゴー」 (歌:荒木一郎)オススメ
監督・脚本 - 蛭子能収
出演 - 武田真治、インリン・オブ・ジョイトイ、久保麻衣子、矢沢心、希和、長井秀和
見所:血まみれバイオレンス。蛭子さんの漫画そのままのはちゃめちゃな結末に映画の楽しさを感じました。妻によれば原曲がそのまま生かされていると。でもまさか「真っ赤なドレス」がこう使われるとは!武田真治さんのドヤ顔に悶え笑い。ヒロインは顔を引きつらせたまま。二人の今後がどうなるかはもうはっきり見えますね。
第8話 「乙女のワルツ」 (歌:伊藤咲子)
監督・脚本 - 宮島竜治
出演 - マモル・マヌー、内田朝陽、高橋真唯、梅沢昌代、山下敦弘、エディ藩、鈴木ヒロミツ
見所:原曲とのマッチングに失敗。映像の印象は薄くて、カラオケ背景映像の域を出ません。最後に主役を現実に戻す梅沢昌代さんはいい味。それにしても伊藤咲子さんの歌が胸を打つとは予想外でした。いい曲ですね。
第9話 「逢いたくて逢いたくて」 (歌:園まり)オススメ
監督・脚本 - 矢口史靖
出演 - 妻夫木聡、伊藤歩、ベンガル、江口のりこ、堺沢隆史、寺部智英、小林トシ江
見所:越した先の部屋の前住人との心温まるエピソード。脚本・演出の完成度の高さはさすが矢口監督。妻夫木さんと伊藤さんが主役という豪華版ですから当然かもしれませんが。ベンガルさんの心情と原曲の雰囲気は私にはミスマッチでした。とはいえ歌謡曲ファンでない方にもこの作品だけはご覧になれば?と薦めます。
第10話 「みんな夢の中」 (歌:高田恭子)
監督・脚本 - おさだたつや
出演 - 高橋恵子、烏丸せつこ、松金よね子、キムラ緑子、田山涼成、本田博太郎、鈴木ヒロミツ、北見敏之、村松利史
見所:同窓会のお話。高橋恵子さんは雰囲気あるわねと妻。そうなんです、ならばもう少し高橋さんに焦点を絞れば良かった。散漫で冗長な印象。また、子ども時代の回想を「みんな夢の中」と括るのは無理筋でしょう。
エンディング「東京ラプソディ」 (歌:渥美二郎、オリジナル:藤山一郎)
監督・脚本 - 山口晃二
出演 - 瀬戸朝香、田口浩正、中村咲哉
私たち夫婦は各々のベスト3を作ってみました。
妻
第一位 「逢いたくて逢いたくて」
第二位 「ざんげの値打ちもない 」
第三位 「ラブユー東京」
私
第一位 「女のみち」
第二位 「いとしのマックス/マックス・ア・ゴーゴー」
第三位 「ざんげの値打ちもない 」
ちなみに、「こんな映画は見ちゃいけない」さんのベストスリーは、以下の模様です。
第一位 「女のみち」
第二位 「小指の思い出」
第二位 「 いとしのマックス/マックス・ア・ゴーゴー」
また、「365日映画コラム」さんは、本作全体を痛烈に批判される中で、二作品だけ推しておられます。それは
「女のみち」
「逢いたくて逢いたくて」
他の方の好みも尋ねてみたいものです。
できれば全世界の人々にみていただいて(笑)

シネマぴあ
ですが、私の中で「女のみち」の首位は動かないでしょう。
これこそオムニバス短編映画の代表例とすら思います。
サウナに耐えている青年。
そこに刺青のヤクザが入室。
「女のみち」の歌詞がどうしても思い出せない、と。
服役生活中、週に一回面会に来てくれた女性がいて、その女性のためにもどうしても思い出したいと。
歌詞を思い出す手伝いをさせられる青年。
思い出すまでサウナから出してもらえない。
・・・
そのヤクザを演じるのがぴんからトリオの宮史郎さん。
ご本人が歌うのは本作ではこの短編だけ。
歌詞を思い出した後には銭湯の客たちの声援に包まれて熱唱。
銭湯を後にしたら、
何と和服姿の美女、板谷由夏さんが待っている。
面会の女性とは板谷さんだったのか!
その二人を眺め、胸ふくらませて「良かったあ」と笑顔になる青年・・・
この面白さと意外性に溢れる設定を考えた三原光尋監督は、関西を活動拠点にする映画監督。
大阪芸大出身だそうな。
2018年10月18日
『ガール・オン・ザ・トレイン』
データ
『ガール・オン・ザ・トレイン』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2016年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:テイト・テイラー
原作:ポーラ・ホーキンズ
音楽:ダニー・エルフマン
俳優:エミリー・ブラント(レイチェル) レベッカ・ファーガソン(アナ) ヘイリー・ベネット(メガン)
ジャスティン・セロー(トム) ルーク・エヴァンス(スコット) アリソン・ジャネイ(ライリー刑事)
リサ・クドロー(マーサ) ローラ・プリポン(キャシー) エドガー・ラミレス(カマル医師)
ダーレン・ゴールドスタイン(スーツの男)
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

©UNIVERSAL PICTURES
コメント
しっとりした映像。
心理サスペンス+メロドラマ。
女優たちの競演。
アメリカ映画なのに郊外鉄道の車内や美しい車窓風景がたっぷり。
珍しいと思いましたが、原作がイギリスの小説だと知って、なるほどと思いました。
ロンドンをニューヨークに置き換えて映画化したようです。
アルコール依存症でしばしば記憶を失う女性レイチェルが主人公。
彼女を演じるエミリー・ブラントさんの演技が素晴らしい。
不安、渇き、妄想、安堵、、心理的な上がり下がりの表情がとてもわかりやすい。
他の女性俳優陣も、エミリー・ブラントさんから一歩引いたところで地味な好演。
レベッカ・ファーガソンさんは漠たる不安を、ヘイリー・ベネットさんは切なさを、それぞれ適度に表現していますが、
私が特に印象に残ったのは、事件を捜査するライリー刑事を演じたアリソン・ジャネイさんの鉄の女ぶりと、元夫の元上司の妻マーサ役のリサ・クドローさんの起承転結の「転」の輝きでした。
上記以外では、少し物足りなさが残りました。
男優たちの存在感がやや薄っぺら過ぎ。
セックスに関わるシーンが多過ぎ。
あざといくらいにミスリードを誘う回想シーンがあり過ぎ。
それにもかかわらず、序盤で真犯人が推察できる底の浅さ。
それでも、欧州の映画かと思わせる粋な映像やシーン、
それに、繰り返しますが、エミリー・ブラントさんの秀逸な演技は、
観て良かったと思わせてくれました。
なお、タイトルの「ガール」。妻は関心を示しています。
アメリカで、あるいは原作のイギリスで、「ガール」という語はいまどのように使われているのでしょうか。
主要な登場人物は一昔前なら「ガール」とは呼ばれないであろう年齢の女性たち。
どなたか、欧米の現在の女性への呼称を教えて欲しいです。

予告編より
『ガール・オン・ザ・トレイン』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2016年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:テイト・テイラー
原作:ポーラ・ホーキンズ
音楽:ダニー・エルフマン
俳優:エミリー・ブラント(レイチェル) レベッカ・ファーガソン(アナ) ヘイリー・ベネット(メガン)
ジャスティン・セロー(トム) ルーク・エヴァンス(スコット) アリソン・ジャネイ(ライリー刑事)
リサ・クドロー(マーサ) ローラ・プリポン(キャシー) エドガー・ラミレス(カマル医師)
ダーレン・ゴールドスタイン(スーツの男)
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

©UNIVERSAL PICTURES
コメント
しっとりした映像。
心理サスペンス+メロドラマ。
女優たちの競演。
アメリカ映画なのに郊外鉄道の車内や美しい車窓風景がたっぷり。
珍しいと思いましたが、原作がイギリスの小説だと知って、なるほどと思いました。
ロンドンをニューヨークに置き換えて映画化したようです。
アルコール依存症でしばしば記憶を失う女性レイチェルが主人公。
彼女を演じるエミリー・ブラントさんの演技が素晴らしい。
不安、渇き、妄想、安堵、、心理的な上がり下がりの表情がとてもわかりやすい。
他の女性俳優陣も、エミリー・ブラントさんから一歩引いたところで地味な好演。
レベッカ・ファーガソンさんは漠たる不安を、ヘイリー・ベネットさんは切なさを、それぞれ適度に表現していますが、
私が特に印象に残ったのは、事件を捜査するライリー刑事を演じたアリソン・ジャネイさんの鉄の女ぶりと、元夫の元上司の妻マーサ役のリサ・クドローさんの起承転結の「転」の輝きでした。
上記以外では、少し物足りなさが残りました。
男優たちの存在感がやや薄っぺら過ぎ。
セックスに関わるシーンが多過ぎ。
あざといくらいにミスリードを誘う回想シーンがあり過ぎ。
それにもかかわらず、序盤で真犯人が推察できる底の浅さ。
それでも、欧州の映画かと思わせる粋な映像やシーン、
それに、繰り返しますが、エミリー・ブラントさんの秀逸な演技は、
観て良かったと思わせてくれました。
なお、タイトルの「ガール」。妻は関心を示しています。
アメリカで、あるいは原作のイギリスで、「ガール」という語はいまどのように使われているのでしょうか。
主要な登場人物は一昔前なら「ガール」とは呼ばれないであろう年齢の女性たち。
どなたか、欧米の現在の女性への呼称を教えて欲しいです。

予告編より
2018年10月16日
『チャーリーとチョコレート工場』
データ
『チャーリーとチョコレート工場』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:2005年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:ティム・バートン
原作:ロアルド・ダール
音楽:ダニー・エルフマン
俳優:ジョニー・デップ(ウィリー・ウォンカ) フレディ・ハイモア(チャーリー・バケット)
ディープ・ロイ(ウンパ・ルンパ) ヘレナ・ボナム・カーター デヴィッド・ケリー
クリストファー・リー ミッシー・パイル
ジェームズ・フォックス アダム・ゴドリー フランツィスカ・トローグナー アナソフィア・ロブ
ジュリア・ウィンター ジョーダン・フライ フィリップ・ウィーグラッツ リズ・スミス
アイリーン・エッセル デヴィッド・モリス
製作国:アメリカ、イギリス
allcinemaの情報ページはこちら

Warner Bros./Photofest/MediaVast Japan
コメント
ティム・バートン監督の素晴らしい想像力で描かれた本作のカラフルな映像が私を魅了し、
初見では物語が把握できなかったほどです。
(難しい映画じゃないのにね)
ことしようやく見直しが叶い、物語がそっくり理解できました。
ただ以下の文では痒いところに手が届かないような書き方になっています。
初見の際の私の戸惑いを少し滲ませて書いておりますから。
2005年にこの映画を見たとき、ロアルド・ダール(原作者)という作家を思い出しました。
1960年代後半に、世界の流行から少し遅れて日本でも「奇妙な味」ブームが起こりました。
SFとも怪奇ともつかぬ不思議で後味の割り切れない小説群のことです。
(きっかけは少年マガジンだったかの漫画でしたけれど)
私はブームに乗って、サキ、マルセル・エーメ、ジョン・コリアなど読みふけったのですが、ロアルド・ダールの作品も1、2冊は読んだように思います。ただ、本作の原作『チョコレート工場の秘密』は読んでいません。
改めてダールの諸作品の書評など読んでみますと、なかなかにブラックな風刺が散りばめられている様子。
宮崎駿さんがダールを好きだと初めて知りました。
そういう「奇妙な味」作家の一人が書いたブラックな小説を、ティム・バートンさんという辛辣であることがアイデンティティーな監督が映画化したわけですから、これはもう棘(トゲ)だらけのファンタジーになるのも当然と言えましょう。
棘については批評欄に書きます。
とはいえ、本作の結末はわかりやすいハッピーエンド。
このわかりやすさが少し不満です。「奇妙な味」ファンとしては。
高校教員時代にこの映画が好きだという高校生に数多く出会ったことはいまでも不思議です。
こんな悪意に満ちた映画を?
もちろん中にジョニー・デップさんファンもいたでしょうが、なんだかみんな瞳をキラーんとさせて本作が好きだと言っていた様子から、ディズニーに飽き足りないファンタジーファンを惹きつけたのかな、と思ったりしたものです。
でも残念ながら理由は聞き漏らしました。
本作の棘だらけの痛さは彼女たちにとってスパイスだったのでしょうか。
それとも、そういう痛みがわかる世代だったのでしょうか。
チャーリーはウィリー・ウォンカの秘密のチョコレート工場の見学ができるゴールドチケットが欲しくて前倒しして食べたチョコレートにチケットは入っていませんでした。
(↑息継ぎなしで読んでね)
祖父はなけなしのへそくりをチャーリーに渡してチョコレートを買っておいでというのですが、そこにもチケットはありません。
落胆していたチャーリーは、積もった雪の中に一枚の紙幣が落ちているのを見つけました。
チョコレートを買うと、見事に金色に輝くチケットが入っていました。
チャーリーが拾った金でチョコレートを買うことへのためらいのなさに驚きます。
ジョニー・デップさんの偏屈な人物造形に拍手を惜しみません。
また、ヘレナ・ボナム・カーターさんのいつものリアル感溢れる脇役ぶりに賛辞を。でも、
ここでは165役をこなしたディープ・ロイ(ウンパ・ルンパ役)さんに敬意を表し、下記の動画を共有します。
「Oompa Loompa Song」:Tim KnightさんのYoutube。
批評:チョコレートのトゲ
『アリス・イン・ワンダーランド』でも書いたように、
バートン監督の映画にはサボテンのように棘(トゲ)が植えられています。
毒や悪意や辛辣な風刺などという形で作品が飾られています。
本作にも各種の棘があり、たとえば子供に対する憎悪がその代表例なのですが、
中でも私が最も痛く感じた棘は、産業社会の酷薄さという棘でした。
主人公チャーリー少年の住むボロ家は、もちろん何より大切な家族、の象徴なのですが、
そのボロぶりは凄まじく、家屋は傾き、雪が降るようなこの町なのに天井に大穴が空いています。
その家には老人(祖父母)が4人住んでいて、その世話に明け暮れる母と、歯磨き粉工場に勤める父、そしてチャーリー、の計7人が暮らしています。
毎晩の夕食はキャベツスープだけです。
チャーリーは年に一度の誕生日にチョコレートが食べられるだけ。(それすらみんなに分けます)
歯磨き工場の給料はとても安いようです。
チャーリーにへそくりを渡した祖父は、かつてチョコレート工場で働いていましたが、産業スパイに怒った経営者ウォンカは従業員全員に解雇を申し渡しました。
祖父はもちろん、解雇された従業員の怒りの声は描かれません。
歯磨き工場へのロボット導入で父はクビになりますが、なぜかそのロボットの修理技術者として再雇用され、家庭での食事情は飛躍的に好転します。キャベツスープが肉の塊になるのです。ロボット導入で解雇された従業員はチャーリーの父親だけではないでしょう。他の元従業員たちは再雇用されたのでしょうか、とても気になります。
その他様々な場面で、「貧乏人」と「金持ち」「超金持ち」との大きな差が描かれます。
チャーリーはウォンカからの「超金持ち」になるだろう提案を拒み、貧しくても家族と一緒に暮らすことを選びます。
貧乏人の私としては救いがあります。
ですが、結局エンディングでチャーリーはウォンカの提案を呑み、チョコレート工場の跡取りとなりました。
とはいえ、家族とともに工場内で住み、その住まいはこれまで通りのボロ家。
わざわざ移設したのですね。
狭いスペースで家族みんなが仲良く暮らす家。
その家ではウォンカまで一緒に食事をとり、チャーリーの母親のマナー指導を受けます。
観客は呆れ、そして感動するという寸法です。
そうか、金回りが良くなっても豪邸に住む必要はないんだな、と。
ここまででお分かりのように、棘とはいえ、チクと痛いくらいの棘です。
致命傷にならない程度の棘が無数に刺さり、皮膚をさすっている間に映画は終わります。
なんとなくチャーリーの家族のブレない団結に心暖かくなった気分で映画館を後にできます。
でも、棘はすべて皮膚がはじき出してくれるとは限りません。
中には体内に入り込み、血管を遊泳し、やがて心の臓に達する可能性もありますから、
私たちのリアルな生活では些細な棘にも御用心召されよ。
『チャーリーとチョコレート工場』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:2005年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:ティム・バートン
原作:ロアルド・ダール
音楽:ダニー・エルフマン
俳優:ジョニー・デップ(ウィリー・ウォンカ) フレディ・ハイモア(チャーリー・バケット)
ディープ・ロイ(ウンパ・ルンパ) ヘレナ・ボナム・カーター デヴィッド・ケリー
クリストファー・リー ミッシー・パイル
ジェームズ・フォックス アダム・ゴドリー フランツィスカ・トローグナー アナソフィア・ロブ
ジュリア・ウィンター ジョーダン・フライ フィリップ・ウィーグラッツ リズ・スミス
アイリーン・エッセル デヴィッド・モリス
製作国:アメリカ、イギリス
allcinemaの情報ページはこちら

Warner Bros./Photofest/MediaVast Japan
コメント
ティム・バートン監督の素晴らしい想像力で描かれた本作のカラフルな映像が私を魅了し、
初見では物語が把握できなかったほどです。
(難しい映画じゃないのにね)
ことしようやく見直しが叶い、物語がそっくり理解できました。
ただ以下の文では痒いところに手が届かないような書き方になっています。
初見の際の私の戸惑いを少し滲ませて書いておりますから。
2005年にこの映画を見たとき、ロアルド・ダール(原作者)という作家を思い出しました。
1960年代後半に、世界の流行から少し遅れて日本でも「奇妙な味」ブームが起こりました。
SFとも怪奇ともつかぬ不思議で後味の割り切れない小説群のことです。
(きっかけは少年マガジンだったかの漫画でしたけれど)
私はブームに乗って、サキ、マルセル・エーメ、ジョン・コリアなど読みふけったのですが、ロアルド・ダールの作品も1、2冊は読んだように思います。ただ、本作の原作『チョコレート工場の秘密』は読んでいません。
改めてダールの諸作品の書評など読んでみますと、なかなかにブラックな風刺が散りばめられている様子。
宮崎駿さんがダールを好きだと初めて知りました。
そういう「奇妙な味」作家の一人が書いたブラックな小説を、ティム・バートンさんという辛辣であることがアイデンティティーな監督が映画化したわけですから、これはもう棘(トゲ)だらけのファンタジーになるのも当然と言えましょう。
棘については批評欄に書きます。
とはいえ、本作の結末はわかりやすいハッピーエンド。
このわかりやすさが少し不満です。「奇妙な味」ファンとしては。
高校教員時代にこの映画が好きだという高校生に数多く出会ったことはいまでも不思議です。
こんな悪意に満ちた映画を?
もちろん中にジョニー・デップさんファンもいたでしょうが、なんだかみんな瞳をキラーんとさせて本作が好きだと言っていた様子から、ディズニーに飽き足りないファンタジーファンを惹きつけたのかな、と思ったりしたものです。
でも残念ながら理由は聞き漏らしました。
本作の棘だらけの痛さは彼女たちにとってスパイスだったのでしょうか。
それとも、そういう痛みがわかる世代だったのでしょうか。
チャーリーはウィリー・ウォンカの秘密のチョコレート工場の見学ができるゴールドチケットが欲しくて前倒しして食べたチョコレートにチケットは入っていませんでした。
(↑息継ぎなしで読んでね)
祖父はなけなしのへそくりをチャーリーに渡してチョコレートを買っておいでというのですが、そこにもチケットはありません。
落胆していたチャーリーは、積もった雪の中に一枚の紙幣が落ちているのを見つけました。
チョコレートを買うと、見事に金色に輝くチケットが入っていました。
チャーリーが拾った金でチョコレートを買うことへのためらいのなさに驚きます。
ジョニー・デップさんの偏屈な人物造形に拍手を惜しみません。
また、ヘレナ・ボナム・カーターさんのいつものリアル感溢れる脇役ぶりに賛辞を。でも、
ここでは165役をこなしたディープ・ロイ(ウンパ・ルンパ役)さんに敬意を表し、下記の動画を共有します。
「Oompa Loompa Song」:Tim KnightさんのYoutube。
批評:チョコレートのトゲ
『アリス・イン・ワンダーランド』でも書いたように、
バートン監督の映画にはサボテンのように棘(トゲ)が植えられています。
毒や悪意や辛辣な風刺などという形で作品が飾られています。
本作にも各種の棘があり、たとえば子供に対する憎悪がその代表例なのですが、
中でも私が最も痛く感じた棘は、産業社会の酷薄さという棘でした。
主人公チャーリー少年の住むボロ家は、もちろん何より大切な家族、の象徴なのですが、
そのボロぶりは凄まじく、家屋は傾き、雪が降るようなこの町なのに天井に大穴が空いています。
その家には老人(祖父母)が4人住んでいて、その世話に明け暮れる母と、歯磨き粉工場に勤める父、そしてチャーリー、の計7人が暮らしています。
毎晩の夕食はキャベツスープだけです。
チャーリーは年に一度の誕生日にチョコレートが食べられるだけ。(それすらみんなに分けます)
歯磨き工場の給料はとても安いようです。
チャーリーにへそくりを渡した祖父は、かつてチョコレート工場で働いていましたが、産業スパイに怒った経営者ウォンカは従業員全員に解雇を申し渡しました。
祖父はもちろん、解雇された従業員の怒りの声は描かれません。
歯磨き工場へのロボット導入で父はクビになりますが、なぜかそのロボットの修理技術者として再雇用され、家庭での食事情は飛躍的に好転します。キャベツスープが肉の塊になるのです。ロボット導入で解雇された従業員はチャーリーの父親だけではないでしょう。他の元従業員たちは再雇用されたのでしょうか、とても気になります。
その他様々な場面で、「貧乏人」と「金持ち」「超金持ち」との大きな差が描かれます。
チャーリーはウォンカからの「超金持ち」になるだろう提案を拒み、貧しくても家族と一緒に暮らすことを選びます。
貧乏人の私としては救いがあります。
ですが、結局エンディングでチャーリーはウォンカの提案を呑み、チョコレート工場の跡取りとなりました。
とはいえ、家族とともに工場内で住み、その住まいはこれまで通りのボロ家。
わざわざ移設したのですね。
狭いスペースで家族みんなが仲良く暮らす家。
その家ではウォンカまで一緒に食事をとり、チャーリーの母親のマナー指導を受けます。
観客は呆れ、そして感動するという寸法です。
そうか、金回りが良くなっても豪邸に住む必要はないんだな、と。
ここまででお分かりのように、棘とはいえ、チクと痛いくらいの棘です。
致命傷にならない程度の棘が無数に刺さり、皮膚をさすっている間に映画は終わります。
なんとなくチャーリーの家族のブレない団結に心暖かくなった気分で映画館を後にできます。
でも、棘はすべて皮膚がはじき出してくれるとは限りません。
中には体内に入り込み、血管を遊泳し、やがて心の臓に達する可能性もありますから、
私たちのリアルな生活では些細な棘にも御用心召されよ。
2018年10月14日
『007/ゴールドフィンガー』
データ
『007/ゴールドフィンガー』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:1964年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後何度かビデオ等で、また2018年BS/CSで視聴。
監督:ガイ・ハミルトン
原作:イアン・フレミング
音楽:ジョン・バリー
主題歌:シャーリー・バッシー
俳優:ショーン・コネリー(ジェームズ・ボンド) ゲルト・フレーベ(ゴールドフィンガー)
ハロルド坂田(オッドジョブ) オナー・ブラックマン( プッシー・ガロア:空中サーカス団長)
シャーリー・イートン (ジル・マスターソン:金粉を塗られて殺害される姉)
タニア・マレット(ティリー・マスターソン:オッドジョブの帽子で殺害される妹)
マイケル・メリンジャー バート・クウォーク セク・リンダー
バーナード・リー(M) デスモンド・リュウェリン(Q) ロイス・マクスウェル(マネーペニー)
製作国:イギリス
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
合衆国保有の金塊を放射能汚染させて自ら所有する莫大な金の値上がりを図る資本家ゴールドフィンガー。
その企てを阻止しようとするジェームズ・ボンドら米英の情報部。
もちろん美女がたくさん登場。ボンドのユーモアや博識も健在。
ボンドカーはアストンマーチンに変更されました。
映画化三作目。ここから純娯楽色が強まります。
原作者イアン・フレミングさんの007シリーズ著作は全て、しかもたぶん刊行順に読んでいます。
『カジノ・ロワイヤルCasino Royale』、『死ぬのは奴らだ Live and Let Die』 、『ムーンレイカー Moonraker』、『ダイヤモンドは永遠に Diamonds Are Forever 』『ロシアから愛をこめて From Russia, With Love』 、『ドクター・ノオ Doctor No』、と続いて第七作がこの映画の原作となった『ゴールドフィンガー Goldfinger 』でした。
中学生〜高一の頃にまとめて読んだのですが、『ゴールドフィンガー』あたりから飽きてきました。もともとリアルなスパイ小説ではないのですが、少し荒唐無稽がすぎる、というか、フレミングさん自身の(このシリーズの)限界だったのでしょう。
一方、ショーン・コネリーさん主演の007シリーズの映画(全六作)も全て観ています。
皮肉なことに、小説では飽きてきたきっかけとなった『ゴールドフィンガー』でしたが、映画では一番好きな作品になりました。
(小説刊行の順に映画化されたわけではありません)
フィオートノックスを放射能汚染する、
そしてそのために毒薬を空中散布する、
などという無理筋の設定にはなっていますが、そもそも殺人許可証を持つなどという設定そのものが絵空事なのですから、構わないのではないでしょうか。
ショーン・コネリーさんが前二作よりも渋みを増し(by 妻)、次々と変わる展開が飽きさせません。
それに何よりもシャーリー・バッシーさんのあの歌唱。
中学生の頃、深夜ラジオで毎日毎日流れてきたために、夜の匂いとともに私の人生の大事な記憶になっています。
James ReedさんのYoutubeから
そして忘れてはならない日系米国人レスラー、ハロルド坂田さんのあの笑顔と帽子。
坂田さんはかつてのロンドンオリンピックで銀メダルを獲ったウェイトリフティングの選手だったのです。
批評
学校だったのです、007シリーズは。
世界の美しい景色や色々な民族の文化、
自動車や航空機など新しいマシン、
英国人の立ち居振る舞い、
中でもユーモア。
本作にも英国流ヒューモアはたくさん登場しますが、
縛り付けられたボンドがレーザーで股から真っ二つにされようかというとき、
「デモンストレーションをありがとう」と強がるような、
あのどこかトボけた上から目線のユーモアは、とても勉強になりました。
今の若い世代がいきなりこの作品を観たとすると、
私のこの高評価には驚かれると思いますが、
文化は積み重ねられていくものですので、
そこを理解していただければ嬉しいです。
『007/ゴールドフィンガー』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:1964年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後何度かビデオ等で、また2018年BS/CSで視聴。
監督:ガイ・ハミルトン
原作:イアン・フレミング
音楽:ジョン・バリー
主題歌:シャーリー・バッシー
俳優:ショーン・コネリー(ジェームズ・ボンド) ゲルト・フレーベ(ゴールドフィンガー)
ハロルド坂田(オッドジョブ) オナー・ブラックマン( プッシー・ガロア:空中サーカス団長)
シャーリー・イートン (ジル・マスターソン:金粉を塗られて殺害される姉)
タニア・マレット(ティリー・マスターソン:オッドジョブの帽子で殺害される妹)
マイケル・メリンジャー バート・クウォーク セク・リンダー
バーナード・リー(M) デスモンド・リュウェリン(Q) ロイス・マクスウェル(マネーペニー)
製作国:イギリス
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
合衆国保有の金塊を放射能汚染させて自ら所有する莫大な金の値上がりを図る資本家ゴールドフィンガー。
その企てを阻止しようとするジェームズ・ボンドら米英の情報部。
もちろん美女がたくさん登場。ボンドのユーモアや博識も健在。
ボンドカーはアストンマーチンに変更されました。
映画化三作目。ここから純娯楽色が強まります。
原作者イアン・フレミングさんの007シリーズ著作は全て、しかもたぶん刊行順に読んでいます。
『カジノ・ロワイヤルCasino Royale』、『死ぬのは奴らだ Live and Let Die』 、『ムーンレイカー Moonraker』、『ダイヤモンドは永遠に Diamonds Are Forever 』『ロシアから愛をこめて From Russia, With Love』 、『ドクター・ノオ Doctor No』、と続いて第七作がこの映画の原作となった『ゴールドフィンガー Goldfinger 』でした。
中学生〜高一の頃にまとめて読んだのですが、『ゴールドフィンガー』あたりから飽きてきました。もともとリアルなスパイ小説ではないのですが、少し荒唐無稽がすぎる、というか、フレミングさん自身の(このシリーズの)限界だったのでしょう。
一方、ショーン・コネリーさん主演の007シリーズの映画(全六作)も全て観ています。
皮肉なことに、小説では飽きてきたきっかけとなった『ゴールドフィンガー』でしたが、映画では一番好きな作品になりました。
(小説刊行の順に映画化されたわけではありません)
フィオートノックスを放射能汚染する、
そしてそのために毒薬を空中散布する、
などという無理筋の設定にはなっていますが、そもそも殺人許可証を持つなどという設定そのものが絵空事なのですから、構わないのではないでしょうか。
ショーン・コネリーさんが前二作よりも渋みを増し(by 妻)、次々と変わる展開が飽きさせません。
それに何よりもシャーリー・バッシーさんのあの歌唱。
中学生の頃、深夜ラジオで毎日毎日流れてきたために、夜の匂いとともに私の人生の大事な記憶になっています。
James ReedさんのYoutubeから
そして忘れてはならない日系米国人レスラー、ハロルド坂田さんのあの笑顔と帽子。
坂田さんはかつてのロンドンオリンピックで銀メダルを獲ったウェイトリフティングの選手だったのです。
批評
学校だったのです、007シリーズは。
世界の美しい景色や色々な民族の文化、
自動車や航空機など新しいマシン、
英国人の立ち居振る舞い、
中でもユーモア。
本作にも英国流ヒューモアはたくさん登場しますが、
縛り付けられたボンドがレーザーで股から真っ二つにされようかというとき、
「デモンストレーションをありがとう」と強がるような、
あのどこかトボけた上から目線のユーモアは、とても勉強になりました。
今の若い世代がいきなりこの作品を観たとすると、
私のこの高評価には驚かれると思いますが、
文化は積み重ねられていくものですので、
そこを理解していただければ嬉しいです。
2018年10月12日
『パラサイト・イヴ』
データ
『パラサイト・イヴ』
評価:☆☆☆・・・・・・・
年度:1997年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:落合正幸
原作:瀬名秀明
音楽:久石譲
俳優:三上博史 葉月里緒菜 別所哲也 中嶋朋子 稲垣吾郎 大村彩子 萬田久子
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

Atticus SatoさんのYoutubeより
コメント
原作が好きでしたので、遅ればせながら映画を見たのです。
原作体験をきっかけに、文系の私がミトコンドリアに関する翻訳科学本(入門書ですが)を数冊読みました。
体内のミトコンドリアとの対話を試みたりする私になりました。
映画にはがっかりしました。
演出が薄っぺら。
脇役が演技できてません。三上博史さんが大げさな怪演をするわけですから、別所哲也さんや萬田久子さんのポジションには堅実な芝居ができる人を配すべきでした。(中嶋朋子さんは良かった。)
また観客は、めでたしめでたしのラブストーリーを見たかったわけではないでしょう。
生々しい臓器を見せてホラー味、とは安直です。
全体に美しい映像ですが、それ以外の見どころは三つに絞られます。
1)葉月里緒奈さんの雰囲気満点の美しさ。適役(by 妻)です。彼女のPVでもあります、本作は。アップだらけ。
2)三上博史さんが妻の肝臓を培養する場面の目つき。
ここはホラー。
3)中嶋朋子さんが学会で発表するときの目つき。
ここもホラー。
以上です。
『パラサイト・イヴ』
評価:☆☆☆・・・・・・・
年度:1997年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:落合正幸
原作:瀬名秀明
音楽:久石譲
俳優:三上博史 葉月里緒菜 別所哲也 中嶋朋子 稲垣吾郎 大村彩子 萬田久子
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

Atticus SatoさんのYoutubeより
コメント
原作が好きでしたので、遅ればせながら映画を見たのです。
原作体験をきっかけに、文系の私がミトコンドリアに関する翻訳科学本(入門書ですが)を数冊読みました。
体内のミトコンドリアとの対話を試みたりする私になりました。
映画にはがっかりしました。
演出が薄っぺら。
脇役が演技できてません。三上博史さんが大げさな怪演をするわけですから、別所哲也さんや萬田久子さんのポジションには堅実な芝居ができる人を配すべきでした。(中嶋朋子さんは良かった。)
また観客は、めでたしめでたしのラブストーリーを見たかったわけではないでしょう。
生々しい臓器を見せてホラー味、とは安直です。
全体に美しい映像ですが、それ以外の見どころは三つに絞られます。
1)葉月里緒奈さんの雰囲気満点の美しさ。適役(by 妻)です。彼女のPVでもあります、本作は。アップだらけ。
2)三上博史さんが妻の肝臓を培養する場面の目つき。
ここはホラー。
3)中嶋朋子さんが学会で発表するときの目つき。
ここもホラー。
以上です。
2018年10月12日
『怪物はささやく』
データ
『怪物はささやく』A MONSTER CALLS
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:J・A・バヨナ
原作:シヴォーン・ダウド、パトリック・ネス
音楽:フェルナンド・ベラスケス
俳優:ルイス・マクドゥーガル(コナー) シガーニー・ウィーヴァー(祖母)
フェリシティ・ジョーンズ (母) トビー・ケベル(父) ジェニファー・リム
ジェラルディン・チャップリン(教師) リーアム・ニーソン(怪物の声)
製作国:アメリカ、スペイン
allcinemaの情報ページはこちら

予告編より
コメント
美しくて深い映像と、真摯な物語。
観ている間は久しぶりに傑作と出会った快感と共に在りました。
涙は出ませんが、心が潤みました。
ただ、見終わって二、三日たつと一つの欠落感が拭えません。
そのあたりについて、簡単なあらすじと共に書いてみたいと思います。
その前に、シガーニー・ウィーヴァー(祖母)さんの渋い演技、フェリシティ・ジョーンズ(母)さんの切実な演技がとても良かったと言っておきたいと思いますし、
それ以上にコナー役のルイス・マクドゥーガル少年の様々な表情に賞賛の拍手を贈りたいと思います。
批評
スペイン?に住む小柄な少年コナーが主人公です。
絵が好きで頭も良さそうです。
学校ではガタイの大きな同級生にイジメられています。
両親は離婚し、大好きな母はガン?治療中ですが、治療の方法も尽きてきたようす。
しかしコナーと母は、明日こそは治る、次の治療は効果があるはず、と声を掛け合っています。
コナーが家事を頑張っています。
祖母が来ます。祖母は娘が治療に専念できるよう、またコナーが家事をしなくていいように、引き取ると告げます。
コナーは厳格で小言の多い祖母が嫌いなので拒みます。
(あれ?コナーはお母さんと離れたくないから断るわけではないの?)
アメリカLAに住み、第二の世帯を持っている父が来ます。
父がLAに引き取ってくれるのかと期待したコナーですが、父にその気はありません。
(あれ?コナーはお母さんと離れてもいいの?)
そのあとコナーは荒れます。祖母の家を破壊し尽くします。
コナーは毎晩悪夢を見ます。崩れた崖から落ちそうな母の手を必死に引っ張り上げようとするのですが、ついにその手は離れ、母は落下して消えてしまいます。
そのつどコナーは目が覚めます。
(この悪夢は繰り返し紹介されますので、重要であることがわかります。)
そんなある夜、「コナー」とささやく声が聞こえます。怪物です。丘の上の樹齢千年をゆうに超えそうなイチイの木の精のようです。
(おそらくセイヨウイチイの木Yew。実は食用になるがタネはイチイと同様に有毒。なお、この怪物が<ささやく>のはこのとき限り。あとはだいたい大きな声で話すから、邦題はピンと来ない。だいたい、原題のcallはささやくではなく呼ぶ意ですよね。)
怪物は、何度も現れて三つの物語を語ります。
一つ目は、善と悪とは画然としないという話です。人間は善人でも悪人でもなく、たいてい善と悪の間に生きているというのです。
二つ目は、信念は大切だという話です。嫌なやつでも信念を貫けば立派だし、いい人でも信念を捨てたら・・というのです。
この二つは、実に美しいアニメーションで描かれます。楽しい話ではありませんが、うっとりします。
ところが三つ目の物語が問題です。ここはアニメーションがなく、これまでのようにイチイの木が見て来た昔話でもありません。
コナーがいまぶち当たっている壁を突き破る現実の映像で語られます。
具体的には、いじめっ子が和解を求め、「きみは自分が殴られたかったんだな。もうしない。君は透明人間だから。」と言ったことに逆上し、逆にいじめっ子をぶちのめし、入院させるほどの怪我を負わせます。
これはたぶん反則です。
私は原作を読んでいませんが、そこにはもう一つ昔話があったのではないでしょうか。
その話をアニメーションで見たかったなと思いました。
このことがこの作品に抱いた唯一の不満ですし、コメント欄に書いた欠落です。
もう一つの昔話については私の誤解かもしれませんが、なんだか上映時間の制限のためにカットされてしまったような唐突感があったのです。
さて、本作はこのあと大詰めを迎えます。
怪物の正体は最後の最後に判明します。
そのあたりまで書いてしまうことはなかろうと思い、そろそろ筆を置きます。
ただ一つ、映画に慣れていない方は見落とすかもしれないポイントを一つだけ紹介しておきます。
上述のように、コナーは二度荒れます。キレます。
しかし二度とも誰からも罰は下されませんでした。
「罰は無し?」と尋ねるコナーの顔はホッとした表情には見えないはずです。
そしていじめっ子のあのセリフ。。。。
コナーはなぜ荒れるのでしょうか。
その答えはきちんと説明されますが、その答えの伏線がこれだったのか、と
気がつくと満足感が得られるはずです。
難しい図形の問題が解けたときのように。
こういうきちんと作られた映画は、きちんと考えて観た方が楽しいですよね。
『怪物はささやく』A MONSTER CALLS
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:J・A・バヨナ
原作:シヴォーン・ダウド、パトリック・ネス
音楽:フェルナンド・ベラスケス
俳優:ルイス・マクドゥーガル(コナー) シガーニー・ウィーヴァー(祖母)
フェリシティ・ジョーンズ (母) トビー・ケベル(父) ジェニファー・リム
ジェラルディン・チャップリン(教師) リーアム・ニーソン(怪物の声)
製作国:アメリカ、スペイン
allcinemaの情報ページはこちら

予告編より
コメント
美しくて深い映像と、真摯な物語。
観ている間は久しぶりに傑作と出会った快感と共に在りました。
涙は出ませんが、心が潤みました。
ただ、見終わって二、三日たつと一つの欠落感が拭えません。
そのあたりについて、簡単なあらすじと共に書いてみたいと思います。
その前に、シガーニー・ウィーヴァー(祖母)さんの渋い演技、フェリシティ・ジョーンズ(母)さんの切実な演技がとても良かったと言っておきたいと思いますし、
それ以上にコナー役のルイス・マクドゥーガル少年の様々な表情に賞賛の拍手を贈りたいと思います。
批評
スペイン?に住む小柄な少年コナーが主人公です。
絵が好きで頭も良さそうです。
学校ではガタイの大きな同級生にイジメられています。
両親は離婚し、大好きな母はガン?治療中ですが、治療の方法も尽きてきたようす。
しかしコナーと母は、明日こそは治る、次の治療は効果があるはず、と声を掛け合っています。
コナーが家事を頑張っています。
祖母が来ます。祖母は娘が治療に専念できるよう、またコナーが家事をしなくていいように、引き取ると告げます。
コナーは厳格で小言の多い祖母が嫌いなので拒みます。
(あれ?コナーはお母さんと離れたくないから断るわけではないの?)
アメリカLAに住み、第二の世帯を持っている父が来ます。
父がLAに引き取ってくれるのかと期待したコナーですが、父にその気はありません。
(あれ?コナーはお母さんと離れてもいいの?)
そのあとコナーは荒れます。祖母の家を破壊し尽くします。
コナーは毎晩悪夢を見ます。崩れた崖から落ちそうな母の手を必死に引っ張り上げようとするのですが、ついにその手は離れ、母は落下して消えてしまいます。
そのつどコナーは目が覚めます。
(この悪夢は繰り返し紹介されますので、重要であることがわかります。)
そんなある夜、「コナー」とささやく声が聞こえます。怪物です。丘の上の樹齢千年をゆうに超えそうなイチイの木の精のようです。
(おそらくセイヨウイチイの木Yew。実は食用になるがタネはイチイと同様に有毒。なお、この怪物が<ささやく>のはこのとき限り。あとはだいたい大きな声で話すから、邦題はピンと来ない。だいたい、原題のcallはささやくではなく呼ぶ意ですよね。)
怪物は、何度も現れて三つの物語を語ります。
一つ目は、善と悪とは画然としないという話です。人間は善人でも悪人でもなく、たいてい善と悪の間に生きているというのです。
二つ目は、信念は大切だという話です。嫌なやつでも信念を貫けば立派だし、いい人でも信念を捨てたら・・というのです。
この二つは、実に美しいアニメーションで描かれます。楽しい話ではありませんが、うっとりします。
ところが三つ目の物語が問題です。ここはアニメーションがなく、これまでのようにイチイの木が見て来た昔話でもありません。
コナーがいまぶち当たっている壁を突き破る現実の映像で語られます。
具体的には、いじめっ子が和解を求め、「きみは自分が殴られたかったんだな。もうしない。君は透明人間だから。」と言ったことに逆上し、逆にいじめっ子をぶちのめし、入院させるほどの怪我を負わせます。
これはたぶん反則です。
私は原作を読んでいませんが、そこにはもう一つ昔話があったのではないでしょうか。
その話をアニメーションで見たかったなと思いました。
このことがこの作品に抱いた唯一の不満ですし、コメント欄に書いた欠落です。
もう一つの昔話については私の誤解かもしれませんが、なんだか上映時間の制限のためにカットされてしまったような唐突感があったのです。
さて、本作はこのあと大詰めを迎えます。
怪物の正体は最後の最後に判明します。
そのあたりまで書いてしまうことはなかろうと思い、そろそろ筆を置きます。
ただ一つ、映画に慣れていない方は見落とすかもしれないポイントを一つだけ紹介しておきます。
上述のように、コナーは二度荒れます。キレます。
しかし二度とも誰からも罰は下されませんでした。
「罰は無し?」と尋ねるコナーの顔はホッとした表情には見えないはずです。
そしていじめっ子のあのセリフ。。。。
コナーはなぜ荒れるのでしょうか。
その答えはきちんと説明されますが、その答えの伏線がこれだったのか、と
気がつくと満足感が得られるはずです。
難しい図形の問題が解けたときのように。
こういうきちんと作られた映画は、きちんと考えて観た方が楽しいですよね。
2018年10月10日
『デューン 砂の惑星』
データ
『デューン 砂の惑星』DUNE
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:1985年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:デヴィッド・リンチ
原作:フランク・ハーバート
音楽:ブライアン・イーノ、TOTO
俳優:カイル・マクラクラン ホセ・ファーラー ポール・スミス フランチェスカ・アニス スティング
ショーン・ヤング ブラッド・ドゥーリフ ジャックナンス マックス・フォン・シドー
シルヴァーナ・マンガーノ
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

Universal Pictures / Photofest / ゲッティ イメージズ
コメント
1985年、、、実生活がかなり忙しすぎる頃の封切りでした。
気にはなっていたのですがスクリーンで見ることは叶わず、結局2018年になってようやくTV画面で。
自業自得とはいえ、これはかなり残念なことでした。
なにせ、少年のようなカイル・マクラクランさんがクーパー(『ツインピークス』)に見えてしまうのですからやんぬるかな。
リアルタイムで観ていれば驚きに満ちていて、あの『スター・ウォーズ』に(私の中で)肩を並べていたに違いありません。
とはいえ、それは言っても仕方がないこと。
ようやく鑑賞できたことを喜びましょう。
個別俳優的にはカイル・マクラクランさんが見られて満足です。
それに加えて『ブレードランナー』のレイチェル、あのショーン・ヤングさんの登場が嬉しい。
シルヴァーナ・マンガーノさんまで出演していて、もう天に昇ります、は大げさですが。
俳優たちは様式的な、ステレオタイプな演技をしています。
平坦な表情、少ない表現動作、大げさなアクション。
あのホセ・ファーラーさん、マックス・フォン・シドーさんが木偶の坊みたい。
(スティングさんの演技を標準にしているのか、と一瞬疑ってしまいました。
冗談です、スティングさんごめんなさい。悪役として浮遊感のある、いい雰囲気出してましたよ。)
それもこれも、デューンという惑星で繰り広げられるオデッセイを強調するためでしょう。
惑星の救世主が、悪人たちを蹴散らしてついに君臨する勧善懲悪物語。
巨大な虫が守る?産み出す?スパイスの謎は詳しく語られることがありません。
とても知りたいと思いました。
総じて、膨大な情報量を、わずかな時間に詰め込んだ映画でした。
けれど、少しだけ自分を1985年に戻す努力をして観てみると、
壮大な物語と奔放なイマジネーションに心踊るのです。
特に虫です。虫には取り憑かれます。
リメイク話があるようですが、CGなど使いすぎて端麗・端正な映像にならないよう願いたいと思います。
どこか野暮ったい粒子の荒い印象のあるところが本作の魅力だと思いますから。
この映画が示したイマジネーションの数々は、どれもこれも既視感に満ちています。
ということは、以後の多くのSF映画がオマージュしたということになります。
遅れて観ると、そういう楽しみはありますね。
『デューン 砂の惑星』DUNE
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:1985年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:デヴィッド・リンチ
原作:フランク・ハーバート
音楽:ブライアン・イーノ、TOTO
俳優:カイル・マクラクラン ホセ・ファーラー ポール・スミス フランチェスカ・アニス スティング
ショーン・ヤング ブラッド・ドゥーリフ ジャックナンス マックス・フォン・シドー
シルヴァーナ・マンガーノ
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

Universal Pictures / Photofest / ゲッティ イメージズ
コメント
1985年、、、実生活がかなり忙しすぎる頃の封切りでした。
気にはなっていたのですがスクリーンで見ることは叶わず、結局2018年になってようやくTV画面で。
自業自得とはいえ、これはかなり残念なことでした。
なにせ、少年のようなカイル・マクラクランさんがクーパー(『ツインピークス』)に見えてしまうのですからやんぬるかな。
リアルタイムで観ていれば驚きに満ちていて、あの『スター・ウォーズ』に(私の中で)肩を並べていたに違いありません。
とはいえ、それは言っても仕方がないこと。
ようやく鑑賞できたことを喜びましょう。
個別俳優的にはカイル・マクラクランさんが見られて満足です。
それに加えて『ブレードランナー』のレイチェル、あのショーン・ヤングさんの登場が嬉しい。
シルヴァーナ・マンガーノさんまで出演していて、もう天に昇ります、は大げさですが。
俳優たちは様式的な、ステレオタイプな演技をしています。
平坦な表情、少ない表現動作、大げさなアクション。
あのホセ・ファーラーさん、マックス・フォン・シドーさんが木偶の坊みたい。
(スティングさんの演技を標準にしているのか、と一瞬疑ってしまいました。
冗談です、スティングさんごめんなさい。悪役として浮遊感のある、いい雰囲気出してましたよ。)
それもこれも、デューンという惑星で繰り広げられるオデッセイを強調するためでしょう。
惑星の救世主が、悪人たちを蹴散らしてついに君臨する勧善懲悪物語。
巨大な虫が守る?産み出す?スパイスの謎は詳しく語られることがありません。
とても知りたいと思いました。
総じて、膨大な情報量を、わずかな時間に詰め込んだ映画でした。
けれど、少しだけ自分を1985年に戻す努力をして観てみると、
壮大な物語と奔放なイマジネーションに心踊るのです。
特に虫です。虫には取り憑かれます。
リメイク話があるようですが、CGなど使いすぎて端麗・端正な映像にならないよう願いたいと思います。
どこか野暮ったい粒子の荒い印象のあるところが本作の魅力だと思いますから。
この映画が示したイマジネーションの数々は、どれもこれも既視感に満ちています。
ということは、以後の多くのSF映画がオマージュしたということになります。
遅れて観ると、そういう楽しみはありますね。
2018年10月08日
『オデッサ・ファイル』
データ
『オデッサ・ファイル』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:1975年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:ロナルド・ニーム
原作:フレデリック・フォーサイス
俳優:ジョン・ヴォイト(ピーター・ミラー) マクシミリアン・シェル(ロシュマン) マリア・シェル
マリー・タム ノエル・ウィルマン デレク・ジャコビ ピーター・ジェフリー
製作国:イギリス映画、ドイツ映画(当時は西ドイツ)
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
原作者フレデリック・フォーサイスはイギリスの作家で、1970年代にベストセラーを連発しました。
今回彼の著作リストを眺めると、「ジャッカルの日」「オデッサ・ファイル」「戦争の犬たち」など7作品を読んでいました。
ノンフィクションルポである「ビアフラ物語 飢えと血と死の淵から」を除き、テンポの良いミステリーサスペンスで退屈させません。
世界の現実もよく取り入れられています。
本作公開の一年前に映画化・公開された『ジャッカルの日』(フレッド・ジンネマン監督)では、原作に負けない緊張感と面白さに感じ入りましたので、柳の下の泥鰌を狙って映画館に足を運んだのでした。
その結果は、う〜ん、少々大味だなあ、と思いました。
原作で、主人公ピーターがナチスSSの生き残り組織オデッサ(Organisation Der Ehemaligen SS-Angehorigen)への潜入を試みる際のあの胃袋がキューっとするような緊迫感は感じられないなあ、と。
1970年代の私は、ナチズム批判の勉強を少しばかりしていた頃ですので、少し映画が甘く感じられたのです。
今回見直して見ると、やはりその当時の印象は拭えませんでした。
けれど、その後のドイツにおけるネオナチなど欧州の極右勢力の台頭や、ナチスを見習えとまで公言する日本の麻生太郎や日本会議の面々の言動を見聞きするにつけ、70年代は戦争の体験が残っていた分だけ、世界がまだリベラルだったのかな、と妙な感想を持ちました。
そういう意味では、現状はもはや本作のような娯楽映画にてファシズムを扱える時代ではなくなったのかもしれません。
ジョン・ヴォイトさん、(当時は)『真夜中のカーボーイ』以来の対面でしたが、意外に人間臭さのある好演でした。
マクシミリアン・シェルさんは、リガ収容所の元所長ロシュマン役。素晴らしい。
マリー・タムさん、ピーターの恋人役。いえエンドクレジットにはミラー夫人と書かれていました。演技力はともかく、とにかく可愛い。
というわけで、当時の世相も少し把握できます。
必見とは申しませんが、一度ご覧になってはいかがですか、の映画です。
オチもあります。
ただ、ヒトラーやナチスによるユダヤ人虐殺についての最低限の知識だけは持って観てください。
なお、(西)ドイツロケを徹底していますが、残念ながらセリフは全編英語です。

マリー・タムさん。出典不詳です。支障がありましたら連絡を。
『オデッサ・ファイル』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:1975年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:ロナルド・ニーム
原作:フレデリック・フォーサイス
俳優:ジョン・ヴォイト(ピーター・ミラー) マクシミリアン・シェル(ロシュマン) マリア・シェル
マリー・タム ノエル・ウィルマン デレク・ジャコビ ピーター・ジェフリー
製作国:イギリス映画、ドイツ映画(当時は西ドイツ)
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
原作者フレデリック・フォーサイスはイギリスの作家で、1970年代にベストセラーを連発しました。
今回彼の著作リストを眺めると、「ジャッカルの日」「オデッサ・ファイル」「戦争の犬たち」など7作品を読んでいました。
ノンフィクションルポである「ビアフラ物語 飢えと血と死の淵から」を除き、テンポの良いミステリーサスペンスで退屈させません。
世界の現実もよく取り入れられています。
本作公開の一年前に映画化・公開された『ジャッカルの日』(フレッド・ジンネマン監督)では、原作に負けない緊張感と面白さに感じ入りましたので、柳の下の泥鰌を狙って映画館に足を運んだのでした。
その結果は、う〜ん、少々大味だなあ、と思いました。
原作で、主人公ピーターがナチスSSの生き残り組織オデッサ(Organisation Der Ehemaligen SS-Angehorigen)への潜入を試みる際のあの胃袋がキューっとするような緊迫感は感じられないなあ、と。
1970年代の私は、ナチズム批判の勉強を少しばかりしていた頃ですので、少し映画が甘く感じられたのです。
今回見直して見ると、やはりその当時の印象は拭えませんでした。
けれど、その後のドイツにおけるネオナチなど欧州の極右勢力の台頭や、ナチスを見習えとまで公言する日本の麻生太郎や日本会議の面々の言動を見聞きするにつけ、70年代は戦争の体験が残っていた分だけ、世界がまだリベラルだったのかな、と妙な感想を持ちました。
そういう意味では、現状はもはや本作のような娯楽映画にてファシズムを扱える時代ではなくなったのかもしれません。
ジョン・ヴォイトさん、(当時は)『真夜中のカーボーイ』以来の対面でしたが、意外に人間臭さのある好演でした。
マクシミリアン・シェルさんは、リガ収容所の元所長ロシュマン役。素晴らしい。
マリー・タムさん、ピーターの恋人役。いえエンドクレジットにはミラー夫人と書かれていました。演技力はともかく、とにかく可愛い。
というわけで、当時の世相も少し把握できます。
必見とは申しませんが、一度ご覧になってはいかがですか、の映画です。
オチもあります。
ただ、ヒトラーやナチスによるユダヤ人虐殺についての最低限の知識だけは持って観てください。
なお、(西)ドイツロケを徹底していますが、残念ながらセリフは全編英語です。

マリー・タムさん。出典不詳です。支障がありましたら連絡を。
2018年10月06日
『ブラックホーク・ダウン』
データ
『ブラックホーク・ダウン』
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2002年公開
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:リドリー・スコット
原作:マーク・ボウデン
音楽:リサ・ジェラード、ハンス・ジマー
俳優:ジョシュ・ハートネット ユアン・マクレガー トム・サイズモア サム・シェパード エリック・バナ
ジェイソン・アイザックス ジョニー・ストロング ウィリアム・フィクトナー ロン・エルダード
ジェレミー・ピヴェン ヒュー・ダンシー ユエン・ブレムナー ガブリエル・カソーズ キム・コーツ
ジェリコ・イヴァネク グレン・モーシャワー トーマス・ハーディ ラザーク・アドティ
ブレンダン・セクストン三世 リチャード・タイソン ブライアン・ヴァン・ホルト
ニコライ・コスター・ワルドー スティーヴン・フォード オーランド・ブルーム トーマス・グイリー
エンリケ・ムルシアーノ クリス・ビーテム カーマイン・ジョヴィナッツォ ジョージ・ハリス
グレゴリー・スポーレダー ヨアン・グリフィズ チャーリー・ホフハイマー
製作国:
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
ブラックシー街区の位置。マイナスボタンでソマリア全体をご覧ください。
↑不調のようですので、モガディシュの位置がわかる地図だけ追加しておきます。

上の地図の場所、大変狭い地域で15時間にわたって繰り広げられたアメリカの失敗作戦の模様を、リドリー・スコット監督という手練れの手を得て、リアルにリアルに再現した映画です。
戦闘シーンはさすがに見応え十分。その意味では比類のない映画です。
米軍側を、主役に的を絞って描く手法は取っていません。
そこがリアルな戦闘の描写に思わせる仕掛けなのですが、そのことは、同格の登場人物があまりに多すぎる結果になります。
(若いオーランド・ブルームさんなどまだ何者でもない顔で登場。最初にヘリから落下します。)
映画全体を観れば良いのですが、さらにマニアックに探っていきたい場合は、
登場人物紹介をされているこのかたのブログがたいへん詳しくて役に立ちます。
中でジョシュ・ハートネットさんが主役扱いされています。確かに、彼とユアン・マクレガーさんは、他の若い登場人物に比べてすでに何者かになっているので、ヘルメット姿で顔は汚れきっていても区別しやすいのは流石です。
対してソマリア側は、1、2名を除いて名前もない状態の群衆として扱われています。
きわめて不公平な視点で作られた映画と言えるでしょう。
なぜこの映画が製作されたのか、「戦闘をリアルに描こうとした」以上のテーマはなさそうです。
総指揮官ギャリソン少将(サム・シェパードさん)が、血まみれの医療室で床の血を自ら拭うシーンが印象的でした。しかし簡単に綺麗に拭えるものではありません。スコット監督の気持ちは良くわかるシーンでしたが、これとて「後悔」「反省」以上のメッセージは伝わりません。私はやはりビル・クリントンを登場させるべきだったと思います。
「民主主義国家」における戦争の責任は最高権力者に帰すべきだと強く考えるからです。
批評:事件の内容と背景の概略説明
1993年10月、米軍がソマリアで起こしたソマリア要人誘拐作戦が失敗し、ソマリア人1000人(米軍発表数、民間人多数含む)、米軍兵士18人、国連PKOマレーシア兵士1名が犠牲になった事件をアメリカ映画会社が映画化した作品です。
この事件はメディアから「モガディシュの戦闘」と呼ばれるようになりました。モガディシュとは、ソマリアの首都またはそれに準ずる大都市である都市の名称です。モガディシュの中でも戦闘が主に繰り広げられた街区の名をとって、「ブラックシーの戦い」という呼び方もされます。
当時ソマリアには国連のPKO軍が派遣されていましたが、現地政権アイディード将軍派の民兵たちと交戦状態に入っていました。
そんな状況の中、国連としてではなく、米国独自の作戦(つまり、他のPKO派遣国には秘密で)として、アイディード将軍やその副官たちを誘拐し、この内戦を一挙に鎮めようととしたのです。
作戦を実行した部隊は、例えば非公式の特殊部隊デルタやレンジャー。とてもPKO(平和維持部隊)にふさわしい連中ではありません。つまり秘密作戦なのです。
当時の米国大統領は就任一年目のビル・クリントン。
大統領の命令により(←公ではありませんが、指揮系統として当然)、現地の責任者ガリソン少将が実行に当たりました。
クリントンは、世界の目がソマリアに集まっているこの時期を狙い、国際秩序におけるアメリカの主導権を高めよう(=自分の大統領としての評価を高めよう)としたわけです。
ところが、30分で簡単に済ませる予定のこの内密の誘拐作戦が、結局は15時間も必要となり、多くの犠牲者を出す失敗作戦となったのです。
米軍の兵力だけではモガディシュ市街地で孤立している米軍兵士を救助できなくなったため、ガリソン少将はパキスタン軍など他のPKO参加国に救援を求める始末となりました。当然内密の作戦ではなくなり、単なる非合法の失敗作戦という評価になります。
さらに、アメリカにとっての悪夢が始まります。
ここからは本作では描かれていないのですが、殺害された複数の米軍兵士が、裸にされて車に引きずられる映像が全世界に配信されたのです。
(この記事を書くにあたって、ネット上の各種動画にその映像が残されていないか調べたのですが、見つけられませんでした。)
アメリカは世界に恥を撒き散らされました。
ビル・クリントン大統領はこの屈辱に耐えられず、まもなくソマリアから撤兵しました。
(国連PKOもこれに続いて撤収)
アメリカが「世界の警察」から一歩退く契機となった戦闘でした。
参考:ソマリア内戦(wikipediaより抜粋。下線は筆者。)年表
1980年1月、人民議会はバーレを大統領に選出。
1982年 反バーレの反政府武装闘争が表面化。
1988年 ソマリア内戦勃発。
1991年 1月、暫定大統領にアリ・マフディ・ムハンマドが就任。
1991年5月、反政府勢力統一ソマリ会議(USC)が首都を制圧し、バーレを追放。しかしUSCの内部で、モハメッド・ファッラ・アイディード将軍派がアリ・マフディ暫定大統領派と対立。各勢力の内部抗争により南北は再び分裂。
1991年6月、北部の旧英国領地域が「ソマリランド共和国」として独立宣言。バーレ元大統領はナイジェリアのラゴスに亡命。
1991年 アイディード将軍派に首都を追われたアリ・マフディ暫定大統領が国際連合に対しPKO部隊派遣を要請。
1992年6月、アイディード将軍がいくつかの軍閥を統合してソマリ国民同盟(英語版)(SNA)が結成される。
1992年12月、国連PKO部隊、多国籍軍を派遣。
1993年5月、武力行使を認めた第2次国連ソマリア活動展開。アイディード将軍は国連に対して宣戦布告。
1993年10月、モガディシュの戦闘。
1993年 アメリカ合衆国、ソマリアからの撤兵。
1995年3月、国連PKO部隊撤退。
『ブラックホーク・ダウン』
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2002年公開
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:リドリー・スコット
原作:マーク・ボウデン
音楽:リサ・ジェラード、ハンス・ジマー
俳優:ジョシュ・ハートネット ユアン・マクレガー トム・サイズモア サム・シェパード エリック・バナ
ジェイソン・アイザックス ジョニー・ストロング ウィリアム・フィクトナー ロン・エルダード
ジェレミー・ピヴェン ヒュー・ダンシー ユエン・ブレムナー ガブリエル・カソーズ キム・コーツ
ジェリコ・イヴァネク グレン・モーシャワー トーマス・ハーディ ラザーク・アドティ
ブレンダン・セクストン三世 リチャード・タイソン ブライアン・ヴァン・ホルト
ニコライ・コスター・ワルドー スティーヴン・フォード オーランド・ブルーム トーマス・グイリー
エンリケ・ムルシアーノ クリス・ビーテム カーマイン・ジョヴィナッツォ ジョージ・ハリス
グレゴリー・スポーレダー ヨアン・グリフィズ チャーリー・ホフハイマー
製作国:
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
ブラックシー街区の位置。マイナスボタンでソマリア全体をご覧ください。
↑不調のようですので、モガディシュの位置がわかる地図だけ追加しておきます。

上の地図の場所、大変狭い地域で15時間にわたって繰り広げられたアメリカの失敗作戦の模様を、リドリー・スコット監督という手練れの手を得て、リアルにリアルに再現した映画です。
戦闘シーンはさすがに見応え十分。その意味では比類のない映画です。
米軍側を、主役に的を絞って描く手法は取っていません。
そこがリアルな戦闘の描写に思わせる仕掛けなのですが、そのことは、同格の登場人物があまりに多すぎる結果になります。
(若いオーランド・ブルームさんなどまだ何者でもない顔で登場。最初にヘリから落下します。)
映画全体を観れば良いのですが、さらにマニアックに探っていきたい場合は、
登場人物紹介をされているこのかたのブログがたいへん詳しくて役に立ちます。
中でジョシュ・ハートネットさんが主役扱いされています。確かに、彼とユアン・マクレガーさんは、他の若い登場人物に比べてすでに何者かになっているので、ヘルメット姿で顔は汚れきっていても区別しやすいのは流石です。
対してソマリア側は、1、2名を除いて名前もない状態の群衆として扱われています。
きわめて不公平な視点で作られた映画と言えるでしょう。
なぜこの映画が製作されたのか、「戦闘をリアルに描こうとした」以上のテーマはなさそうです。
総指揮官ギャリソン少将(サム・シェパードさん)が、血まみれの医療室で床の血を自ら拭うシーンが印象的でした。しかし簡単に綺麗に拭えるものではありません。スコット監督の気持ちは良くわかるシーンでしたが、これとて「後悔」「反省」以上のメッセージは伝わりません。私はやはりビル・クリントンを登場させるべきだったと思います。
「民主主義国家」における戦争の責任は最高権力者に帰すべきだと強く考えるからです。
批評:事件の内容と背景の概略説明
1993年10月、米軍がソマリアで起こしたソマリア要人誘拐作戦が失敗し、ソマリア人1000人(米軍発表数、民間人多数含む)、米軍兵士18人、国連PKOマレーシア兵士1名が犠牲になった事件をアメリカ映画会社が映画化した作品です。
この事件はメディアから「モガディシュの戦闘」と呼ばれるようになりました。モガディシュとは、ソマリアの首都またはそれに準ずる大都市である都市の名称です。モガディシュの中でも戦闘が主に繰り広げられた街区の名をとって、「ブラックシーの戦い」という呼び方もされます。
当時ソマリアには国連のPKO軍が派遣されていましたが、現地政権アイディード将軍派の民兵たちと交戦状態に入っていました。
そんな状況の中、国連としてではなく、米国独自の作戦(つまり、他のPKO派遣国には秘密で)として、アイディード将軍やその副官たちを誘拐し、この内戦を一挙に鎮めようととしたのです。
作戦を実行した部隊は、例えば非公式の特殊部隊デルタやレンジャー。とてもPKO(平和維持部隊)にふさわしい連中ではありません。つまり秘密作戦なのです。
当時の米国大統領は就任一年目のビル・クリントン。
大統領の命令により(←公ではありませんが、指揮系統として当然)、現地の責任者ガリソン少将が実行に当たりました。
クリントンは、世界の目がソマリアに集まっているこの時期を狙い、国際秩序におけるアメリカの主導権を高めよう(=自分の大統領としての評価を高めよう)としたわけです。
ところが、30分で簡単に済ませる予定のこの内密の誘拐作戦が、結局は15時間も必要となり、多くの犠牲者を出す失敗作戦となったのです。
米軍の兵力だけではモガディシュ市街地で孤立している米軍兵士を救助できなくなったため、ガリソン少将はパキスタン軍など他のPKO参加国に救援を求める始末となりました。当然内密の作戦ではなくなり、単なる非合法の失敗作戦という評価になります。
さらに、アメリカにとっての悪夢が始まります。
ここからは本作では描かれていないのですが、殺害された複数の米軍兵士が、裸にされて車に引きずられる映像が全世界に配信されたのです。
(この記事を書くにあたって、ネット上の各種動画にその映像が残されていないか調べたのですが、見つけられませんでした。)
アメリカは世界に恥を撒き散らされました。
ビル・クリントン大統領はこの屈辱に耐えられず、まもなくソマリアから撤兵しました。
(国連PKOもこれに続いて撤収)
アメリカが「世界の警察」から一歩退く契機となった戦闘でした。
参考:ソマリア内戦(wikipediaより抜粋。下線は筆者。)年表
1980年1月、人民議会はバーレを大統領に選出。
1982年 反バーレの反政府武装闘争が表面化。
1988年 ソマリア内戦勃発。
1991年 1月、暫定大統領にアリ・マフディ・ムハンマドが就任。
1991年5月、反政府勢力統一ソマリ会議(USC)が首都を制圧し、バーレを追放。しかしUSCの内部で、モハメッド・ファッラ・アイディード将軍派がアリ・マフディ暫定大統領派と対立。各勢力の内部抗争により南北は再び分裂。
1991年6月、北部の旧英国領地域が「ソマリランド共和国」として独立宣言。バーレ元大統領はナイジェリアのラゴスに亡命。
1991年 アイディード将軍派に首都を追われたアリ・マフディ暫定大統領が国際連合に対しPKO部隊派遣を要請。
1992年6月、アイディード将軍がいくつかの軍閥を統合してソマリ国民同盟(英語版)(SNA)が結成される。
1992年12月、国連PKO部隊、多国籍軍を派遣。
1993年5月、武力行使を認めた第2次国連ソマリア活動展開。アイディード将軍は国連に対して宣戦布告。
1993年10月、モガディシュの戦闘。
1993年 アメリカ合衆国、ソマリアからの撤兵。
1995年3月、国連PKO部隊撤退。
2018年10月06日
『籠釣瓶花街酔醒』
データ
シネマ歌舞伎『籠釣瓶花街酔醒』(かごつるべ さとのえいざめ)
評価:☆☆☆☆・・・・・・
年度:2012年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
俳優:中村勘三郎(佐野次郎左衛門) 坂東玉三郎(八ツ橋) 中村魁春 中村勘九郎 中村七之助
中村鶴松 片岡亀蔵 片岡市蔵 坂東彌十郎 片岡秀太郎 片岡我當 片岡仁左衛門
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちらただし、ほぼ情報はありません
本稿は在庫一掃私の鑑賞記録(ログ付け)のための記事の一環です。昔書いたままの文章、短か過ぎるコメントや古い記憶に基づく記述の場合もありますのでご了承ください。再見の機会があれば、補足修正する可能性が高いです。

コメント
松竹のシネマ歌舞伎鑑賞は『大江戸りびんぐでっど』に続いて二作目になります。
歌舞伎座の臨場感の高揚はほとんど味わうことができませんが、
高い席料を払っても観ることの出来ないアップ画像を観覧できますから、これはこれで魅力です。
もっとも、失礼ながらアップ映像を見たくない役者さんもおられますから、それはそれで残念です。
どっちやねん。
とびきりの歌舞伎ファンではない私は、役者への思い入れはありません。
やはり一つの演劇作品/映像作品として鑑賞することになります。
そういう目で眺めると、全体を通じて<きょとん>とした印象が残ります。
中村勘三郎扮する佐野次郎左衛門が、振られた数ヶ月後に再び吉原に現れて、
振った八ツ橋(坂東玉三郎)を妖刀籠釣瓶で斬り殺す、その心理的必然が納得いかないから。
無理して自分に言い聞かせるのです。「それだけ時間が経っても恨みを残すほどの恥だったんだよ」と。
むしろ妖刀の魔力をフィーチャーしてくれたほうがファンタジーとして腑に落ちるのですけれど。
歌舞伎の演目の中でも、ストーリーに無理のある作品じゃないのかなあ。
とはいえ、中村勘三郎さん、坂東玉三郎さんの色気とオーラは存分に楽しませていただきました。
そういう作品なんでしょうね、きっと。
あ、そうそう、中村勘九郎さん演じる次六がことのほかよろしゅうございました。
この作品の中ではややリアルすぎる演技だったのかもしれませんが、
私にはお父さんよりライトが当たっているように見えましたね。
シネマ歌舞伎『籠釣瓶花街酔醒』(かごつるべ さとのえいざめ)
評価:☆☆☆☆・・・・・・
年度:2012年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
俳優:中村勘三郎(佐野次郎左衛門) 坂東玉三郎(八ツ橋) 中村魁春 中村勘九郎 中村七之助
中村鶴松 片岡亀蔵 片岡市蔵 坂東彌十郎 片岡秀太郎 片岡我當 片岡仁左衛門
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちらただし、ほぼ情報はありません
本稿は
コメント
松竹のシネマ歌舞伎鑑賞は『大江戸りびんぐでっど』に続いて二作目になります。
歌舞伎座の臨場感の高揚はほとんど味わうことができませんが、
高い席料を払っても観ることの出来ないアップ画像を観覧できますから、これはこれで魅力です。
もっとも、失礼ながらアップ映像を見たくない役者さんもおられますから、それはそれで残念です。
どっちやねん。
とびきりの歌舞伎ファンではない私は、役者への思い入れはありません。
やはり一つの演劇作品/映像作品として鑑賞することになります。
そういう目で眺めると、全体を通じて<きょとん>とした印象が残ります。
中村勘三郎扮する佐野次郎左衛門が、振られた数ヶ月後に再び吉原に現れて、
振った八ツ橋(坂東玉三郎)を妖刀籠釣瓶で斬り殺す、その心理的必然が納得いかないから。
無理して自分に言い聞かせるのです。「それだけ時間が経っても恨みを残すほどの恥だったんだよ」と。
むしろ妖刀の魔力をフィーチャーしてくれたほうがファンタジーとして腑に落ちるのですけれど。
歌舞伎の演目の中でも、ストーリーに無理のある作品じゃないのかなあ。
とはいえ、中村勘三郎さん、坂東玉三郎さんの色気とオーラは存分に楽しませていただきました。
そういう作品なんでしょうね、きっと。
あ、そうそう、中村勘九郎さん演じる次六がことのほかよろしゅうございました。
この作品の中ではややリアルすぎる演技だったのかもしれませんが、
私にはお父さんよりライトが当たっているように見えましたね。
2018年10月04日
『インビジブル』
データ
『インビジブル』HOLLOW MAN
評価:☆☆・・・・・・・・
年度:2000年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:ポール・ヴァーホーヴェン
俳優:ケヴィン・ベーコン エリザベス・シュー ジョシュ・ブローリン キム・ディケンズ
ジョーイ・スロトニック メアリー・ランドル グレッグ・グランバーグ
ローナ・ミトラ ウィリアム・ディヴェイン
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
思うことと、それを口に出すことの間には深くて暗い川が流れていますが、
まして実行するとなると、惑星間を飛行するくらい別のことなのです。
私が透明人間になれたら何をしようかな、と二時間空想することはできましたが、
この映画を見なくたってそんなことはできるのでした。
透明人間になったら、女性に悪さを仕掛けようなどと、
21世紀の映画が、、、
科学者ならもう少し斬新なアイデアはなかったものかな、ねえセバスチャン。
いや、ヴァーホーヴェン監督。
滅多にない、観なければ良かった映画でした。
(特にアクション風になった後半ね)
ケヴィン・ベーコンさんやエリザベス・シューさんの熱烈ファンにしかお勧めできません。
『インビジブル』HOLLOW MAN
評価:☆☆・・・・・・・・
年度:2000年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:ポール・ヴァーホーヴェン
俳優:ケヴィン・ベーコン エリザベス・シュー ジョシュ・ブローリン キム・ディケンズ
ジョーイ・スロトニック メアリー・ランドル グレッグ・グランバーグ
ローナ・ミトラ ウィリアム・ディヴェイン
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
思うことと、それを口に出すことの間には深くて暗い川が流れていますが、
まして実行するとなると、惑星間を飛行するくらい別のことなのです。
私が透明人間になれたら何をしようかな、と二時間空想することはできましたが、
この映画を見なくたってそんなことはできるのでした。
透明人間になったら、女性に悪さを仕掛けようなどと、
21世紀の映画が、、、
科学者ならもう少し斬新なアイデアはなかったものかな、ねえセバスチャン。
いや、ヴァーホーヴェン監督。
滅多にない、観なければ良かった映画でした。
(特にアクション風になった後半ね)
ケヴィン・ベーコンさんやエリザベス・シューさんの熱烈ファンにしかお勧めできません。
2018年10月04日
『愛と誠』
データ
『愛と誠』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2012年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:三池崇史
原作:梶原一騎、ながやす巧
音楽:小林武史
主題歌:一青窈『愛と誠のファンタジア』
エンディングテーマ:かりゆし58『笑っててくれよ』
俳優:妻夫木聡(太賀誠) 武井咲(早乙女愛) 斎藤工(岩清水弘) 大野いと(高原由紀)
安藤サクラ(ガムコ)前田健 加藤清史郎 一青窈 余貴美子 伊原剛志 市村正親
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら
本稿は在庫一掃私の鑑賞記録(ログ付け)のための記事の一環です。昔書いたままの文章、短か過ぎるコメントや古い記憶に基づく記述の場合もありますのでご了承ください。再見の機会があれば、補足修正する可能性が高いです。

パンフレットより
コメント
コミカルにはっちゃけた三池崇史監督の映画は『ヤッターマン』以来ですが、私の笑いのツボをついてきます。
いや、笑いました。
アニメのオープニング、妻夫木くんの下手な歌『激しい恋』へと続くオープニングから、昭和の匂いプンプンのインド風映画。
一青窈さん、市村正親さんの歌と踊りというおまけがついてます。
加藤清史郎くんがいい顔してます。
余貴美子さんが登場すると空気が引き締まります。ストーリーが一挙にリアルになります。
向日葵を一輪ぶらさげて見舞いに行ったり、女子トイレでミラーボールぶら下げるスケ番たちもキモかわいかったです。
(P.S. そのスケバンが安藤サクラさん。強烈に印象に残りましたが、今日の活躍は予想できませんでした。)
ウラ主役級のプラトニックガリ勉を斉藤工くんが熱演してます。
伊原剛志さんが高校生というキャスティングはそれだけで笑えます。しかも関西弁。
彼の歌う『狼少年ケン』は焼き付きましたよ、脳裏に。
武井咲さん、底知れない素直な演技がかわいい。彼女のダンスは必見(笑)。
今は演技もダンスもまだまだだけど、いつか第二の吉永小百合さんになれたらいいですね。
そして誰より、妻夫木聡さん。大好きな映画『ジョゼと虎と魚たち』を超えられないな、という印象をずっと抱いていましたが、この映画の妻夫木さんの眼がいいです。一皮むけましたね。特に余貴美子さんとのからみは泣けます。
原作漫画をまったく知らない私ですが、千円でじゅうぶん楽しめました。
観なくてもあなたの人生には何の損もありませんが、
けったいな映画が好きな方と妻夫木ファンには必見です。
『愛と誠』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2012年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:三池崇史
原作:梶原一騎、ながやす巧
音楽:小林武史
主題歌:一青窈『愛と誠のファンタジア』
エンディングテーマ:かりゆし58『笑っててくれよ』
俳優:妻夫木聡(太賀誠) 武井咲(早乙女愛) 斎藤工(岩清水弘) 大野いと(高原由紀)
安藤サクラ(ガムコ)前田健 加藤清史郎 一青窈 余貴美子 伊原剛志 市村正親
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら
本稿は
パンフレットより
コメント
コミカルにはっちゃけた三池崇史監督の映画は『ヤッターマン』以来ですが、私の笑いのツボをついてきます。
いや、笑いました。
アニメのオープニング、妻夫木くんの下手な歌『激しい恋』へと続くオープニングから、昭和の匂いプンプンのインド風映画。
一青窈さん、市村正親さんの歌と踊りというおまけがついてます。
加藤清史郎くんがいい顔してます。
余貴美子さんが登場すると空気が引き締まります。ストーリーが一挙にリアルになります。
向日葵を一輪ぶらさげて見舞いに行ったり、女子トイレでミラーボールぶら下げるスケ番たちもキモかわいかったです。
(P.S. そのスケバンが安藤サクラさん。強烈に印象に残りましたが、今日の活躍は予想できませんでした。)
ウラ主役級のプラトニックガリ勉を斉藤工くんが熱演してます。
伊原剛志さんが高校生というキャスティングはそれだけで笑えます。しかも関西弁。
彼の歌う『狼少年ケン』は焼き付きましたよ、脳裏に。
武井咲さん、底知れない素直な演技がかわいい。彼女のダンスは必見(笑)。
今は演技もダンスもまだまだだけど、いつか第二の吉永小百合さんになれたらいいですね。
そして誰より、妻夫木聡さん。大好きな映画『ジョゼと虎と魚たち』を超えられないな、という印象をずっと抱いていましたが、この映画の妻夫木さんの眼がいいです。一皮むけましたね。特に余貴美子さんとのからみは泣けます。
原作漫画をまったく知らない私ですが、千円でじゅうぶん楽しめました。
観なくてもあなたの人生には何の損もありませんが、
けったいな映画が好きな方と妻夫木ファンには必見です。
2018年10月02日
『美しい星』
データ
『美しい星』
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:吉田大八
原作:三島由紀夫
俳優:リリー・フランキー 亀梨和也 橋本愛 中嶋朋子 佐々木蔵之介 羽場裕一 若葉竜也
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

公式サイトより
コメント
こなれた秀作です。
目を奪われる場面や表情がたくさんありました。
例えば、
リリー・フランキーさんが車ごと田んぼに落ちた後の警官の顔の見え方の角度、
中嶋朋子さんが美しい水のパーティーで佐々木蔵之介さんの話を至近距離で聞いているときの表情、
橋本愛さんが北陸の海岸でUFOを呼ぶポーズの美しさ、
亀梨和也さんがエレベーターの中で何度も暗殺予知を繰り返す場面、
佐々木蔵之介さんが亀梨和也さんの周りを回りながら語るシーン、
・・・
どれもこれも印象的です。
そしてその一つ一つの場面は粒立っているのに、
作品として一つの器に収まってこぼれ落ちないところがお手柄だと感じました。
冒頭に書いた「こなれている」という印象はそういうことなのかなと思っています。
もちろん、「三島由紀夫の原作をよく読み込んで消化しているのだろう」と言う妻の意見を前提として。
作品中に解説的説明はほとんどありませんので、そういう意味では不親切な映画ですから、支離滅裂と見なす観客もあるかもしれません。
ですが私には映画的楽しさに満ちた作品になりました。
主な俳優の使いどころが見物です。
その点でリリーさんの絶妙のいい加減さをはじめ家族四人とも持ち味発揮ですが、佐々木蔵之介さんが本作の強烈なスパイス役になっていたことは忘れるわけにいきません。(そうでなくてはならない役柄なのですが)
惑星人たちのそれぞれのスタンスや表現の違いも面白うございました。
(吉田監督、いつものように随分遊んでいます。)
もしも太陽系のすべての惑星人が一致団結して人類指導に当たってくれたなら、人類はもう少しまともな生き方をしていたかもしれないな、と思うと少し残念ですが、他人いや他星人任せにしないで自分で解決しないといけませんよね。
私も実は冥王星人ですので、
地球人に言いたいことは火星人や水星人や金星人と重なる部分があります。
とはいえ、彼らはせっかちか、または甘すぎるきらいがあります。
地球人は女性だけ残して男性は抹消せよとという私の主張を、みんなが早く受け入れてくれればと思います。
地球人としては男性の私ですが、構いません。冥王星に帰りますから。
亀梨くん、いえ大杉一雄くん、
本当はスイッチは押されたのですよ、カウントダウンは始まっているはずです。
『美しい星』
評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・
年度:2017年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:吉田大八
原作:三島由紀夫
俳優:リリー・フランキー 亀梨和也 橋本愛 中嶋朋子 佐々木蔵之介 羽場裕一 若葉竜也
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら

公式サイトより
コメント
こなれた秀作です。
目を奪われる場面や表情がたくさんありました。
例えば、
リリー・フランキーさんが車ごと田んぼに落ちた後の警官の顔の見え方の角度、
中嶋朋子さんが美しい水のパーティーで佐々木蔵之介さんの話を至近距離で聞いているときの表情、
橋本愛さんが北陸の海岸でUFOを呼ぶポーズの美しさ、
亀梨和也さんがエレベーターの中で何度も暗殺予知を繰り返す場面、
佐々木蔵之介さんが亀梨和也さんの周りを回りながら語るシーン、
・・・
どれもこれも印象的です。
そしてその一つ一つの場面は粒立っているのに、
作品として一つの器に収まってこぼれ落ちないところがお手柄だと感じました。
冒頭に書いた「こなれている」という印象はそういうことなのかなと思っています。
もちろん、「三島由紀夫の原作をよく読み込んで消化しているのだろう」と言う妻の意見を前提として。
作品中に解説的説明はほとんどありませんので、そういう意味では不親切な映画ですから、支離滅裂と見なす観客もあるかもしれません。
ですが私には映画的楽しさに満ちた作品になりました。
主な俳優の使いどころが見物です。
その点でリリーさんの絶妙のいい加減さをはじめ家族四人とも持ち味発揮ですが、佐々木蔵之介さんが本作の強烈なスパイス役になっていたことは忘れるわけにいきません。(そうでなくてはならない役柄なのですが)
惑星人たちのそれぞれのスタンスや表現の違いも面白うございました。
(吉田監督、いつものように随分遊んでいます。)
もしも太陽系のすべての惑星人が一致団結して人類指導に当たってくれたなら、人類はもう少しまともな生き方をしていたかもしれないな、と思うと少し残念ですが、他人いや他星人任せにしないで自分で解決しないといけませんよね。
私も実は冥王星人ですので、
地球人に言いたいことは火星人や水星人や金星人と重なる部分があります。
とはいえ、彼らはせっかちか、または甘すぎるきらいがあります。
地球人は女性だけ残して男性は抹消せよとという私の主張を、みんなが早く受け入れてくれればと思います。
地球人としては男性の私ですが、構いません。冥王星に帰りますから。
亀梨くん、いえ大杉一雄くん、
本当はスイッチは押されたのですよ、カウントダウンは始まっているはずです。
2018年10月02日
『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』
データ
『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:2008年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:ティム・バートン
原作:スティーヴン・ソンドハイム、ヒュー・ウィーラー
音楽:スティーヴン・ソンドハイム
俳優:ジョニー・デップ(スウィーニー・トッド) ヘレナ・ボナム・カーター(ミセス・ラベット) アラン・リックマン(ターピン判事) ティモシー・スポール サシャ・バロン・コーエン エド・サンダース
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら
本稿は在庫一掃私の鑑賞記録(ログ付け)のための記事の一環です。昔書いたままの文章、短か過ぎるコメントや古い記憶に基づく記述の場合もありますのでご了承ください。再見の機会があれば、補足修正する可能性が高いです。

コメント
いやもう素晴らしい。
というか、ダークな色彩とクールな雰囲気を背景に行われる殺戮がツボ。
ミュージカル嫌いな私でも、これなら有りのスムースさ。
笑ってしまいたいけど、笑っちゃいけないと諌める小市民の私を、振り切って笑ってしまった私。
おびただしく流れる血の色が微妙に血の色じゃないところが、『シザーハンズ』/『チャーリーとチョコレート工場』につながる作り物世界の達人の映画。
ティム・バートン
そうそう、『ビートル・ジュース!』から始まったのだった。
その作り物世界の中でぎりぎりなリアル感を醸し出す主役俳優の絶妙演技と歌唱。
ジョニー・ディップ
『デッドマン!』から好きになったんだった。
もう少し詳しく言えば
こんな場所は現実には存在しませんよと、おとぎ話のミニチュアセットのような街並をまず俯瞰して示した『シザーハンズ』。
一つの街だけでセールスが成り立つエイボンレディ。
エドワードはズバリ人造人間だった。こんにちははじめまして両手がはさみの人造人間さん。
その手でちょきちょきすれば植木がみごとな造形に早変わり。
あり得ない色彩のチョコレートを製造するありえない工場を設定してくれたから、ゴールデン・チケットを持つ子どもたちだけでなく、観客の誰にとってもはじめてのありえない見学ができた『チャーリーとチョコレート工場』。
ウォンカさんの表情がふつうの人間のようにスムースに変化していれば、あっというまに二流の映画だったのに。
この二作に比較すると本作『スウィーニー・トッド』は最初、現実感あふれる映画に見える。
ばい煙にくもるリアルなロンドンを再現したと見せかける。
けれどカメラはその<セット>を飛翔して舞台となったパイ屋にたどりつく。
客が来ない店でパイをつくり続ける女店主。
きちんと説明されない無実の罪とその後の苦難。
城の塔に閉じ込められた姫様のようなトッドの娘。
役者たちの白すぎる化粧。
一晩で仕上がる死体すべり台。
一瞬でひげを剃る超絶技巧の床屋技。
燃えさかるオーブンの前でダンス。
映画が始まって五分もたてばまちがいなくこれはおとぎ話だとわかるのに、その残虐シーンに観客はおぞけをふるい目を背ける。
なぜ?
それにはジョニー・ディップの「迫真のつくりもの演技」の神業に秘密がある。
ティム・バートンの、人は観客はそうしたものだと言う見切りに秘密がある。
ヘレナ・ボナム・カーター、すごくいい。
脇役、あるいは助演として、荒唐無稽なフィクションをリアルに感じさせる力がある俳優。
ぶっ飛んだ作品と観客とを結ぶ赤い糸。
さいごにひとこと。
ジョニー、歌声がいいね。
でも、
しばらくは一人で床屋に行かない。
『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』
評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・
年度:2008年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:ティム・バートン
原作:スティーヴン・ソンドハイム、ヒュー・ウィーラー
音楽:スティーヴン・ソンドハイム
俳優:ジョニー・デップ(スウィーニー・トッド) ヘレナ・ボナム・カーター(ミセス・ラベット) アラン・リックマン(ターピン判事) ティモシー・スポール サシャ・バロン・コーエン エド・サンダース
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら
本稿は
コメント
いやもう素晴らしい。
というか、ダークな色彩とクールな雰囲気を背景に行われる殺戮がツボ。
ミュージカル嫌いな私でも、これなら有りのスムースさ。
笑ってしまいたいけど、笑っちゃいけないと諌める小市民の私を、振り切って笑ってしまった私。
おびただしく流れる血の色が微妙に血の色じゃないところが、『シザーハンズ』/『チャーリーとチョコレート工場』につながる作り物世界の達人の映画。
ティム・バートン
そうそう、『ビートル・ジュース!』から始まったのだった。
その作り物世界の中でぎりぎりなリアル感を醸し出す主役俳優の絶妙演技と歌唱。
ジョニー・ディップ
『デッドマン!』から好きになったんだった。
もう少し詳しく言えば
こんな場所は現実には存在しませんよと、おとぎ話のミニチュアセットのような街並をまず俯瞰して示した『シザーハンズ』。
一つの街だけでセールスが成り立つエイボンレディ。
エドワードはズバリ人造人間だった。こんにちははじめまして両手がはさみの人造人間さん。
その手でちょきちょきすれば植木がみごとな造形に早変わり。
あり得ない色彩のチョコレートを製造するありえない工場を設定してくれたから、ゴールデン・チケットを持つ子どもたちだけでなく、観客の誰にとってもはじめてのありえない見学ができた『チャーリーとチョコレート工場』。
ウォンカさんの表情がふつうの人間のようにスムースに変化していれば、あっというまに二流の映画だったのに。
この二作に比較すると本作『スウィーニー・トッド』は最初、現実感あふれる映画に見える。
ばい煙にくもるリアルなロンドンを再現したと見せかける。
けれどカメラはその<セット>を飛翔して舞台となったパイ屋にたどりつく。
客が来ない店でパイをつくり続ける女店主。
きちんと説明されない無実の罪とその後の苦難。
城の塔に閉じ込められた姫様のようなトッドの娘。
役者たちの白すぎる化粧。
一晩で仕上がる死体すべり台。
一瞬でひげを剃る超絶技巧の床屋技。
燃えさかるオーブンの前でダンス。
映画が始まって五分もたてばまちがいなくこれはおとぎ話だとわかるのに、その残虐シーンに観客はおぞけをふるい目を背ける。
なぜ?
それにはジョニー・ディップの「迫真のつくりもの演技」の神業に秘密がある。
ティム・バートンの、人は観客はそうしたものだと言う見切りに秘密がある。
ヘレナ・ボナム・カーター、すごくいい。
脇役、あるいは助演として、荒唐無稽なフィクションをリアルに感じさせる力がある俳優。
ぶっ飛んだ作品と観客とを結ぶ赤い糸。
さいごにひとこと。
ジョニー、歌声がいいね。
でも、
しばらくは一人で床屋に行かない。
2018年09月30日
『パラダイム』
データ
『パラダイム』PRINCE OF DARKNESS
評価:☆☆・・・・・・・・
年度:1988年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:ジョン・カーペンター
俳優:ドナルド・プレザンス ジェームソン・パーカー リサ・ブロント ヴィクター・ウォン
デニス・ダン アリス・クーパー
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
嗚呼カーペンター監督。。
引き締まった名作『遊星からの物体X』の見る影も無い駄作です。
脚本も監督が書いています。言い訳はできません。
タイトル(邦題)も残念ですが、それは批評欄に書きます。
俳優陣がお粗末です。(主役たちがもう致命的)
設定がお粗末です。
展開がお粗末です。
取り柄といえば、サタン信奉者でゾンビ風のアリス・クーパーさん(ロックミュージシャン)の怖さと、
1988年時点で「サタンは神の子」という文言を映画史上に残したことくらいでしょうか。
あ、アジア系二人の俳優陣は存在感を示していました。
タグ付けは監督とこの三人に絞っておきます。
批評
作品は作品として観なければならない。
世評や監督の他作品などはもちろん、
邦題の適切さ、キャッチコピーの是非などに惑わされてはいけない。
という正論を私は認めますけれど、それでもやはり私など惑わされてしまうのですよ。
その惑いが良い結果を生むこともあれば悪い結果を招くこともあります。
結局は自分のせいですけれど、惑うきっかけはたいてい制作側・配給側のセンスの悪さと浅薄な儲け主義にあります。
したがって、悪い結果になることが圧倒的に多くなります。
本作は悪い結果となった好例です。
『パラダイム』という題名をなぜつけたのでしょう。
「パラダイム」(日本語では「思考の枠組み」)という概念は、20世紀の科学哲学者クーンの著述が誤解(または拡大解釈)され、一人歩きし、またたくまに世界に広がった新しい概念です。
みんなこういう概念を待っていたのでしょうね。
拡大解釈された結果、主に「パラダイムシフト」という使用法で使われました。
その詳細は、wikipediaの説明が比較的わかりやすいので、正しく知りたい方はご覧ください。
ここでは、浅はかにも私が事前に本作に期待したパラダイムシフトを簡単に紹介しておきます。
繰り返し書いていますが、私はキリスト教は片手落ち宗教だと考えています。
(『オーメン』にて詳述)
善悪の善のみをすくい上げて成立させているからです。
全知全能の絶対神はすなわち愛であり善なのに、なぜ人間世界に悪がはびこるのか、という疑問に対し「人間が過ちをおかしたから(原罪)」と解答するしか無いのです。
これがキリスト教教義のパラダイム(思考の枠組み)です。
『沈黙』その他で明らかなように、「なぜ神は救ってくださらないのか」という信者の訴えに対し、神は何一つ手を差し伸べてくれません。
キリスト教信仰の大きな矛盾点であることを誰もが薄々気がついていたはずです。
もっともその矛盾はキリスト自身が磔の上で「エリ・エリ・レマ・サバクタニ(神よ我が神、なぜに私をお見捨てになる)」(マタイによる福音書第27章) と叫んだとありますから、宗教成立時点ですでに意識されていたことでしょう。
その旧来のパラダイムを大転換(パラダイムシフト)するには、宗教成立時点(厳密には母教であるユダヤ教成立)で捨ててしまった異端の神々、中でもサタンに代表される悪魔群、すなわち悪の神の復活・共存という未来しかないはずです。
〜こういう道筋を期待したのですが、
登場神父の「私たちはセールスマンにすぎない」とか、古文書の「神は我が子サタンを砂漠に封じ込めた」などといい線まで匂わせながら、新しいキリスト教パラダイムを示すことはできず、サタンの復活を恐怖とともに描こうとするよくある悪魔ものから脱皮することはなかったのです。
私の勝手な期待に背いたからといってここまで低評価されてしまってはカーペンター監督にすまない気持ちもあります。
最大の要因は、原題ですらないパラダイムという用語を使った日本の配給側の無知性です。
(原題は『PRINCE OF DARKNESS」:”闇の王子”かな)
墓の下のクーンさんも、さらに誤解が誤解を招いてしまったかとお嘆きでしょう。
(もちろん、paradigmという英単語は、クーン以前からあり、例とか模範とかの意味で使われています。念のため。)
『パラダイム』PRINCE OF DARKNESS
評価:☆☆・・・・・・・・
年度:1988年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。
監督:ジョン・カーペンター
俳優:ドナルド・プレザンス ジェームソン・パーカー リサ・ブロント ヴィクター・ウォン
デニス・ダン アリス・クーパー
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら

コメント
嗚呼カーペンター監督。。
引き締まった名作『遊星からの物体X』の見る影も無い駄作です。
脚本も監督が書いています。言い訳はできません。
タイトル(邦題)も残念ですが、それは批評欄に書きます。
俳優陣がお粗末です。(主役たちがもう致命的)
設定がお粗末です。
展開がお粗末です。
取り柄といえば、サタン信奉者でゾンビ風のアリス・クーパーさん(ロックミュージシャン)の怖さと、
1988年時点で「サタンは神の子」という文言を映画史上に残したことくらいでしょうか。
あ、アジア系二人の俳優陣は存在感を示していました。
タグ付けは監督とこの三人に絞っておきます。
批評
作品は作品として観なければならない。
世評や監督の他作品などはもちろん、
邦題の適切さ、キャッチコピーの是非などに惑わされてはいけない。
という正論を私は認めますけれど、それでもやはり私など惑わされてしまうのですよ。
その惑いが良い結果を生むこともあれば悪い結果を招くこともあります。
結局は自分のせいですけれど、惑うきっかけはたいてい制作側・配給側のセンスの悪さと浅薄な儲け主義にあります。
したがって、悪い結果になることが圧倒的に多くなります。
本作は悪い結果となった好例です。
『パラダイム』という題名をなぜつけたのでしょう。
「パラダイム」(日本語では「思考の枠組み」)という概念は、20世紀の科学哲学者クーンの著述が誤解(または拡大解釈)され、一人歩きし、またたくまに世界に広がった新しい概念です。
みんなこういう概念を待っていたのでしょうね。
拡大解釈された結果、主に「パラダイムシフト」という使用法で使われました。
その詳細は、wikipediaの説明が比較的わかりやすいので、正しく知りたい方はご覧ください。
ここでは、浅はかにも私が事前に本作に期待したパラダイムシフトを簡単に紹介しておきます。
繰り返し書いていますが、私はキリスト教は片手落ち宗教だと考えています。
(『オーメン』にて詳述)
善悪の善のみをすくい上げて成立させているからです。
全知全能の絶対神はすなわち愛であり善なのに、なぜ人間世界に悪がはびこるのか、という疑問に対し「人間が過ちをおかしたから(原罪)」と解答するしか無いのです。
これがキリスト教教義のパラダイム(思考の枠組み)です。
『沈黙』その他で明らかなように、「なぜ神は救ってくださらないのか」という信者の訴えに対し、神は何一つ手を差し伸べてくれません。
キリスト教信仰の大きな矛盾点であることを誰もが薄々気がついていたはずです。
もっともその矛盾はキリスト自身が磔の上で「エリ・エリ・レマ・サバクタニ(神よ我が神、なぜに私をお見捨てになる)」(マタイによる福音書第27章) と叫んだとありますから、宗教成立時点ですでに意識されていたことでしょう。
その旧来のパラダイムを大転換(パラダイムシフト)するには、宗教成立時点(厳密には母教であるユダヤ教成立)で捨ててしまった異端の神々、中でもサタンに代表される悪魔群、すなわち悪の神の復活・共存という未来しかないはずです。
〜こういう道筋を期待したのですが、
登場神父の「私たちはセールスマンにすぎない」とか、古文書の「神は我が子サタンを砂漠に封じ込めた」などといい線まで匂わせながら、新しいキリスト教パラダイムを示すことはできず、サタンの復活を恐怖とともに描こうとするよくある悪魔ものから脱皮することはなかったのです。
私の勝手な期待に背いたからといってここまで低評価されてしまってはカーペンター監督にすまない気持ちもあります。
最大の要因は、原題ですらないパラダイムという用語を使った日本の配給側の無知性です。
(原題は『PRINCE OF DARKNESS」:”闇の王子”かな)
墓の下のクーンさんも、さらに誤解が誤解を招いてしまったかとお嘆きでしょう。
(もちろん、paradigmという英単語は、クーン以前からあり、例とか模範とかの意味で使われています。念のため。)
2018年09月30日
『大鹿村騒動記』
データ
『大鹿村騒動記』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2011年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:阪本順治
撮影:笠松則通
主題歌:忌野清志郎
俳優:原田芳雄 大楠道代 岸部一徳 松たか子 佐藤浩市 三國連太郎
冨浦智嗣 瑛太 石橋蓮司 小野武彦 小倉一郎 でんでん 加藤虎ノ介
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら
本稿は在庫一掃私の鑑賞記録(ログ付け)のための記事の一環です。昔書いたままの文章、短か過ぎるコメントや古い記憶に基づく記述の場合もありますのでご了承ください。再見の機会があれば、補足修正する可能性が高いです。

↑↓出典不明:支障あれば連絡をください

コメント
原田芳雄さんの遺作となった『大鹿村騒動記』。
監督は阪本順治さん。私にとっては「闇の子供たち」以来の彼の作品でした。

批評:「仇も恨も是まで是まで」
(あだもうらみもこれまでこれまで)
実在する大鹿村歌舞伎劇中のこの台詞は、この映画の登場人物の決意だけでなく、私たちにはとても馴染みのある人生の「標語」「金言」ですよね。
この台詞が作品中でもよく生かされていた作品でした。
仇や恨を消し去る為にはハレの日が必要なのだ、というのは忘れてはならない真理です。
祭りも村歌舞伎も、だからこそ今日まで命を保っているのです。
でもここでは、少し違う観点で書いていきます。
この映画は、
これが原田さんの遺作になるかも知れないと言う思いで製作されたのでしょう。
製作期間がわずか二週間だったそうです。
この短さが、よくも悪くもこの作品の性格を規定したようです。
舞台の背景となる長野県大鹿村での撮影は11月に行われました。
映画は、実際にこの大鹿村で村民の力で行われている歌舞伎公演に向かって進行します。
原田さんたち主要な出演者は、この歌舞伎に関わる人々という設定です。
大鹿村のHPによれば、大鹿歌舞伎の公演は5月と10月。
たとえば南アルプスに残雪が残る5月公演の終了時のエピソードあたりから映画をスタートさせれば、
美しい大鹿村の風景の変化を背景に取り込むことができ、
人間関係の描き方も深くなり、
良い意味での大作映画になったでしょう。
それほどこの映画の素材と出演者には魅力があるのです。

しかしそれはかないませんでした。
急いで製作しなければならないということは、歌舞伎公演直前に起こったドタバタ騒動を描くしかないということです。
つまり娯楽レベルでのコメディとして脚本を書くしかなかったことになります。
その準備期間が短かったことから起こった不満を具体的に1,2挙げます。
たとえば佐藤浩市さんの松たか子さんへの思慕の描写は、
たった一つの回想シーンでも追加されていれば、説得力がズンと深まったでしょう。
あるいは三国連太郎さんのシベリア抑留体験が、現在の彼の行動に影を落としているような描写がわずかでもあれば、
この映画は観客の心が揺さぶられる重層的な本格コメディになり得たでしょう。
存在感のあるホンモノの役者を使う限り、
制作者側はそこまで配慮する義務があるのだと私は考えます。
しかしそれは不可能でした。
おそらく原田芳雄さんの体調が許す短い期間にやり遂げなければならなかったからでしょう。
出演者たちも半ばそれを知りつつ、スケジュールを強引に調整して結集したと思われます。
ところがそのことが逆に、
この映画の魅力を生み出したとも言えます。
一人一人の役者の今しかない想いの渾身の演技の光芒が、
原田芳雄さん、岸部一徳さん、大楠道代さんという主要な三人の俳優のまわりを飛び回って包むような、
こじんまりしながらも密度の高い佳作を生みました。
これは、
合宿のような撮影現場が醸し出したとも言え、
大鹿村の風土と村民の力とも言えそうです。
褒め言葉を具体的に書くには映画の筋の本流に触れなければなりません。
「仇も恨も是まで是まで」という肝心の台詞に向き合って書きたいのですが、
残念ながら正確に思い出すことができません。
そこで最後に、
ずらり並んだ脇役たちの演技だけでなく、
原田さんの内向的な不良性、
岸部さんの外交的な不良性、
この二人の不良性がからみあうナマナマしくも飄々としたシーンを観るだけでも一見の価値があるということと、
この二人をはじめとする俳優たちの姿は、
日本のフツーの村のフツーの人々のフツーの可笑しさ、不良性に見事に立脚しているということを指摘して、
今回の筆をおくことにします。
はは、
ニッポン人は不良です。
素敵じゃないですか。
『大鹿村騒動記』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:2011年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:阪本順治
撮影:笠松則通
主題歌:忌野清志郎
俳優:原田芳雄 大楠道代 岸部一徳 松たか子 佐藤浩市 三國連太郎
冨浦智嗣 瑛太 石橋蓮司 小野武彦 小倉一郎 でんでん 加藤虎ノ介
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら
本稿は

↑↓出典不明:支障あれば連絡をください
コメント
原田芳雄さんの遺作となった『大鹿村騒動記』。
監督は阪本順治さん。私にとっては「闇の子供たち」以来の彼の作品でした。
批評:「仇も恨も是まで是まで」
(あだもうらみもこれまでこれまで)
実在する大鹿村歌舞伎劇中のこの台詞は、この映画の登場人物の決意だけでなく、私たちにはとても馴染みのある人生の「標語」「金言」ですよね。
この台詞が作品中でもよく生かされていた作品でした。
仇や恨を消し去る為にはハレの日が必要なのだ、というのは忘れてはならない真理です。
祭りも村歌舞伎も、だからこそ今日まで命を保っているのです。
でもここでは、少し違う観点で書いていきます。
この映画は、
これが原田さんの遺作になるかも知れないと言う思いで製作されたのでしょう。
製作期間がわずか二週間だったそうです。
この短さが、よくも悪くもこの作品の性格を規定したようです。
舞台の背景となる長野県大鹿村での撮影は11月に行われました。
映画は、実際にこの大鹿村で村民の力で行われている歌舞伎公演に向かって進行します。
原田さんたち主要な出演者は、この歌舞伎に関わる人々という設定です。
大鹿村のHPによれば、大鹿歌舞伎の公演は5月と10月。
たとえば南アルプスに残雪が残る5月公演の終了時のエピソードあたりから映画をスタートさせれば、
美しい大鹿村の風景の変化を背景に取り込むことができ、
人間関係の描き方も深くなり、
良い意味での大作映画になったでしょう。
それほどこの映画の素材と出演者には魅力があるのです。

しかしそれはかないませんでした。
急いで製作しなければならないということは、歌舞伎公演直前に起こったドタバタ騒動を描くしかないということです。
つまり娯楽レベルでのコメディとして脚本を書くしかなかったことになります。
その準備期間が短かったことから起こった不満を具体的に1,2挙げます。
たとえば佐藤浩市さんの松たか子さんへの思慕の描写は、
たった一つの回想シーンでも追加されていれば、説得力がズンと深まったでしょう。
あるいは三国連太郎さんのシベリア抑留体験が、現在の彼の行動に影を落としているような描写がわずかでもあれば、
この映画は観客の心が揺さぶられる重層的な本格コメディになり得たでしょう。
存在感のあるホンモノの役者を使う限り、
制作者側はそこまで配慮する義務があるのだと私は考えます。
しかしそれは不可能でした。
おそらく原田芳雄さんの体調が許す短い期間にやり遂げなければならなかったからでしょう。
出演者たちも半ばそれを知りつつ、スケジュールを強引に調整して結集したと思われます。
ところがそのことが逆に、
この映画の魅力を生み出したとも言えます。
一人一人の役者の今しかない想いの渾身の演技の光芒が、
原田芳雄さん、岸部一徳さん、大楠道代さんという主要な三人の俳優のまわりを飛び回って包むような、
こじんまりしながらも密度の高い佳作を生みました。
これは、
合宿のような撮影現場が醸し出したとも言え、
大鹿村の風土と村民の力とも言えそうです。
褒め言葉を具体的に書くには映画の筋の本流に触れなければなりません。
「仇も恨も是まで是まで」という肝心の台詞に向き合って書きたいのですが、
残念ながら正確に思い出すことができません。
そこで最後に、
ずらり並んだ脇役たちの演技だけでなく、
原田さんの内向的な不良性、
岸部さんの外交的な不良性、
この二人の不良性がからみあうナマナマしくも飄々としたシーンを観るだけでも一見の価値があるということと、
この二人をはじめとする俳優たちの姿は、
日本のフツーの村のフツーの人々のフツーの可笑しさ、不良性に見事に立脚しているということを指摘して、
今回の筆をおくことにします。
はは、
ニッポン人は不良です。
素敵じゃないですか。
2018年09月28日
『フロム・ダスク・ティル・ドーン』
データ
『フロム・ダスク・ティル・ドーン』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:1996年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:ロバート・ロドリゲス
原案:ロバート・カーツマン
脚本:クエンティン・タランティーノ
音楽:グレーム・レヴェル
撮影:ギレルモ・ナヴァロ
俳優:ジョージ・クルーニー(セス・ゲッコー) クエンティン・タランティーノ(リチャード・ゲッコー)
ハーヴェイ・カイテル(ジェイコブ・フラー) ジュリエット・ルイス(ケイト・フラー)
アーネスト・リュー(スコット・フラー)サルマ・ハエック フレッド・ウィリアムソン
トム・サヴィーニ チーチ・マリン
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら


コメント
前半は犯罪ムービー。
ジョージ・クルーニーさんとクエンティン・タランティーノさんがイカレてます。悪い奴らです。たまりません。
ジュリエット・ルイスさんまで仲間になるのかな、これから犯罪を繰り返して最後にみんな死ぬのかな。タランティーノ風に味付けされた『BONNIE AND CLYDE』(俺たちに明日はない)かいな、それとも『明日に向かって撃て』やろかと思っていたら、びっくり。
後半は閉じられた空間のホラーアクションの風情。
一粒で二度美味しいグリコ映画でした。
製作していて楽しかったでしょうね。
映画オタクには語ることが多すぎる作品のようです。
残念ながらオタクにはなれない私には、特にコメントすることはありませんが、
少しばかりヘンな映画が好きな方には強くお勧めできます。
そうそう、30歳のサルマ・ハエックさんの妖艶な姿は一見の価値があります。
『フリーダ』よりも8年前の作品です。
『フロム・ダスク・ティル・ドーン』
評価:☆☆☆☆☆☆・・・・
年度:1996年
鑑賞:2018年BS/CSで視聴。
監督:ロバート・ロドリゲス
原案:ロバート・カーツマン
脚本:クエンティン・タランティーノ
音楽:グレーム・レヴェル
撮影:ギレルモ・ナヴァロ
俳優:ジョージ・クルーニー(セス・ゲッコー) クエンティン・タランティーノ(リチャード・ゲッコー)
ハーヴェイ・カイテル(ジェイコブ・フラー) ジュリエット・ルイス(ケイト・フラー)
アーネスト・リュー(スコット・フラー)サルマ・ハエック フレッド・ウィリアムソン
トム・サヴィーニ チーチ・マリン
製作国:アメリカ
allcinemaの情報ページはこちら


コメント
前半は犯罪ムービー。
ジョージ・クルーニーさんとクエンティン・タランティーノさんがイカレてます。悪い奴らです。たまりません。
ジュリエット・ルイスさんまで仲間になるのかな、これから犯罪を繰り返して最後にみんな死ぬのかな。タランティーノ風に味付けされた『BONNIE AND CLYDE』(俺たちに明日はない)かいな、それとも『明日に向かって撃て』やろかと思っていたら、びっくり。
後半は閉じられた空間のホラーアクションの風情。
一粒で二度美味しいグリコ映画でした。
製作していて楽しかったでしょうね。
映画オタクには語ることが多すぎる作品のようです。
残念ながらオタクにはなれない私には、特にコメントすることはありませんが、
少しばかりヘンな映画が好きな方には強くお勧めできます。
そうそう、30歳のサルマ・ハエックさんの妖艶な姿は一見の価値があります。
『フリーダ』よりも8年前の作品です。
2018年09月28日
『恋しくて』
データ
『恋しくて』
評価:☆☆☆☆・・・・・・
年度:2007年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:中江裕司
主題歌:BEGIN『ミーファイユー』
俳優:石田法嗣 東里翔斗 宜保秀明 大嶺健一 山入端佳美 与世山澄子 平良とみ
三宅裕司 BEGIN 登川誠仁(牛の声)
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら
本作稿は在庫一掃私の鑑賞記録(ログ付け)のための記事の一環です。昔書いたままの文章、短か過ぎるコメントや古い記憶に基づく記述の場合もありますのでご了承ください。再見の機会があれば、補足修正する可能性が高いです。
 パンフレットより
パンフレットより
コメント
那覇桜坂劇場を文化発信の地に育て上げた中江さんの功績は偉大というべきです。
その中江さんが監督として創り上げた本作は、BEGINのデビュー曲『恋しくて』をモチーフに、石垣島の若者の青春物語を採り上げます。
BGINの三人のメンバーの青春と微妙に重ね合わせながら。
とはいえ、この青春ドラマはあまりにシンプルで、心理に分け入る深さがありません。
社会性も、沖縄の風土の匂いも感じられません。
なぜ作ったのかな、と思う作品です。
ただし、石垣島もBEGINも大好きな私は、映画の内容とは別のところで楽しませていただいたことは事実です。
批評欄の文章は、本作を鑑賞した直後の文章です。(わずかに修正)
批評
中江作品は、『ナビィの恋』『ホテル・ハイビスカス』『白百合クラブ 東京へ行く』に続いて本作が四作目の鑑賞となります。
その後、『さんかく山のマジルー 真夏の夜の夢』も観ました。
すべて沖縄が主たる舞台になっています。
どの作品も、ウチナー(沖縄)、ヤイマ(八重山)の自然が、人間が、観客の目の前に存在し動いているような親近感と美しさと力強さが漂っています。
大気の熱さも感じます。
登場人物が素敵です。
でも私には、ウチナー、ヤイマのあの空気に含まれた猥雑な匂い、色っぽいとも言える香りが、だんだん薄れてきているような気がします。
その匂いは、良い意味での”下品さ”と言い換えても良い、私の皮膚にまとわりつき、しみ通ってくる「何か」なのです。
私はこの感覚が好きなので、インドネシアが、タイが好きになり、ウチナー、ヤイマからも、もう逃れられなくなってしまっています。
この嗜好は世の「沖縄病」患者の多くの人と(たぶん)同じではないでしょうか。
別のことばを使えば、人間の得体の知れなさ、自然の不気味さ、にも通じる、かなり本能に訴える「何か」なのです。
その「何か」が、中江作品には希薄なように思われます。
これは作品の欠点ではなく、中江監督の沖縄への対峙の仕方それ自体がこうである、ということなのでしょう。
中江監督はきっと上品な方なのです。
ただ、四作品の中では、この「何か」が色濃く漂う作品もありました。『ナビィの恋』です。
思えば、平良とみさんという俳優が、その「何か」を醸し出し、提示してくれていたのでしょうか。
今回の『恋しくて』の中では、その平良とみさんを除くと、シンガー与世山澄子さんの歌にだけ、かすかに感じましたこの感触を。
中江監督の映画が好きです。
しかし私は、中江監督の本作をきっかけに沖縄が好きになることはないでしょう。
ま、もうとっくに好きになっているからよいのですが。
『恋しくて』
評価:☆☆☆☆・・・・・・
年度:2007年
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:中江裕司
主題歌:BEGIN『ミーファイユー』
俳優:石田法嗣 東里翔斗 宜保秀明 大嶺健一 山入端佳美 与世山澄子 平良とみ
三宅裕司 BEGIN 登川誠仁(牛の声)
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら
本作稿は
コメント
那覇桜坂劇場を文化発信の地に育て上げた中江さんの功績は偉大というべきです。
その中江さんが監督として創り上げた本作は、BEGINのデビュー曲『恋しくて』をモチーフに、石垣島の若者の青春物語を採り上げます。
BGINの三人のメンバーの青春と微妙に重ね合わせながら。
とはいえ、この青春ドラマはあまりにシンプルで、心理に分け入る深さがありません。
社会性も、沖縄の風土の匂いも感じられません。
なぜ作ったのかな、と思う作品です。
ただし、石垣島もBEGINも大好きな私は、映画の内容とは別のところで楽しませていただいたことは事実です。
批評欄の文章は、本作を鑑賞した直後の文章です。(わずかに修正)
批評
中江作品は、『ナビィの恋』『ホテル・ハイビスカス』『白百合クラブ 東京へ行く』に続いて本作が四作目の鑑賞となります。
その後、『さんかく山のマジルー 真夏の夜の夢』も観ました。
すべて沖縄が主たる舞台になっています。
どの作品も、ウチナー(沖縄)、ヤイマ(八重山)の自然が、人間が、観客の目の前に存在し動いているような親近感と美しさと力強さが漂っています。
大気の熱さも感じます。
登場人物が素敵です。
でも私には、ウチナー、ヤイマのあの空気に含まれた猥雑な匂い、色っぽいとも言える香りが、だんだん薄れてきているような気がします。
その匂いは、良い意味での”下品さ”と言い換えても良い、私の皮膚にまとわりつき、しみ通ってくる「何か」なのです。
私はこの感覚が好きなので、インドネシアが、タイが好きになり、ウチナー、ヤイマからも、もう逃れられなくなってしまっています。
この嗜好は世の「沖縄病」患者の多くの人と(たぶん)同じではないでしょうか。
別のことばを使えば、人間の得体の知れなさ、自然の不気味さ、にも通じる、かなり本能に訴える「何か」なのです。
その「何か」が、中江作品には希薄なように思われます。
これは作品の欠点ではなく、中江監督の沖縄への対峙の仕方それ自体がこうである、ということなのでしょう。
中江監督はきっと上品な方なのです。
ただ、四作品の中では、この「何か」が色濃く漂う作品もありました。『ナビィの恋』です。
思えば、平良とみさんという俳優が、その「何か」を醸し出し、提示してくれていたのでしょうか。
今回の『恋しくて』の中では、その平良とみさんを除くと、シンガー与世山澄子さんの歌にだけ、かすかに感じましたこの感触を。
中江監督の映画が好きです。
しかし私は、中江監督の本作をきっかけに沖縄が好きになることはないでしょう。
ま、もうとっくに好きになっているからよいのですが。
2018年09月26日
『20世紀少年』(全三作)
データ
『20世紀少年』(全三作)
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2008年(『Ⅰ』)
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:堤幸彦
原作:浦沢直樹
主題歌:T・レックス「20th Century Boy」
俳優:『Ⅰ』唐沢寿明 豊川悦司 常盤貴子 香川照之 石塚英彦 宇梶剛士 宮迫博之 生瀬勝久
小日向文世 佐々木蔵之介 佐野史郎 森山未來 津田寛治 藤井隆 山田花子 ARATA 片瀬那奈
池脇千鶴 平愛梨 光石研 竜雷太 研ナオコ 石橋蓮司 中村嘉葎雄 黒木瞳
『Ⅱ』藤木直人 古田新太 小池栄子 木南晴夏 前田健 佐藤二朗 西村雅彦 石丸謙二郎
佐々木すみ江 梅津栄 ユースケ・サンタマリア 甲本雅裕 西村和彦 小松政夫 平田満
『Ⅲ』六平直政 竹中直人 遠藤賢司 サーマート・セーンサンギアム チェン・チャオロン
斎藤工 神木隆之介 高橋幸宏
※重複を避けました。
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら(『第1章』)
本作は在庫一掃私の鑑賞記録(ログ付け)のための記事の一環です。昔書いたままの文章、短か過ぎるコメントや古い記憶に基づく記述の場合もありますのでご了承ください。再見の機会があれば、補足修正する可能性が高いです。

パンフレットより
コメント
よく頑張って映画化したな、と思った映画でした。
星の数は、その営為へのご褒美です。(エラソー)
私たちは原作漫画の熱心なファンでした。
特に妻の場合は登場人物と世代的にかぶっているため、いつも楽しそうに読んでいました。
私は私で、少年時代の友情や想像や悪夢が、長じても残っている、いやむしろ歪みながら大きく育っているこの種の漫画は初体験でしたので、シュールで不穏な印象を楽しんで読んでいました。
第二第三のオウム、、出現するかなと思ってたら、あっという間にもう蔓延ってるじゃないですか。
日本会議、統一教会、創価学会、安倍信者まで一体になった不気味なファシズムが。
映画として観るときに、様々な大道具や小道具、そしてもちろん登場人物たちがどのように再現されて映像になるのか楽しみでした。
その結果、『Ⅰ』『Ⅱ』『Ⅲ』を通じて、俳優さんたちが原作映画のテイストに忠実なことに驚きました。
ビジュアル面での俳優の再現率の高さベストスリーを発表します。
①平愛梨さん:物語の要になる遠藤カンナちゃんの再現率はもう言うことなしの可愛さ。
②豊川悦司さん:ビジュアルの相似に加えてオッチョのアウトローヒーロー的な側面が強く感じられました。
③ARATAさん(井浦新さん):殺し屋13番。強く原作を思い出させてくれました。
他に印象的だった出演者をリストアップしてみます。
・遠藤賢司さん:最終章に登場。撮影に際して顔合わせの時、堤幸彦監督も原作者浦沢直樹さんもガチガチに緊張したというエピソードが伝わっています。私が大好きだったミュージシャンであると同時に、本作の主人公遠藤健児(ケンヂ)のモデルでもあります。
・木南晴夏さん:小泉響子役。原作以上にイキイキと良い人ぶりを発揮。
・小池栄子さん:年齢的に高須光代役には無理がありましたが、原作とは違う怖さを表現。私がファンになったきっかけの作品です。
・佐々木蔵之介さん:フクベエ役の目つきが悪く、不穏でした。
・佐藤二朗さん:ホクロのおまわりさんの無表情な笑顔?・・不気味さがよく再現されていました。
というわけで、原作愛読者としてはたっぷり楽しめたのです。
でも、しかし、
俳優の皆さんどなたの熱演も、
『Ⅲ』終盤の屋上の神木隆之介さん(その場面で本作初登場)の笑顔がかっさらっていきました。
のちに「ともだち」となる陰影を笑顔の中に滲ませての登場。おそるべし神木(by 妻)
ということは、神木さんにかっさらわれていく、ということは、
やはり原作を映画化するに当たっての再構成作業の失敗は認めざるをえますまい。
忠実に作って(映画として)成功するわけではないのです。
演技には素人のタレントまで含めてオールスターキャストを楽しみましょう。
辛抱すれば、神木隆之介さんが待ってます。

パンフレットより
批評欄の文章は浦沢直樹さんの漫画からの引用です。
私にとって、この原作漫画の根幹に関わるセリフ集です。
そのまま映画に使われているとは限りません。
批評
『私はコリンズ。
月の周回軌道から、アームストロングとオルドリンが着陸するのを見ていた。』
「ぶはははは!! なんだこりゃあ? ただの
バカでかいテルテル坊主じゃないか。」
『失敗だ。失敗だ。失敗だ。』
『あんな奴。あんな奴。
絶交だ。』
『あんな恐ろしいテルテル坊主が
宙にぶら下がっているんだよ。
誰か叫んでよ。
恐怖で逃げまわってよ。』
『誰も見ていてくれなかった。
先生が全員で目をつぶれって…
スプーンを曲げた奴は手を上げろって…
僕はこうやって手を上げたのに…
みんな、本当に、目をつぶっていて、
誰も見ていないんだ…
見てよ。
誰か、僕を見てよ。
誰か驚いてよ。』
『誰も気にかけてない…
夏休みの間中、万博に行ってる僕が
ここにいるのに、
誰も…
僕がここにいるのに…』
『ケーンヂくーん。あーそーびまーしょ。』
『20世紀少年』(全三作)
評価:☆☆☆☆☆・・・・・
年度:2008年(『Ⅰ』)
鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。
監督:堤幸彦
原作:浦沢直樹
主題歌:T・レックス「20th Century Boy」
俳優:『Ⅰ』唐沢寿明 豊川悦司 常盤貴子 香川照之 石塚英彦 宇梶剛士 宮迫博之 生瀬勝久
小日向文世 佐々木蔵之介 佐野史郎 森山未來 津田寛治 藤井隆 山田花子 ARATA 片瀬那奈
池脇千鶴 平愛梨 光石研 竜雷太 研ナオコ 石橋蓮司 中村嘉葎雄 黒木瞳
『Ⅱ』藤木直人 古田新太 小池栄子 木南晴夏 前田健 佐藤二朗 西村雅彦 石丸謙二郎
佐々木すみ江 梅津栄 ユースケ・サンタマリア 甲本雅裕 西村和彦 小松政夫 平田満
『Ⅲ』六平直政 竹中直人 遠藤賢司 サーマート・セーンサンギアム チェン・チャオロン
斎藤工 神木隆之介 高橋幸宏
※重複を避けました。
製作国:日本
allcinemaの情報ページはこちら(『第1章』)
本作は
パンフレットより
コメント
よく頑張って映画化したな、と思った映画でした。
星の数は、その営為へのご褒美です。(エラソー)
私たちは原作漫画の熱心なファンでした。
特に妻の場合は登場人物と世代的にかぶっているため、いつも楽しそうに読んでいました。
私は私で、少年時代の友情や想像や悪夢が、長じても残っている、いやむしろ歪みながら大きく育っているこの種の漫画は初体験でしたので、シュールで不穏な印象を楽しんで読んでいました。
第二第三のオウム、、出現するかなと思ってたら、あっという間にもう蔓延ってるじゃないですか。
日本会議、統一教会、創価学会、安倍信者まで一体になった不気味なファシズムが。
映画として観るときに、様々な大道具や小道具、そしてもちろん登場人物たちがどのように再現されて映像になるのか楽しみでした。
その結果、『Ⅰ』『Ⅱ』『Ⅲ』を通じて、俳優さんたちが原作映画のテイストに忠実なことに驚きました。
ビジュアル面での俳優の再現率の高さベストスリーを発表します。
①平愛梨さん:物語の要になる遠藤カンナちゃんの再現率はもう言うことなしの可愛さ。
②豊川悦司さん:ビジュアルの相似に加えてオッチョのアウトローヒーロー的な側面が強く感じられました。
③ARATAさん(井浦新さん):殺し屋13番。強く原作を思い出させてくれました。
他に印象的だった出演者をリストアップしてみます。
・遠藤賢司さん:最終章に登場。撮影に際して顔合わせの時、堤幸彦監督も原作者浦沢直樹さんもガチガチに緊張したというエピソードが伝わっています。私が大好きだったミュージシャンであると同時に、本作の主人公遠藤健児(ケンヂ)のモデルでもあります。
・木南晴夏さん:小泉響子役。原作以上にイキイキと良い人ぶりを発揮。
・小池栄子さん:年齢的に高須光代役には無理がありましたが、原作とは違う怖さを表現。私がファンになったきっかけの作品です。
・佐々木蔵之介さん:フクベエ役の目つきが悪く、不穏でした。
・佐藤二朗さん:ホクロのおまわりさんの無表情な笑顔?・・不気味さがよく再現されていました。
というわけで、原作愛読者としてはたっぷり楽しめたのです。
でも、しかし、
俳優の皆さんどなたの熱演も、
『Ⅲ』終盤の屋上の神木隆之介さん(その場面で本作初登場)の笑顔がかっさらっていきました。
のちに「ともだち」となる陰影を笑顔の中に滲ませての登場。おそるべし神木(by 妻)
ということは、神木さんにかっさらわれていく、ということは、
やはり原作を映画化するに当たっての再構成作業の失敗は認めざるをえますまい。
忠実に作って(映画として)成功するわけではないのです。
演技には素人のタレントまで含めてオールスターキャストを楽しみましょう。
辛抱すれば、神木隆之介さんが待ってます。
パンフレットより
批評欄の文章は浦沢直樹さんの漫画からの引用です。
私にとって、この原作漫画の根幹に関わるセリフ集です。
そのまま映画に使われているとは限りません。
批評
『私はコリンズ。
月の周回軌道から、アームストロングとオルドリンが着陸するのを見ていた。』
「ぶはははは!! なんだこりゃあ? ただの
バカでかいテルテル坊主じゃないか。」
『失敗だ。失敗だ。失敗だ。』
『あんな奴。あんな奴。
絶交だ。』
『あんな恐ろしいテルテル坊主が
宙にぶら下がっているんだよ。
誰か叫んでよ。
恐怖で逃げまわってよ。』
『誰も見ていてくれなかった。
先生が全員で目をつぶれって…
スプーンを曲げた奴は手を上げろって…
僕はこうやって手を上げたのに…
みんな、本当に、目をつぶっていて、
誰も見ていないんだ…
見てよ。
誰か、僕を見てよ。
誰か驚いてよ。』
『誰も気にかけてない…
夏休みの間中、万博に行ってる僕が
ここにいるのに、
誰も…
僕がここにいるのに…』
『ケーンヂくーん。あーそーびまーしょ。』























































